中国の世界制覇戦略で一番怖いのが、有り余る人口を、世界に進出させて、内側から崩壊させる方法です。
平和ボケの日本は、政治家が、留学生や研修に観光客と率先して中国人を呼び込んでいるようなものです。本当に、日本の政治家はどうにもならないですね。
と、その人民輸出戦略を恐れていたら、その人口が中国の命取りになるという考えがあるようです。
何時もの阿比留さんが、詳しく書いてくれています。
産経ニュースより 2017.5.12
【阿比留瑠比の極言御免】無 謀な軍拡は老いる中国の焦りか
中国の習近平指導部がトランプ米政権に対し先月、南シナ海問題などで対中強硬姿勢を示すハリス米太平洋軍司令官(海軍大 将)を、更迭するよう求めたという。外交上、極めて異例な内政干渉である。
ハリス氏が原子力空母「カール・ビンソン」の北朝鮮付近への派遣を決めたことや、日系米国人であることが気に入らなかった のかもしれない。いずれにしても、挑戦的かつ傍若無人な要求というほかない。
直接関係はないが、ちょうど10年前の2007年5月、当時のキーティング米太平洋軍司令官(海軍大将)が中国軍幹部と会 談した際に、「ハワイ以東を米国、以西を中国で管理しないか」と2分割支配を提案された件を連想した。
経済力と国際影響力を強めてきた中国からは、自信とも背伸びとも、また焦燥とも受けとれるさまざまな発信がみられる。国際 的孤立の危険を冒してまで南シナ海の軍事要塞化を進め、領土的野心を隠そうともしないのはなぜか-。
政府関係者に薦められて米紙ニューヨーク・タイムズの元上海特派員でジャーナリスト、ハワード・フレンチ氏の著書 『Everything Under the Heavens(すべては天の下に)』を斜め読みしたところ、いくつかヒントを得た。
それによると、中国にはもともと地理的な意味でも、概念としても国境は存在せず、2千年来、中華皇帝は天の下のすべてに対する当然の支配権を持つとされてきたものである。
そして、かつての中華秩序と領域の回復という「大目標に成功するか失敗するかは、現職リーダーである習近平の正統性を決めるだけでなく、さらに、中国共産党の生死をも左右することになる」とされる。
また、「中国の究極の目標は、東南アジアや日本を新しい朝貢体制に組み込むこと」だけではなく、「この地域の米国のパワー にとって代わることである」という。
同書はこうした前提の上で、「中国の行動は、危機感や自国への疑念から生まれている」と指摘し、こうも断じている。
「習近平たちは、中国が(欧米によって作られた)『天下』の形を変えられるチャンスは、いまが一番大きく、チャンスは二度と来ないと考えている」
その上で理由をいくつか挙げているが、中でも中国が抱える最大の障害は人口問題だとし、次のように書いてあるのが興味深 い。
「中国は、想像を超えたスピードで発生する高齢化の入り口にいる。十分に近代化できていない国が、労働人口が急速に減少す る中で、社会保障システムを構築しなければならないという、歴史上、類のない状況に中国は直面する」
同書によると、中国の出生率は過去30年間に2・5から1・56に下がり、一人っ子政策の緩和(昨年1月に廃止)は期待通 りの効果を上げていない。50年には65歳以上の高齢者人口が3億2900万人に上り、労働力人口比率が世界最低水準にまで 縮小する。
当然、現在の軍拡路線は維持できなくなっていくことになる。従って中国は、老いて身動きできなくなる前に、取れるものはす べて取っておくとの決意で行動しているというのである。
こうした見方がどこまで的を射ているのかはともかく、中国と向き合う上ではこの人口問題という要素を、10年、20年とい う時間軸の中で考えることが重要なのは間違いない。(論説委員兼政治部編集委員)
なる程、中国が、こんな危機感を持っていたとは思いませんでした。最大の武器が最大の危機になるとは皮肉なものです。と喜んでいる訳には行かないですね。本気で、世界を取りに来るつもりがありそうなだけに怖いものがあります。
それにしても、2013年7月4日(木)、第5037回の「地球の人口問題」などでも書いてきたように、地球は人口が増えすぎましたね。人類が抱える根本的な問題は、この人口増にあることは間違いないでしょう。
人類も同じですが、食料があり、敵がいなければ動物は際限なく増えるのが恐ろしいいですね。やはり、人口を減らすことこそが世界平和の目指すべき方向だったりして。
顰蹙を買いそうですね!










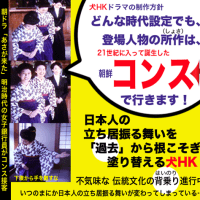
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます