第541回の「米から支援の声」や第5534回の「アメリカ人の本音」などで取り上げたように、最近テキサス親父さんのように日本を理解して応援してくれるアメリカの方達が声を上げてくれるようになって心強いばかりです。
そこに、又、加勢してくれているのがテレビでもおなじみのケント・ギルバートさんです。最近はツイッターなどでも良く取り上げられていて日本をきちんと評価していることに有難いと思っていたのですが、今度は、新聞にも書いてくれています。
これが、戦後の日本がどうしてこれ程酷くなったのかを非常に分かり易く纏めて書いてくれています。このくらい簡潔にずばりと書いてくれれば、今まで知らなかった人も分かってくれるのじゃないでしょうか。
日本ではテレビなどで有名ですのでこうした方が本当のことを発言してくれることは、情弱の高齢者には効き目がありそうです。
ZAKZAKより 2014.11.18
【反撃せよ!ニッポン】創作された「歴史」の修正を主張する時期に来た K・ギルバート氏 (1/2ページ)
近年、「歴史修正主義」という言葉を目にする機会がある。通常あまり良い意味では使われない。「ホロコーストはなかった」などの、荒唐無稽な主張がこう呼ばれる。
ナチスによってユダヤ人虐殺が行われたことは歴史的真実であり、十分な証拠がある。ところが、歴史修正主義者は自らに不利な圧倒的多数の証拠は無視し、 小さな争点を拡大解釈して不毛な論争を創り出す。結果、「歴史修正主義」は「歴史創作主義」といった、侮蔑的ニュアンスを帯びる言葉となった。
いわゆる「従軍慰安婦の強制連行」は、最初は小説内の創作だった。それが反日的プロパガンダによって、いつの間にか歴史的事実として世界中に認識され た。歴史の創作(捏造)がまさに完成しつつあったのだ。歴史の真実を伝える側が、逆に「歴史修正主義者」として非難されてきた。
朝日新聞の意図的とも思える「誤報」と、その後の放置、誤報の拡散に加担した日本人弁護士、「日本たたき」の結論ありきで、真実の追究は二の次だった国連人権委員会、加えて、日本的な「事なかれ主義」で、毅然たる対応を取らなかった外務省や政府の責任は重い。
慰安婦問題に限らず、日本の近現代史では後から創作された話が、世界では「正しい歴史」として認識されているケースが多々ある。代表例は日本が東南アジア諸国や中国大陸で「侵略戦争を行った」という話である。
はっきり言うが、これは戦後占領政策の一部としてGHQ(連合国軍総司令部)が世界中に広めたプロパガンダである。慰安婦問題と同様、真実とは異なる嘘が、今や「歴史的事実」として認識されている。
GHQの最高責任者だったダグラス・マッカーサー元帥自身が後に「日本の戦争は、安全保障(自衛)が動機だった」と米上院の特別委員会で証言したのは、彼の懺悔とも受け取れる。
しきりに「侵略戦争」や「歴史認識」などの言葉を用いて日本を責めたてる国は、GHQのプロパガンダの恩恵を最大限に受けた国である。
戦後、アジア諸国で唯一、驚異的なスピードで復興を果たして先進国となった「優等生」は、近所の「不良」から見れば心底妬ましい存在であり、ゆすり・タカリの格好の対象だった。
GHQの思惑通り、罪悪感を刷り込まれた優等生は、不良にせがまれて金を払い続けた。結果、不良は少し裕福になったが、妬ましい優等生に対して感謝の気 持ちなど持つはずがない。現在は優等生が過去の真実を知り、「今までよくもやってくれたな!」と言い始めることを最も恐れている。
最初に嘘をついて、これを広めたのはGHQだから、嘘が暴かれることを、わが祖国・米国も喜びはしない。しかし、来年は戦後70年だ。そろそろ、日本は近現代の間違った歴史認識の修正を堂々と主張すべきである。今こそ反撃せよ、ニッポン!
『ケント・ギルバートの知ってるつもり』より 2014-11-18
テキサス親父さん以外の方は、日本に住まれて奥さんが日本人という方が多いようです。やはり、自分で体験すると日本の本当が解ってもらえるようです。
それだけ、日本の広報が余りにも貧弱だったと言うことかもしれません。
何度も書きますが、こうした有難い人達を日本の広報担当として世界に発信してもらうのが一番効果があるのじゃないでしょうか。どう考えても仕事をしないどころか日本の足を引っ張っている外務省より余程役に立ってくれるでしょう。










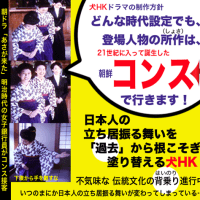
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます