北海道の南、亀田半島の突端に、椴法華(とどほっけ)という、一風変わった名前の村が存在していました。
箱館戦争が終わった7年後の明治9年1月17日、渡島国茅部郡尾札部村より一村独立した村でございます。
以来先人たちの涙と汗の村づくりが始まることになります。
函館市に継ぐ簡易水道の施設や、電気事業などのインフラの整備は、北海道一小さな自治体に、各地から視察に訪れるほどだったそうです。
平成16年12月1日。平成の大合併北海道第一号として、近隣3町と一緒に、函館市に吸収合併されました。
それに先駆けること、昭和29年から始まった昭和の大合併には、北海道知事からの再度の合併勧告にも反旗を翻し、郷土を守った先人たち。
平成の合併は「国と地方の財政難」が最大の理由だったとは、なんとも先人たちに申し訳の立たぬ話であります。
そんな小さくともきらりと光る椴法華村には「渡唐法華スピリット」という、精神が脈々と語り継がれています。
そんな話をこれより皆様にご披露いたします。

「椴法華村の由来」日持上人渡唐の伝説
鎌倉時代中頃のことでございます。
法華の行者、日蓮大聖人の並み居る弟子の中で、もっともすぐれた六高弟の一人に、蓮華阿闍利日持と申すものがおりました。
これよりその方のご生涯をお話いたします。
霊峰富士山の麓、富士川のほとりに、松野という村がございます。その村長でありました、松野六郎左衛門の次男として、日持上人はお生まれになりました。
上人は幼い頃から体格もよく、13歳の時には四書を諳んじ、諸子百家を読み、文章は巧みで、和歌にも長じ、人々からは、神童といわれたそうでございます。
たまたま仏教の経典を読み、大いに感ずるところがありまして、父母の許可を得て、出家し、仏門に入ることになります。
当時の、仏教教学の中心である、比叡山に登り、勉学に励みますが、学べば学ぶほど、当時の宗教に疑問を抱くようになります。
かつて、この比叡山で修業したという、日蓮大聖人が、鎌倉にいることを聞いて、すぐさま旅の支度をし、鎌倉に入り、大聖人のお弟子となったのでございます。
日持上人は、特に文才に富み、書道は妙技に達し、上人の書いた「持妙法華問答抄」は、大聖人のおほめをいただき、その才能は、門下第一人者であるといわれました。 つづく
箱館戦争が終わった7年後の明治9年1月17日、渡島国茅部郡尾札部村より一村独立した村でございます。
以来先人たちの涙と汗の村づくりが始まることになります。
函館市に継ぐ簡易水道の施設や、電気事業などのインフラの整備は、北海道一小さな自治体に、各地から視察に訪れるほどだったそうです。
平成16年12月1日。平成の大合併北海道第一号として、近隣3町と一緒に、函館市に吸収合併されました。
それに先駆けること、昭和29年から始まった昭和の大合併には、北海道知事からの再度の合併勧告にも反旗を翻し、郷土を守った先人たち。
平成の合併は「国と地方の財政難」が最大の理由だったとは、なんとも先人たちに申し訳の立たぬ話であります。
そんな小さくともきらりと光る椴法華村には「渡唐法華スピリット」という、精神が脈々と語り継がれています。
そんな話をこれより皆様にご披露いたします。

「椴法華村の由来」日持上人渡唐の伝説
鎌倉時代中頃のことでございます。
法華の行者、日蓮大聖人の並み居る弟子の中で、もっともすぐれた六高弟の一人に、蓮華阿闍利日持と申すものがおりました。
これよりその方のご生涯をお話いたします。
霊峰富士山の麓、富士川のほとりに、松野という村がございます。その村長でありました、松野六郎左衛門の次男として、日持上人はお生まれになりました。
上人は幼い頃から体格もよく、13歳の時には四書を諳んじ、諸子百家を読み、文章は巧みで、和歌にも長じ、人々からは、神童といわれたそうでございます。
たまたま仏教の経典を読み、大いに感ずるところがありまして、父母の許可を得て、出家し、仏門に入ることになります。
当時の、仏教教学の中心である、比叡山に登り、勉学に励みますが、学べば学ぶほど、当時の宗教に疑問を抱くようになります。
かつて、この比叡山で修業したという、日蓮大聖人が、鎌倉にいることを聞いて、すぐさま旅の支度をし、鎌倉に入り、大聖人のお弟子となったのでございます。
日持上人は、特に文才に富み、書道は妙技に達し、上人の書いた「持妙法華問答抄」は、大聖人のおほめをいただき、その才能は、門下第一人者であるといわれました。 つづく















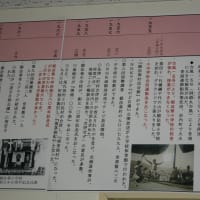




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます