▼ 普通の人間が、正義を貫き人々を救う。でも普通の力では限りがあるので、数百倍、いや数万倍にパワー・アップする。その時に発する言葉が「ヘン・シーン」だ。本来は「変身」というのだろうが「ウルトラマン」や「スーパンマン」などが代表格なので、カタカナ表記の方がヒーローっぽい。漢字表記になると、スケールが小さいような気がする。大正生まれの私の父も、酒を飲むと瞬時にパワーを増し“変身”。「ウルトラマンの父」と家族から呼ばれていたからだ。
※夜明け前。島崎藤村の妻は函館出身です。

▼ 昨日の函館市町会連合会の「第3回大間原発建設凍結実行委員会」の会議は白熱した。まだ、3回目なのに委員がすでに二人辞任し、現在、補充中なのだ。福島原発事故後、対岸に見える大間原発に対し「安心・安全なまちづくり」をめざす町会長のほとんどが反対と思っていたが、そう簡単にイカないのが“イカのまち函館”のようだ。
▼ 大雑把に分類すると、市民が主役という民主派と、体制派(頑なに維持しようとしているわけではない。ゆるやかな改革を望む派)のせめぎあいだ。町会長といえば、それぞれの地域にある様々な組織の役員を務めている。務めさせられているというのが正確かもしれない。いわゆる体制を維持・運営する役割が、町会長の責務と自覚している人が多いようだ。それが、体制側からしてみれば望ましい会長像なのだ。
▼ 第一回の実行委員会では、市長の「原発建設凍結」発言に対する討論だ。「凍結」は春になれば雪が融けると同じだと主張したが、市長に足並みをそろえるのが市町連としてのあるべき姿だとの意見が勝り「中止」から「凍結」のスタートラインに付いた。184町会の足並みをそろえるためには「薔薇はいくら名前を変えようが、何時も芳しい香を発する」という、敗戦の弁で矛を納めたのだ。
▼ 今回、新委員に推薦されてきた会長は「凍結なんて生ぬるい。現実は反原発だ。市町連が市長を擁護する団体だなんて、もってのほかだと」主張する。事務局長としての私は、単刀直入な発言は控えていたが、この主張に会議のもやもやが一気に晴れた感じがした。
▼ 体制派の中には、委員を降りたいという会長や、新委員もこの程度なら引き受けは出来ないとまでなった。「違う意見があって会議が成熟する。どちらも市民の生命を守るという町会長の使命は同じだ。違う意見があるということは、目的を達成しようとする熱意の表れだ」というような発言で、委員の離脱をかろうじて保ち終了した。
▼ 今回の主議題は「27万全市民の署名をもって、建設凍結の意思を小渕優子経産大臣に、函館市民のクリスマス・プレゼント(第3回の口頭弁論が12月25日)として届けましょう」ということだった。私としてはオシャレなプレゼントだと思ったが「今まで総理に要望しても意味がなかったので、大臣などなんの意味があるのか」との意見もあったが「署名こそ、市民の真心だ」というので、署名は実行することになった。期日は12月では準備が間に合わないということで、正月あけの第4回口頭弁論(3月予定)にあわせて実行することに決定した。
▼ だが、次の常任理事会、さらに理事会へのハードルが待ち受けている。「山は高い方が達成感がある」と、心の中でつぶやいてみる。設立53年目の市町連。現在まで、役所の下請け機関としての活躍は、賞賛に値するものがあったことは間違いない。だが、近年、成立した「函館市民自治基本条例」には「まちづくりは市民が主役」と、謳われている。「自主・自立の市町連」が、今後の半世紀に望まれる姿であろう。
※日の出

▼ 「北海道新幹線、開業まで1年半。地域の用意はOK?」というある特集に、函館市長の発言が載っている。「まちづくりは市の役目。おもてなしは民の役目。私はそう考えています」と。何と茶目っ気のある市長だろうか。現在、原発訴訟の寄付金が全国各地から寄せられ、3千万円は越えているという。絶口調!の市長をいただく函館市民だが、市も人口減で過疎地域に指定されたが、この市長の傘下であれば、函館市の春もまもなくやってくるに違いない。
同時に、大間原発建設も「凍結解除」という「変身」もありはしないか。市民の目は鵜の目でもあり、鷹の目でもなければならないようだ。















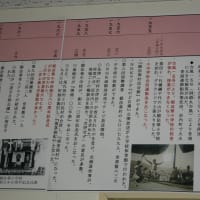




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます