▼ 昨日(土曜日)、椴法華小学校の学芸会に出かけた。廊下には子どもたちの感性あふれる作品が並んでいる。「子供は芸術家の卵だ」というのが私の持論だが、我が後輩たちの芸術家ぶりは頼もしい。私が入学したのは昭和30年だ。今は鉄筋コンクリート3階建で、津波の際の避難場所にも指定されている。当時の木造校舎の教室や教員室、軍の宿舎にもあるような大きな便所、体育館など、すべてが私の脳裏に今でも鮮明によみがえってくる。もちろんセピア色だが、先生の「廊下を走ってはいけない」という声も、聞こえてくるそんな懐かしさが小学校にはある。
▼ 廊下には椴法華村の歴史を調べ直したものがあった。私が入学の前年に、洞爺丸台風があり、私たちもお寺で授業を受けたことを記憶している。私が入学した年、NHKラジオのど自慢コンクールが体育館で行われている。合格したのは私と中学生のおねえさんだ。その時、将来歌手を目指したか、そこは記憶にない。高校時代にはバンドでボーカルを担当したが、どうやら舞台に立つのが好きなだけのようだ。そういえばサーカスの舞台にも立ったことがある。これは迷子になり紹介されただけだが。
※
▼ 32年には昭和の大合併があり、我が先人たちは「合併せず」の英断を下し、自治権を死守している。35年の国勢調査、村の人口は3,342人だ。驚くべきことはこの年の小学生の677という人数だ。私の推測では中学生は300人程度いた。未就学児童を含めると、おおよそ1,500名ほど子供がいたのだ。まさしく村の中は、子供だらけだったのだ。真夏の海岸風景が蘇ってきた。青い海、青い空、大きな砂浜に川が夏には蛇行してくれ、河口付近で天然のプールをつくってくれた。そこには数えきれぬほどの子供たちが遊んでいた。釘やガラスの破片が足に刺さっても、誰も病院などにも行かなかった。自然治癒に任せていた、そんな自然児ばかりが村にあふれていたのだ。
▼ 現在、小学生は37名だという。パフォーマンスはほとんどが、全員でおこなっているようだ。スクールバンドは、ラテンの名曲「ブラジル」にチャレンジしている。この迫力には大先輩の私の胸も、思わずカーニバル状態だ。40人学級制が言われているようだが、少数精鋭という、目の届く範囲もいいのではないかと思った昨日の学芸会だ。
▼ その夜は「函館文学学校40周年記念式典」に出席した。函館は歴史と文化の街だが、風光明美な港街でもある。何かを書きたくなる街でもある。その33期の入学生が私だ。夜間の講義を4年間続けた。合評会の厳しさには驚いた。泣いて、一日で退学した生徒もいたという伝説さえある。3年目に「あなたは10年もいるような顔をしている」というので、事務局も手伝わされた。講義の区切りのたび「補習授業」と称す飲み会では、文学談議に花が咲きすぎ、我が人生で最も楽しい思い出になった。
▼昨日一日は、椴法華小学校に始まり、函館文学学校で終了した。今のところ私の最終学歴は「函館文学学校卒」ということです。















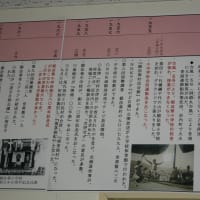




地域を大切にする心意気と言葉に磨きがかかりました。
お世辞抜きですがブログ始めた頃の記事より、問題意識が明確になり、難しい政治的問題も解りやすく、親しみながら読ませて頂いております。
選挙後に予定されている大間の原発建設反対か推進かの市民投票?行く手には更なる闘いがあるようですが、持ち前の明るさとユーモアを駆使して堂々勝ち抜いて下さい。
垂れ流しの汚染水、どれだけ海が汚されたことか!考える度に胸が圧迫されています。
地震国の怖さを突き付けても平然としている推進派の厚顔さには、良心の一欠けらも無いのでしょうか。
子ども達の未来に自然豊かな環境を残したいと切望しています。