エンジンオイルの循環方式の一つです。
現在はごく一部の高性能車(フェラーリやポルシェ辺り)にしか採用されておらず、あまり一般的な循環方式ではありません。
多くの車のエンジンオイルはウエットサンプ方式で循環されております。
オイルの循環方式に関しての詳細はこちらを参考にしてください。
ドライサンプのメリットには次の4つが挙げられることが多いです。
1.クランクシャフトなどがオイルをかき回さないため、オイル攪拌抵抗がなくなる。
2.オイルパンの厚さを薄く出来るため、エンジンの取付位置(重心)を下げることができる。
3.オイルタンクをエンジンから切り離せるため、高い旋回Gを受けても安定したオイル供給が出来る設計が可能。
4.大きいタンク容量を持たせることが出来るため、オイルの温度上昇がおさえられる。
これらの事(特に“1.”ね)を考えると、今後の低燃費モデルには採用されない理由が見当たりません。
「限られたステージで耐久性を顧慮しなければ採用可能な技術」や「理論としては完成されている技術」を一般的な乗用車に採用する為の技術開発が今日の自動車の進化に繋がって行ったものだと思います。(ロータリーやミラーサイクルなど)
ドライサンプのデメリットとして謳われているのは、部品点数の増加によるコスト増やトラブル発生確立の向上です。
これらこそ、地道な開発で潰して行けること(行くべきこと)なのではないでしょうか。
高効率化を実現させるために採用された技術の多くは革新的なものではなく、レーシングカーなどでは使われていたものだったと言う事も多いしね。
B14サニーが登場したとき、GA15DE型エンジンはマルチポイントインジェクション、ピストンリングが2本の腰下(一般的なものと比べてコンプレッションリングが1本少ない)、狭角のDOHC4バルブで直立ポートを採用しておりました。(燃焼室の形状はペントルーフでしたっけ?)
ふた昔前ならレーシングエンジンや“超”高性能車にしか採用されされなかったようなメカニズムがテンコ盛りでした。
もちろんこれらの技術はサニーのホットモデルにのみ採用されたのではなく、最も売れるモデルの低燃費化・高効率化を実現するために採用されたのです。
ここ数年の低燃費化・低公害化の中で、各メーカーがあまり手の付けていないところを考えると、“油と水の循環方法”が真っ先に思い付き、対案が確実にあったのは“油”のほうだったのでネタにしてみました。
補足
こういった状況証拠(多くは“過去の事例”とも言う)から考えると、低燃費化や高効率化の切り札として使われるかもしれないと、本日の帰宅途中にポルシェの後ろを走っていたときに思いつきました。
でも空冷4気筒のドライサンプエンジンの失敗で、本田宗一郎氏は自分の理想を諦める結果に繋がったような。。
現在はごく一部の高性能車(フェラーリやポルシェ辺り)にしか採用されておらず、あまり一般的な循環方式ではありません。
多くの車のエンジンオイルはウエットサンプ方式で循環されております。
オイルの循環方式に関しての詳細はこちらを参考にしてください。
ドライサンプのメリットには次の4つが挙げられることが多いです。
1.クランクシャフトなどがオイルをかき回さないため、オイル攪拌抵抗がなくなる。
2.オイルパンの厚さを薄く出来るため、エンジンの取付位置(重心)を下げることができる。
3.オイルタンクをエンジンから切り離せるため、高い旋回Gを受けても安定したオイル供給が出来る設計が可能。
4.大きいタンク容量を持たせることが出来るため、オイルの温度上昇がおさえられる。
これらの事(特に“1.”ね)を考えると、今後の低燃費モデルには採用されない理由が見当たりません。
「限られたステージで耐久性を顧慮しなければ採用可能な技術」や「理論としては完成されている技術」を一般的な乗用車に採用する為の技術開発が今日の自動車の進化に繋がって行ったものだと思います。(ロータリーやミラーサイクルなど)
ドライサンプのデメリットとして謳われているのは、部品点数の増加によるコスト増やトラブル発生確立の向上です。
これらこそ、地道な開発で潰して行けること(行くべきこと)なのではないでしょうか。
高効率化を実現させるために採用された技術の多くは革新的なものではなく、レーシングカーなどでは使われていたものだったと言う事も多いしね。
B14サニーが登場したとき、GA15DE型エンジンはマルチポイントインジェクション、ピストンリングが2本の腰下(一般的なものと比べてコンプレッションリングが1本少ない)、狭角のDOHC4バルブで直立ポートを採用しておりました。(燃焼室の形状はペントルーフでしたっけ?)
ふた昔前ならレーシングエンジンや“超”高性能車にしか採用されされなかったようなメカニズムがテンコ盛りでした。
もちろんこれらの技術はサニーのホットモデルにのみ採用されたのではなく、最も売れるモデルの低燃費化・高効率化を実現するために採用されたのです。
ここ数年の低燃費化・低公害化の中で、各メーカーがあまり手の付けていないところを考えると、“油と水の循環方法”が真っ先に思い付き、対案が確実にあったのは“油”のほうだったのでネタにしてみました。
補足
こういった状況証拠(多くは“過去の事例”とも言う)から考えると、低燃費化や高効率化の切り札として使われるかもしれないと、本日の帰宅途中にポルシェの後ろを走っていたときに思いつきました。
でも空冷4気筒のドライサンプエンジンの失敗で、本田宗一郎氏は自分の理想を諦める結果に繋がったような。。
















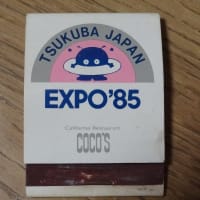



まずポンプの増設
ポンプは最低2つ必要になり
効率よい潤滑となると3つは欲しい
レーシングエンジンとなると4つ以上の潤滑ポンプなんてあたりまえだし
吸い出しにつかうスキャラベジポンプはオイル圧送ポンプの倍以上の容量が必要で
ポンプを動かすためのフリクションロスが大きく増えるため
攪拌抵抗がなくなるメリットはうすい
スキャラベジポンプは何でも吸い上げてしまうため
オイルに空気が混じるため気液分離が必要になる
オイル量が倍になるため廃油が格段に増える
最低重量が決められ無駄なモノがないレーシングカーならともかく、なによりも格段にエンジンまわりの重量増が大きいため、重量増による燃費悪化を招く
潤滑の効率をあげようとするとポンプで重量ふえるし
ドライサンプの構造として~タンクから圧そうポンプより回収のためのスキャベラジポンプの容量を大きくする必要があり
空気も吸い上げる
ポルシェなんかはかなり大容量のスキャベラジポンプをつかっています
オイルの気泡が混じり潤滑効率や潤滑不良を起こす
気液分離装置がつけられていますが…それでも完全に気泡を取り除くことはできないため
酷使した場合や長時間の使用では気泡による潤滑効率の低下はさけられません
はじめまして。
そして、長文のコメントありがとうございます。
圧送側と吸出側の1基ずつのポンプで成立するもんだと思っておりました。
ウエットサンプが主流なのはそれなりに裏付けられた理由があるものなんですね。
ホンダ77を見た直後だったので、その辺の影響を受けていたと思います。(あれも強烈なフロントヘビー車でしたけど。。)
全部燃やしちゃうから、オイルパン自体いらない
ヘッドも必要ない
EFI直噴とEOIでのクランク直噴で解決しそうですね
正常化は、クリーンディゼルの焼き切り触媒の応用でいけそうな気もしますしね
ただメチャたかそう
コメントありがとうございます。
ふり記事なので、よくぞ見つけていただきました。
いろいろ条件があるということは、それだけ見たいがあるということですよね。
個人的には、ドライサンプではなくてもいいですが、環境性能のいい2STの登場に期待したいです。
新技術の普及により、縦方向だけではなく、横方向にも伸びていくのには期待したいです。