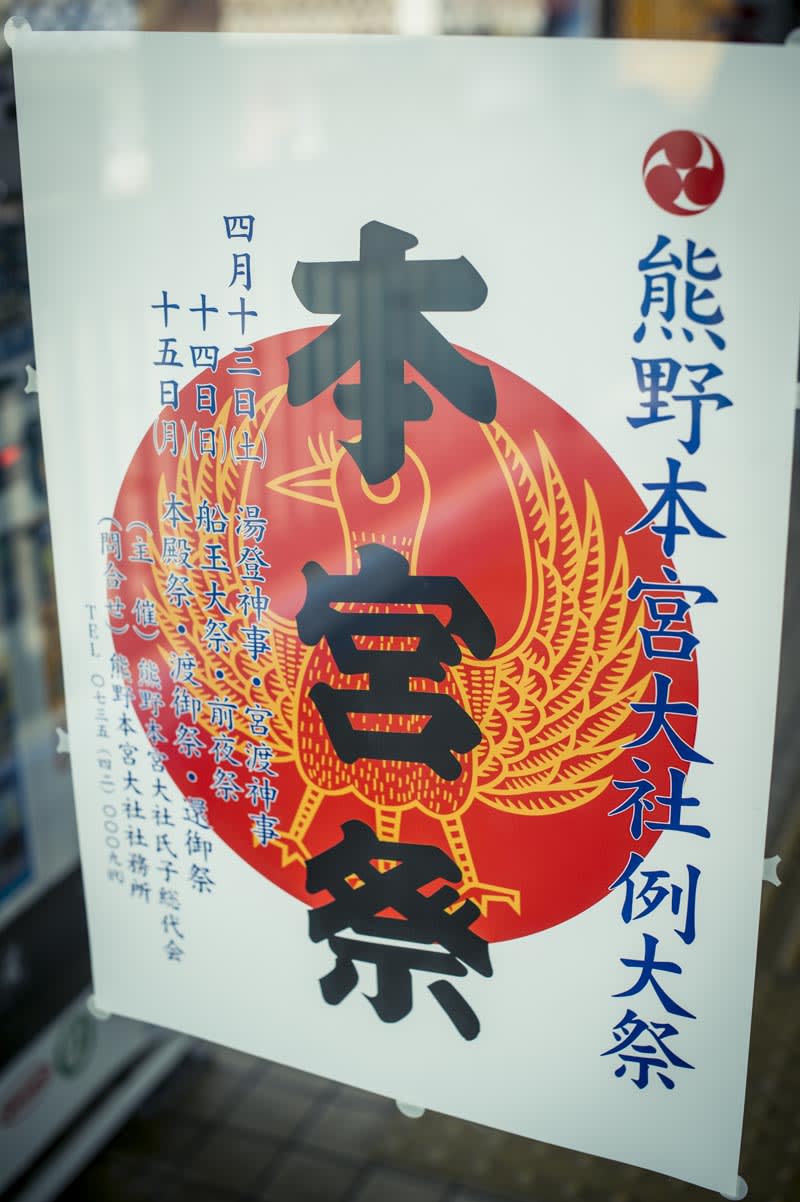おおゆのはら…と読む。明治22年の大水害で流されるまで本宮があった場所。
熊野川・音無川・岩田川の中州に今の8倍の大きさで、存在していた。
中州に建立すること自体無謀な話だが、人間の驕りがそうさせたに違いない。
「明暦丙申立」と裏にある石碑に、「禁殺生穢悪」とあった。
神社の中で、殺生や、穢れや、悪を禁ずるとの意味であろうが、
紀伊半島の土地土地を経巡る途中の私には、それはことさら眼に付いた。
つまり、楷書でしっかりと書き彫り上げた石碑の筆遣いから、
その筆を持って文字を書く人間の、自信と驕りに対する驚きと、反感だった。
自然は、八百万の神々はそんなに生易しくない。自然はもっと生き生きとある。
そう思った。神々は一度や二度、打ち倒されてもなおもぞもぞと生きながらえてある。
自信と驕りとは、つまり堕落のことだろう。本宮という神の場所ではなく、碑に文字を書いた人間、
それを建立した者の人為が、この本宮という場所を、閉塞させている、と思った。
神の場所とは、貴と賤、浄化と穢れが還流し合って、初めて神の場所として息づく。
(紀州「本宮」中上健次)
実際、一遍上人の時代は、貴賤入り乱れた場所だったらしい…のだけど。
熊野川・音無川・岩田川の中州に今の8倍の大きさで、存在していた。
中州に建立すること自体無謀な話だが、人間の驕りがそうさせたに違いない。
「明暦丙申立」と裏にある石碑に、「禁殺生穢悪」とあった。
神社の中で、殺生や、穢れや、悪を禁ずるとの意味であろうが、
紀伊半島の土地土地を経巡る途中の私には、それはことさら眼に付いた。
つまり、楷書でしっかりと書き彫り上げた石碑の筆遣いから、
その筆を持って文字を書く人間の、自信と驕りに対する驚きと、反感だった。
自然は、八百万の神々はそんなに生易しくない。自然はもっと生き生きとある。
そう思った。神々は一度や二度、打ち倒されてもなおもぞもぞと生きながらえてある。
自信と驕りとは、つまり堕落のことだろう。本宮という神の場所ではなく、碑に文字を書いた人間、
それを建立した者の人為が、この本宮という場所を、閉塞させている、と思った。
神の場所とは、貴と賤、浄化と穢れが還流し合って、初めて神の場所として息づく。
(紀州「本宮」中上健次)
実際、一遍上人の時代は、貴賤入り乱れた場所だったらしい…のだけど。