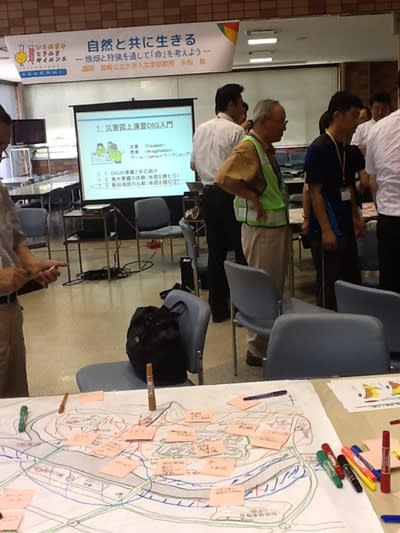2月23日(土)宮崎県国富町にて、「古墳と歴史でまちづくりin国富」を開催しました。主催は、宮崎県地域づくりネットワーク宮崎・東諸県ブロック会議。私はコーディネーターとして昨年10月よりこの行事を進めてきました。また、当日は私と宮崎県NPO活動支援センターのKさん、Kさんの友人Nさんの3名で運営しました。

この行事には地元国富町の他、宮崎市、延岡市、また留学生を含め27名、内訳は小学生から89歳までと幅広い年齢構成でした。
ちなみに国富町は、人口18,859人(2018年10月1日)、農業が中心で、葉タバコ・切干大根は全国1位とされています。町役場の位置する本庄地区は江戸時代、天領で、本庄川を利用した水運による物資の集散地としてにぎわいました。現在は本庄川を利用して、太陽電池パネルを生産する会社が進出しています。
上記は、くにとみ史跡・文化ガイドの会の皆さんのご挨拶風景。
今回の行事は宮崎・東諸県ブロック内で地域づくりをおこなっている団体を応援することで地域活性化へ弾みをつけようというもので、昨年の10月より隣接する高岡町への支援と併せて取り組んできました。
13時より交流プラザくにとみ屋にて、主催者あいさつや行事の説明・参加者による自己紹介後、くにとみ史跡・文化ガイドの会の案内にて町巡りに出かけました。
町内には歴史遺産が多く、なかでも本庄古墳郡は4世紀後半から6世紀にかけて造られ、前方後円墳17基、円墳37基、横穴2基の合計57基点在しています。なおこれらの古墳は諸県地方一帯を支配していた諸県君の歴代の墓として造られたものと考えられているそうです。

町巡りでは、上記の稲荷神社のほか、義門寺、上長塚古墳、下長塚古墳、地下式横穴墓などを案内していただきました。
なかでも、地下式横穴墓は、宮崎県南部から大隅半島北部に分布しており、南九州独自の墓のスタイルと言われています。国富町内には、約100基の地下式横穴墓が確認されています。特に本庄地区には約40基も集中しています。そのためか耕作中や造成中に偶然見つかることが多いそうです。(トラクターが穴に落ちるなど・・凄いですね)本庄小学校では、講堂の建設工事中や、また校舎の改築工事中に地下式横穴墓が発見されるなど、この小学校の中だけでも4基の地下式横穴墓がみつかっています。

90分間の町巡り後、150年以上の歴史を誇る、国富町を代表する和菓子「白玉饅頭」の試食会をおこないました。とても好評で販売用に準備したまんじゅうも完売しました。
私はワールドカフェを盛り上げるため、カフェ店員の衣装を着て参加しました。
ワールドカフェによる話合いでは4つのグループに分かれて、「史跡・文化ガイドをより魅力的にするには」というテーマで、意見を述べ合いました。最初は馴染めなかった参加者も、少しずつ要領がつかめたようで、何度も時間を延長しておこないました。
グループ発表の様子。いずれのグループでも「町中に古墳が点在し、いつでも見れられること、身近に古墳を感じられ親しみを感じた」との意見が出されました。
チーム「アジア」のグループ発表では小学生が発表を担当。ハキハキと意見を述べ、大人達も感心していました。
グループ発表では、それぞれのグループとも違った視点で国富町での町めぐりのことを捉えていました。
このワールドカフェで出された意見をいくつか紹介します。
くにとみ屋屋上からの古墳の眺めはとても良いビューポイントだと思います。
古墳と共存した町は大きな特徴なのでもっとアピールしましょう。
古墳が発見されたエピソードも面白いので、古墳と一緒に紹介して欲しい。
特産の「竹」を生かして工芸品や料理、風景と一緒に売り出しては・・
町並みがキレイ、古墳の管理も行き届いているのでPRしましょう。
桜やしゃくなげなどの花の見頃に合わせて、ウォーキングをしてはどうでしょうか
歴史遺産が町中に集中し、歩いて行けるところが魅力。散歩コースにもなります。
宮崎大学には200名の留学生がおり紹介したい。
途中休憩できるイスが欲しい、気軽に立ち寄れ人と会話できるスペースがあったらいいと思う。
写真や小物をつかって説明してくださるので、親しみが持てる
地下式古墳の中を見ることができ、また古墳の種類がたくさんあることを知った。
白玉饅頭がこんなに美味しいとは思わなかった
などの意見が寄せられました。最後に、くにとみ史跡・文化ガイドの会の方々にワールドカフェでまとめられた模造紙をお渡ししたところ、今後の活動に活用しますとの感想をいただきました。
今回は、地域で頑張っているグループそのものを具体的に応援するという新たな試みを行いました。今後もガイドの会の皆さんとなんらかの形で関わりながら、地域づくり活動を進めていきたいと思います。長いようで短かった5ヶ月間。多くの方にご支援いただきながら、無事終了することができました。ご協力いただいた皆さまありがとうございました!