年があけてからこの方、晴れの日が続いている。そのせいか、放射冷却もあって早朝はとても冷える。家の軒下を貸しているのら猫たちにも近頃はカイロを入れてやっているのだと家人は云う。
今日の最高気温は11度だったから陽光の入る南向の部屋に居るかぎりは寒すぎるということはなかった。しかし、少し陰るだけで体感温度がサッと下がって電気ストーブのスイッチに手が行く。
子供の頃のこんな冬の日、居間には炬燵があっても、子供部屋は火鉢の炭火が唯一の暖房装置だった。綿入れを羽織って、火鉢で手をあぶりながら勉強をしていたことを思い出す。今となっては、炭の火鉢など博物館ものなのかもしれない。大岡信の「折々のうた」の中、冬のうたのひとつに太田水穂のこんな歌が載っている。
「おのが灰 おのれ被りて 消えてゆく 木炭の火に たぐへて思ふ」
太田水穂は信州出身の歌人で、島木赤彦や窪田空穂と同世代。和歌や俳諧の歴史研究に業績が大きかったとある。この歌は昭和30年の歌集『老蘇の森』に収録されているもの。
『老蘇の森』とはなんだろうと思いWEBで探すと、こんな説明を見つけた。
「滋賀県安土にあるこの森は、万葉の昔から多くの歌人や旅人によって歌に詠まれ、歌枕としても名高い。今から約2300年前 孝霊天皇の御世に石辺大連という人が神の助けを得て松、杉、檜などの苗木を植え祈願したところ、たちまち生い茂り大森林になったと伝えらる。この石辺大連は百数十まで生き長らえたといい、此処を、老が蘇る森、「老蘇の森」と呼ぶようになった。平安時代には既に広く知られ、歌所として和歌、紀行文、謡曲にも詠まれ 多くの旅人が足を留めた。 ホトトギスの名所としても知られる。」
老境の自分自身を白い灰をかぶりながら静かに消えてゆく炭の命になぞらえながら、やがて来る生涯の終わりを思いやる歌である。ひえびえとした寂寥を歌うのではなく、作者の芸術観をも示した歌だと、大岡はまとめている。
黒い木炭は、赤々と炎を上げて燃えながら、やがて表面から白く柔らかな灰に変ってゆく。黒から赤になって最後は白。こう見ると、たしかに人の一生と似ていなくもない。白い灰になってからも、火鉢の温かさは長く残っているのも、老年の充実感を示しているようではないか。
ところで、子供部屋にあった、あの青い染付け陶器の火鉢はどこに行ってしまったのだろうか。考えれば、子供が抱えて移動できるほどの適当なサイズだったなと思う。昔の器具の無駄のなさだ。
今日の最高気温は11度だったから陽光の入る南向の部屋に居るかぎりは寒すぎるということはなかった。しかし、少し陰るだけで体感温度がサッと下がって電気ストーブのスイッチに手が行く。
子供の頃のこんな冬の日、居間には炬燵があっても、子供部屋は火鉢の炭火が唯一の暖房装置だった。綿入れを羽織って、火鉢で手をあぶりながら勉強をしていたことを思い出す。今となっては、炭の火鉢など博物館ものなのかもしれない。大岡信の「折々のうた」の中、冬のうたのひとつに太田水穂のこんな歌が載っている。
「おのが灰 おのれ被りて 消えてゆく 木炭の火に たぐへて思ふ」
太田水穂は信州出身の歌人で、島木赤彦や窪田空穂と同世代。和歌や俳諧の歴史研究に業績が大きかったとある。この歌は昭和30年の歌集『老蘇の森』に収録されているもの。
『老蘇の森』とはなんだろうと思いWEBで探すと、こんな説明を見つけた。
「滋賀県安土にあるこの森は、万葉の昔から多くの歌人や旅人によって歌に詠まれ、歌枕としても名高い。今から約2300年前 孝霊天皇の御世に石辺大連という人が神の助けを得て松、杉、檜などの苗木を植え祈願したところ、たちまち生い茂り大森林になったと伝えらる。この石辺大連は百数十まで生き長らえたといい、此処を、老が蘇る森、「老蘇の森」と呼ぶようになった。平安時代には既に広く知られ、歌所として和歌、紀行文、謡曲にも詠まれ 多くの旅人が足を留めた。 ホトトギスの名所としても知られる。」
老境の自分自身を白い灰をかぶりながら静かに消えてゆく炭の命になぞらえながら、やがて来る生涯の終わりを思いやる歌である。ひえびえとした寂寥を歌うのではなく、作者の芸術観をも示した歌だと、大岡はまとめている。
黒い木炭は、赤々と炎を上げて燃えながら、やがて表面から白く柔らかな灰に変ってゆく。黒から赤になって最後は白。こう見ると、たしかに人の一生と似ていなくもない。白い灰になってからも、火鉢の温かさは長く残っているのも、老年の充実感を示しているようではないか。
ところで、子供部屋にあった、あの青い染付け陶器の火鉢はどこに行ってしまったのだろうか。考えれば、子供が抱えて移動できるほどの適当なサイズだったなと思う。昔の器具の無駄のなさだ。


















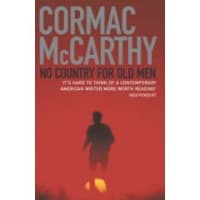

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます