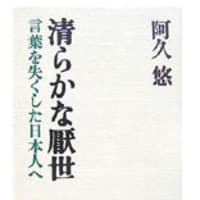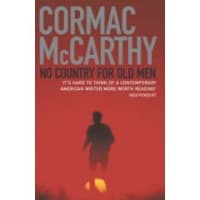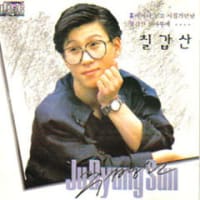9日のコロナは、全国で2242人(延768618人)の感染と96人(累13868人)の死亡が確認された。愛知県では247人(延49336人)の感染と8人(累866人)の死亡の発表があった。
余裕をもって家を出たはずが、駅に着くと電車は出たあとということが最近よくある。構内が工事中でホームまで遠いということもあるが、それよりこちらの歩き方が遅くなったというのが正直な理由だ。
頑張って歩いているつもりが、後からくる人に簡単に追い抜かれ、慌てて追ていくのにどんどん離されてしまう屈辱感、年寄の実感である。そのくせ、仕事を辞めて以来、腕時計を持たなくなっているのだから、せっかちな割りに時間管理も上手くはできていないのだ。
明日は「時の記念日」だ。
「漏刻」と呼ばれた水時計による時の知らせが行われたことを記念して制定されたのが「時の記念日」だ。1920年(大正9年)6月10日だった。
日本では時間と時刻のことばの使い分けがあいまいで「時刻に贈れる」というところを「時間に遅れる」と言う。列車のダイヤ表も、昔は時間表と呼んでいたものが、時刻表に変わったのは、それだけ正確な言い方になったといえるとは「ことばの歳時記」の金田一春彦先生である。
今も昔も日本の列車ダイヤが極めて正確だというのは世界に誇れる日本的特質である。先生はここで、ロシア(旧ソヴィエト)を旅した友人の時間にかかわるエピソードを紹介している。
シベリアの田舎では時刻表などあっても全くアテにならず、とんでもない時に列車が到着するので、こっちもついのんびり、うっかり駅前でで食事でもしていると、カンカンカンというあっさりした警笛を鳴らしたままで乗るべき列車は行ってしまい、結局一晩そこで泊まるハメになるのだという。
もっとも上には上があって、南米ボリビア辺りだと、そも列車時刻表というものがまったく無く、列車は勝手な時刻にやってきて勝手な時刻に出ていくのだそうだ。
二つのエピソードも半世紀以上前のはなし、今では、シベリアもボリビアも、時刻に拘った列車の運行が行われ、ゆっくり流れていた時間の感覚は慌ただしいデジタルの時刻感覚に入れ替わってしまっていないだろうか。