昨年6月4日のブログに「金婚の記念になった片瀬公民館での講演会」を載せましたが、その後、片瀬公民館の主催する移動公民館の催しとして、夫に「江の島で島の今昔の話をしてもらえないか」という依頼がありました。
江の島で商売をしている人も参加できるようにということで、日程は2月2日(水)午後6時半から8時まで、県の施設である江の島ヨットハーバーの会議室を借りて講演会が開かれました。その報告をします。
前もって片瀬公民館のスタッフと綿密な打ち合わせを重ね、話す内容に関連した風景などをスタッフが写真に撮って準備をして下さいました。コロナ禍で人数の制限はありましたが、二十数人の参加者を迎えて講演会が実現しました。
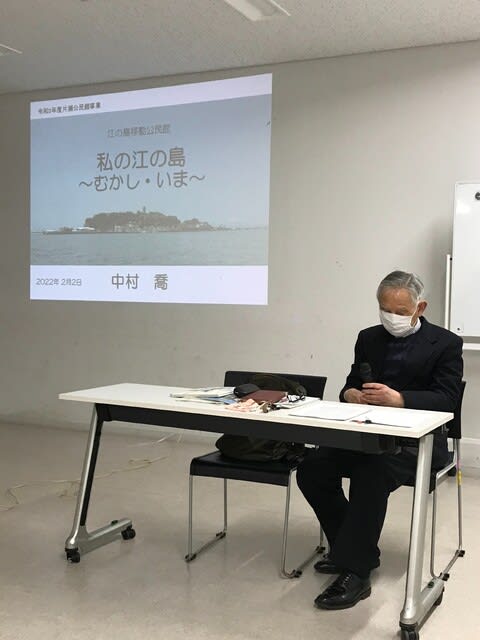
今回も会場の後方には「片瀬だより」にのせた片瀬今昔の挿絵を額装して飾って頂きました。


夫は必ず講演の発表原稿を作り、前もって私に聞かせてくれます。以下にレジメと発表原稿から抜粋を載せます。
⑴ 自己紹介に代えて
岩屋前の「亀石」の話
海中の亀石は 大きな亀が竜宮城にかえっていくようだと有名になった亀で、江の島神社発行の冊子「江之島」に「中村亀太郎が鑿をとった亀」という記述があるということでした。昭和8年当時、地元の秋元石材店で修業していたのが中村亀太郎と中村増次郎の兄弟二人で中村亀太郎は伯父、増次郎は私の父親です。二人の兄弟の父親・中村光五郎は江の島の出なのです。
私(夫)は終戦の翌年の昭和21年4月に片瀬小学校に入学し、片瀬中学校を卒業したのが昭和30年のことです。江の島の友達もたくさんいます。山二つの崖の上にあった「相模」というお店を営んでいたY君は忘れられない友達の一人で、中学校の同期の仲間がよく集まって食したサザエの壺焼きやバイ貝の塩ゆでの味は忘れられません。
⑵「ふるさと片瀬・今昔あれこれ」連載の背景
・妻の絵と二人三脚で
公民館の発行する片瀬便りに「ふるさと片瀬・今昔あれこれ」の連載を始めたのは平成25年で、今まで34回に渡って思い出すままに江の島・片瀬の様々なエピソードを綴ってきました。妻が絵を描いてくれるので、紙面に親しみやすさが増すのではないでしょうか。実は妻が絵を描き、私が言葉を添えるという営みは長いこと続く我が家の年賀状のスタイルなのです。
平成31年の賀状には「江島神社瑞心門」の絵に「冬晴れや神官ひとり祝詞あぐ」の一句を添えて発信しました。
令和2年は片瀬漁港と富士山でした。新年の句は片瀬海岸に紙飛行機を飛ばして「放たるる紙飛行機の初御空」でした。

この営みが「ふるさと片瀬・今昔あれこれ」の連載に結びついて、絵と文章の二人三脚が続いています。絵を描いております妻も今日会場に来ておりますので、一言だけ挨拶をさせて下さい。(妻道子が「片瀬・江の島には絵になる風景が沢山あって幸せです。いつまで続くかわかりませんが、どうぞよろしくお願いいたします」と挨拶しました。)
・「最初の質問に」に導かれて
実は私には大好きな一編の詩がありまして、その詩を読んでいると昔の色々な思い出・記憶や今の暮らしへの思いが湧くいてくるのです。そして毎回の文章が出来上がるのです。
その詩というのは長田弘さんの「最初の質問」です。
今日、あなたは空を見上げましたか。空は遠かったですか、近かったですか。雲はどんな形をしていましたか。風はどんなにおいがしましたか。あなたにとって、いい一日とはどんな一日ですか。「ありがとう」という言葉を、今日、あなたは口にしましたか。
この一節で始まり次々とやさしい言葉で質問を続けます。
その中で長田さんは「人生の材料は、なんだと思いますか」と問います。皆さんはどのように答えられるでしょうか。はじめにもお話したように私にとって大事な人生の材料は、出会いだと思うのです。

⑶ 私の江の島~むかし~
🔹 夢の島だった「江の島」
・ 島には異人館があって、屋根は黒い色のスレートで葺かれているらしい。
・ 初午の日には東町と西町の若者がそれぞれお稲荷さんに詣でて、参道を挟んで太鼓を叩き合うという。
・ 八坂神社の祭礼が近づけば、女の子は子供囃子の三味線の稽古に余念がないという。
江の島は片瀬の子供たちにとって夢の島でした。その江の島と片瀬の文化が片瀬小学校で合体し、子供の世界はま
すます楽しくなっていったのです。と言うのも江の島には分校があって小学校の四年生まではここで学んでいたの
です。五年生になると島の子供たちは本校に通ってきたのでした。
🔹 終戦後の江の島分校の学校給食
終戦後の食糧事情は貧しいものでした。コメはもちろん野菜も手に入りにくかった時期がありました。近隣の農家
に出かけていって物々交換で手に入れたサツマイモが主食になることも珍しくありませんでした。
そんな時代、片瀬小学校で給食が始まりました。昭和二十二年のことです。私は当時二年生でした。給食といって
も毎日提供されるものではなく月に一回程度だったようです。給食は江の島分校でも実施されました。当時を記録
した資料が藤沢市教育文化センターに保管されています。
・昭和二十二年六月二十日の江の島分教場の給食日誌には、献立は「鮭汁」材料は鮭缶九個、たまねぎ二〆、菜五百
匁と記されています。
「今日は児童丹精になる運動場一隅の菜を若干汁の中に入れた。児童の喜びは格別であった。その喜ぶ姿を見て母
親たちの明るい顔、学校へきてみなければこの姿はわからないとは、母親たちの心からの声であった。」
島のお母さんたちが給食のお手伝いをしていたのですね。
給食人員は一〇九名(一年三十七名・二年二十一名・三年十八名・四年二十五名)でした。荒廃した国土の中で子
供たちの成長を念じ、力を合わせて頑張った学校や地域の姿が伝わってきます。
🔹『かわいい科学者・特集号江の島』の発行 (昭和26年4月1日)にまつわるエピソード
戦後の教育で言えば、当時片瀬中学校が取り組んでいた「かわいい科学者」という冊子の発行を中心とした理科を
核にした教育も天下に名をはせていました。ある時『かわいい科学者・特集号江の島』の発行が計画されましたが、
学校にはお金がありません。先生たちが県にかけあってもらちがあきません。費用を捻出するため、藤沢市の観光課
が「江の島には修学旅行生が大勢来ており、帰りに宿屋の方で担任とか学校に手土産を持たせている。それを割愛し
て『かわいい科学者・特集号江の島』をわたそうじゃないか」ということになって、働きかけてくれたところ、発行
に充てる費用の大半は旅館がもってくれたという話が残っているのです。
この優れた実践が評価されて、第一回日本学生科学賞入選で表彰をされたことが当時の新聞によって報道されていま
す。この冊子の中で一人の生徒が「僕は江の島をこうしてみたい(私たちの夢)」と題して論文を発表しています。
項目は次のようなものです。
・水族館を作りたい ・遊覧船を運航させたい ・釣り場を設けたい
・植物園など公園を整備したい ・海洋科学研究館をつくりたい ・片瀬川河口に港をつくりたい
当時の片瀬中学校の生徒の描いた夢は、令和の時代の今ほとんどが実現しているのですから驚くばかりです。
🔹 江の島花火大会のこと
・花火大会は八月十五日と決まっていた。
・川を流れる灯籠と打ち上げ花火が美しかった。
・仕掛け花火の「富士山夏、冬の景」「ナイアガラの滝」も忘れられない
⑷ 私の江の島~いま~
今、私は折に触れて片瀬海岸や江の島を歩くことを楽しんでいます。島で暮らす皆さんには見慣れた風景でしょう
が、私の目に、そして心に、大変新鮮に飛び込んできてくれます。レジメに書き記した短歌は今まで読んできた作品
の一部です。( )の年月日は神奈川新聞の神奈川歌壇に取り上げられ掲載された日付です。
【江の島の空】
結び神宿る公孫樹の二本に分かれて芽吹く江の島の空 (2016.5.8)
上半分バッサリ切られ神木の結び銀杏の冬空広し (2018.12.2)
階段を上ればすでに変わりいる秋の江の島雲の風景 (2016.10.16)
コロナ禍に戦く地球を次々と照らして初日は江の島に来る (2021.1,1)
【江島神社を拝す】
江の島に射し初むる陽を背に受けて神官一人祝詞を上ぐる (2014.8.3)
神木の結び銀杏は切られしも風に絵馬鳴る春の江の島 (2020.2.6)
紫陽花に美央柳の寄り添ひて江島神社の夜は明けにけり (2018.7.29)
辺津・中津・奥津宮へ詣でむと富士に真向う岩屋道行く (2019.1.6)
青銅の鳥居の先に朱の鳥居見えて緑の江の島は雨(2017.7.9)
横文字も漢語も混じる短冊の揺れて江の島七夕祭 (2015.7.19)
【江の島の猫・リス・鴎】
我が影の寄るを怖れず江の島の夕日に伸びる猫の影あり (2015.1.11)
栗鼠走り桜を散らす江の島の弁財天は琵琶抱きて座す (2015.1.11)
三羽ずつ鴎の憩う街路灯消えて江の島の朝は始まる (2014.11.30)
栗鼠走り鳶は無言で弧を描く江の島の朝海に舟無し(2017.5.21)
【天台山の六地蔵】
江の島の天台山なる六地蔵欠けたお顔で海見てござる (2019.8.1)
江の島の石蕗咲く崖に無縁塔粛然と立つ海に向かいて (2017.12.3)
【四角いポスト】
江の島に黒く四角いポスト立ち郵政記念日明治の風吹く (2021.5.23)
【聖天島の祠】
江の島の古き地層に抱かれて聖天島に小さき祠 (2015.10.30)
江ノ島を確と掴みて大樹立つ弁財天の化身のごとく (2016.4.24)
【山二つ】
江ノ島に山二つあり断崖に落ち行く鳶の先は荒磯 (2017.9.17)
山二つ半分明けて潮騒の崖上り来る暁の江の島 (2013.11.24)
【湘南しらす】
湘南のしらす料理に人群れて海黙々と命育む (2018.2.1)
湘南のしらす解禁「生しらすあり」の貼り紙江の島うごく (2017.5.1)
釜揚げの昔のシラスの楽しみは中に混じれるタコやエビカニ (2010.11.14)
【五輪の島】
五輪目指し白帆飛びゆく江の島の二百十日の海に風湧く (2019.9.29)
江の島の猫の寝そべるハーバーの沖を五輪の帆が風を切る (2021.8.22)

五輪待つ島にヨットのモニュメント夕日を受けて赤く輝く (2020.3.1)

【島は慶ぶ】
奉祝の幟連ねて弁天の重文指定島は慶ぶ (2019.5.1)
奉祝の令和の富士に一礼し三社詣での江の島へいざ (2019.5.26)
【海は生きてる】
同じ波寄することなし夕暮れの湘南海岸海の拍動 (2019.5.26)
潮動き魚も動く朝まずめ漁船は急ぐ日の出の海へ (2009.5.3)
白き帆の沖合はるか連なりて連符のごとく波に歌へり (2017.11.5)
潮目には鰺鯖鰯群れ泳ぐ江の島沖合三キロの秋 (2017.11.12)
寒月の照らす海なり江の島の養殖若布包みて光る (2015.3.8)
一本の櫂を操り板に立ち日の出の海へ青年は出る (2015.11.8)
網上げる船に鴎の群れ寄りて江の島の海照りまた曇る (2014.12.7)
朗々と祭甚句は風に乗り寒中御輿海に入りゆく (2018.3.1)
江の島へトンボロの海渡り行く令和の子らの足どり軽し (2019.6.23)
【今年の新春詠草】
丹沢と箱根連山従えて雪の富士座す江の島の春 (2022.1.1)

江の島のイルミネーション粒となりわかめの眠る海に降りしく (2-22,1.1)
ところで、私は昨年、タウン誌の「ふじさわびと」で特集江の島を読ませていただきました。
長田弘さんの問いかける【あなたにとって「わたしたち」というのは、誰ですか。】の答えがみごとに掲げられてい
て、江の島に暮らす皆さんの団結力、島の暮らしを大事になさる心を強く感じさせて貰いました。青銅の鳥居の前で島
の消防団員を中心にして写真に納まる島の皆さんの笑顔が素晴らしかった。
消防団の分団長さんは「私たち自身の力で島を守らなければいけない」と決意を述べています。父上が分団長だった
という団員さんは「江の島そのものが【家】のような ものだものだと語ります。学校帰りに「おかえり!」「おかえ
り!」と声を掛ける商店街の大人達がいました。江の島に移住してきたというお一人は「島に骨をうずめる覚悟なら消
防団に」と言われてメンバ―に加わり、島の暮らしにすっかり馴染んでいると振り返ります。
江の島には「最初の質問」の問いかけに対する豊かな答えがあふれています。
今日のこの席を用意してくださった公民館の皆様、開催にご尽力くださった片瀬地区自治連合会の会長さん、そし
て、お集まりいただいた地域の皆様に感謝しつつ、私の話を閉じたいと思います。
こうして江の島での講演会は無事に終了し、イルミネーションの光の粒が降る江の島を後にしました。帰宅は九時
近くになりましたが、ビールで軽く乾杯をして一日を終えました。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます