夏から一気に読んだ文楽の本です。かなり“忘却の彼方”にありますが、このブログ、そもそも「読書日記」「観劇日記」をつけたくて始めたものなので、とりあえずごくごく簡単にささっとふれておきたいと思います。
「文楽のこころを語る」 竹本住大夫

〈内容紹介〉
山本千恵子さんの「聞き書き」です。住大夫さんがお話されたままを文章に起こしてあるので、大阪弁がそのまま文字になっています。「おまへん」とか「したはります」とか「あきまへん」とか、大阪弁(正しくは河内弁だけれど)nativeの私はすっと入りますが、東京のお人がお読みになったらどうなんでしょうか。
これを読んでいたときは、実際の舞台は「曾根崎心中」を見ただけだったので、どちらかと言うと演目のあらすじをなぞる感じでしたが、今は、と言っても「忠臣蔵」が増えただけですが、もうちょっと身近に感じるようになりました。
ところで、住大夫さんはアノ騒動のせいで、軽い脳梗塞で入院されていましたが、無事退院され、初春公演で復帰されるとのことで、1月公演が楽しみです。
「頭巾かぶって五十年 文楽に生きて」 三代目吉田簑助
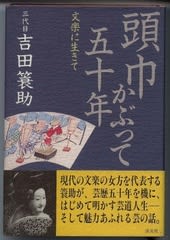
〈内容紹介〉
平成3年に出版された本です。ご病気の前の本です。簑助さん のお父様がやはり文楽の人形遣いでいらっしゃったので、簑助さん
のお父様がやはり文楽の人形遣いでいらっしゃったので、簑助さん も5、6歳の頃から劇場へ通っていらっしゃったそうです。特別に作られた子供用の黒衣を着た簑助さん
も5、6歳の頃から劇場へ通っていらっしゃったそうです。特別に作られた子供用の黒衣を着た簑助さん の写真が掲載されていました。お可愛らしかったです。ドラマチックなことが書かれているわけではなく、淡々と生い立ちや現在のことを書いていらっしゃるだけなんですが、じわじわと感動する本でした。
の写真が掲載されていました。お可愛らしかったです。ドラマチックなことが書かれているわけではなく、淡々と生い立ちや現在のことを書いていらっしゃるだけなんですが、じわじわと感動する本でした。
「花舞台へ帰ってきた 脳卒中・闘病・リハビリ・復帰の記録」 吉田簑助と山川静夫

〈内容紹介〉
簑助さん と山川さんは同い年のお友だちです。山川さんっていうと「歌舞伎」のイメージなんですが、文楽にも精通していらっしゃいます(まあ、歌舞伎の親元のようなものですから)。闘病中のお二人の往復書簡も掲載されていましたが、思いのあふれたお手紙で、本当の親友なんだなぁと思いながら読んでおりました。
と山川さんは同い年のお友だちです。山川さんっていうと「歌舞伎」のイメージなんですが、文楽にも精通していらっしゃいます(まあ、歌舞伎の親元のようなものですから)。闘病中のお二人の往復書簡も掲載されていましたが、思いのあふれたお手紙で、本当の親友なんだなぁと思いながら読んでおりました。
今の簑助さん の舞台を拝見しても、どこにも病気のことを感じさせるところはありません。「舞台に立ちたい」という一心でリハビリに励んだから、とご本人も書いていらっしゃいますが、それでもここまで復帰するというのは強靭な不屈の精神力がないとできないでしょうね。
の舞台を拝見しても、どこにも病気のことを感じさせるところはありません。「舞台に立ちたい」という一心でリハビリに励んだから、とご本人も書いていらっしゃいますが、それでもここまで復帰するというのは強靭な不屈の精神力がないとできないでしょうね。
簑助さん の舞台写真も何点かあって、あの、無愛想にも見える舞台のお顔、萌えます~
の舞台写真も何点かあって、あの、無愛想にも見える舞台のお顔、萌えます~ 。
。
「文楽ざんまい」 亀岡典子

〈内容紹介〉
表紙に簑助さん ご登場です。「吉田屋」の夕霧です。
ご登場です。「吉田屋」の夕霧です。
第1章は「キーワードでたどる文楽」で「足遣い」「衣裳」「太夫と三味線」「床山」「人形拵え」等々文楽の言葉を取り上げ、それについて3ページほどの文章が続きます。新聞記者さんなので、非常にわかりやすくコンパクトに説明してあります。
第2章では太夫・三味線・人形遣いの方たちへのインタビューで、これは一人につき30ページ近く割いてあって、入門から修行、芸談などが語られています。人形遣いでは吉田玉男さんもご登場でした。簑助さん とは名コンビだったそうで、玉男さんが「曾根崎心中」の徳兵衛を1111回勤められたときのセレモニーでは、簑助さん
とは名コンビだったそうで、玉男さんが「曾根崎心中」の徳兵衛を1111回勤められたときのセレモニーでは、簑助さん が「いついつまでも添うてください はつ・簑助」と書いたカードをつけて赤いバラのお花を贈られたそうで、「きゃっ、ステキ
が「いついつまでも添うてください はつ・簑助」と書いたカードをつけて赤いバラのお花を贈られたそうで、「きゃっ、ステキ 」でございます。
」でございます。
この記事を書くために、上の4冊の本をパラパラと見ていたら、実際の文楽を何度か見たからわかる(なんて書くのも厚かましいんですが、スミマセン)という箇所もありそうで、手元に置いて、見るたびにまた見返そうって思っています。とりあえず、日曜までに「忠臣蔵」を中心に…。すっげー、付け焼き刃
「文楽のこころを語る」 竹本住大夫

〈内容紹介〉
当代随一の浄瑠璃語りにして人間国宝である著者が、三大名作から十年に一度の珍しい演目まで19演目について、作品の面白さ、詞の一行一行にこめられた工夫や解釈にいたるまで、芸の真髄を語り尽くした、すべての文楽ファン必携の書。文庫化に際し『菅原伝授手習鑑・寺子屋の段』と、狂言・茂山千之丞氏との対談も収録。
山本千恵子さんの「聞き書き」です。住大夫さんがお話されたままを文章に起こしてあるので、大阪弁がそのまま文字になっています。「おまへん」とか「したはります」とか「あきまへん」とか、大阪弁(正しくは河内弁だけれど)nativeの私はすっと入りますが、東京のお人がお読みになったらどうなんでしょうか。
これを読んでいたときは、実際の舞台は「曾根崎心中」を見ただけだったので、どちらかと言うと演目のあらすじをなぞる感じでしたが、今は、と言っても「忠臣蔵」が増えただけですが、もうちょっと身近に感じるようになりました。
ところで、住大夫さんはアノ騒動のせいで、軽い脳梗塞で入院されていましたが、無事退院され、初春公演で復帰されるとのことで、1月公演が楽しみです。
「頭巾かぶって五十年 文楽に生きて」 三代目吉田簑助
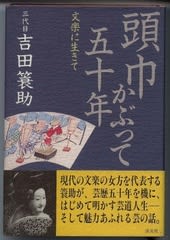
〈内容紹介〉
現代の文楽の女方を代表する簑助が、芸歴50年を機に、はじめて明かす半生記。そして、伝統と現代・人形遣いの知恵・女方の人形の型・文楽に生きる女たちなどをテーマに、簑助本人の体験をまじえて語る芸の話。
平成3年に出版された本です。ご病気の前の本です。簑助さん
 のお父様がやはり文楽の人形遣いでいらっしゃったので、簑助さん
のお父様がやはり文楽の人形遣いでいらっしゃったので、簑助さん も5、6歳の頃から劇場へ通っていらっしゃったそうです。特別に作られた子供用の黒衣を着た簑助さん
も5、6歳の頃から劇場へ通っていらっしゃったそうです。特別に作られた子供用の黒衣を着た簑助さん の写真が掲載されていました。お可愛らしかったです。ドラマチックなことが書かれているわけではなく、淡々と生い立ちや現在のことを書いていらっしゃるだけなんですが、じわじわと感動する本でした。
の写真が掲載されていました。お可愛らしかったです。ドラマチックなことが書かれているわけではなく、淡々と生い立ちや現在のことを書いていらっしゃるだけなんですが、じわじわと感動する本でした。「花舞台へ帰ってきた 脳卒中・闘病・リハビリ・復帰の記録」 吉田簑助と山川静夫

〈内容紹介〉
平成10年文楽人形遣い(人間国宝)吉田簑助発病、平成12年司会者・エッセイストの山川静夫発病。40年来の友が、不幸にも「脳卒中」によって半身のマヒや失語症に見舞われました。汗と涙のリハビリの結果、簑助師匠は舞台復帰をはたし、山川氏はことばを取り戻しました。この間の互いの闘病記録、励まし合いの交信を中心に、「二人の道のり」や生き甲斐を両者の立場から対比的にまとめた書。古希をすぎた二人の友情と、あらためて感ずる “仕事への熱き思い”。同じ病と闘う人や、二人のファンにおくる人生の応援歌です。
簑助さん
 と山川さんは同い年のお友だちです。山川さんっていうと「歌舞伎」のイメージなんですが、文楽にも精通していらっしゃいます(まあ、歌舞伎の親元のようなものですから)。闘病中のお二人の往復書簡も掲載されていましたが、思いのあふれたお手紙で、本当の親友なんだなぁと思いながら読んでおりました。
と山川さんは同い年のお友だちです。山川さんっていうと「歌舞伎」のイメージなんですが、文楽にも精通していらっしゃいます(まあ、歌舞伎の親元のようなものですから)。闘病中のお二人の往復書簡も掲載されていましたが、思いのあふれたお手紙で、本当の親友なんだなぁと思いながら読んでおりました。今の簑助さん
 の舞台を拝見しても、どこにも病気のことを感じさせるところはありません。「舞台に立ちたい」という一心でリハビリに励んだから、とご本人も書いていらっしゃいますが、それでもここまで復帰するというのは強靭な不屈の精神力がないとできないでしょうね。
の舞台を拝見しても、どこにも病気のことを感じさせるところはありません。「舞台に立ちたい」という一心でリハビリに励んだから、とご本人も書いていらっしゃいますが、それでもここまで復帰するというのは強靭な不屈の精神力がないとできないでしょうね。簑助さん
 の舞台写真も何点かあって、あの、無愛想にも見える舞台のお顔、萌えます~
の舞台写真も何点かあって、あの、無愛想にも見える舞台のお顔、萌えます~ 。
。「文楽ざんまい」 亀岡典子

〈内容紹介〉
生身の人間がのたうちまわって築き上げる芸。魂が震えるような感動と美がそこにある。世界無形遺産に指定された文楽の世界をキーワードでわかりやすく紹介する。『産経新聞』連載に加筆して単行本化。
表紙に簑助さん
 ご登場です。「吉田屋」の夕霧です。
ご登場です。「吉田屋」の夕霧です。第1章は「キーワードでたどる文楽」で「足遣い」「衣裳」「太夫と三味線」「床山」「人形拵え」等々文楽の言葉を取り上げ、それについて3ページほどの文章が続きます。新聞記者さんなので、非常にわかりやすくコンパクトに説明してあります。
第2章では太夫・三味線・人形遣いの方たちへのインタビューで、これは一人につき30ページ近く割いてあって、入門から修行、芸談などが語られています。人形遣いでは吉田玉男さんもご登場でした。簑助さん
 とは名コンビだったそうで、玉男さんが「曾根崎心中」の徳兵衛を1111回勤められたときのセレモニーでは、簑助さん
とは名コンビだったそうで、玉男さんが「曾根崎心中」の徳兵衛を1111回勤められたときのセレモニーでは、簑助さん が「いついつまでも添うてください はつ・簑助」と書いたカードをつけて赤いバラのお花を贈られたそうで、「きゃっ、ステキ
が「いついつまでも添うてください はつ・簑助」と書いたカードをつけて赤いバラのお花を贈られたそうで、「きゃっ、ステキ 」でございます。
」でございます。この記事を書くために、上の4冊の本をパラパラと見ていたら、実際の文楽を何度か見たからわかる(なんて書くのも厚かましいんですが、スミマセン)という箇所もありそうで、手元に置いて、見るたびにまた見返そうって思っています。とりあえず、日曜までに「忠臣蔵」を中心に…。すっげー、付け焼き刃











 でございます。
でございます。













