獣脚類を中心とした恐竜イラストサイト
肉食の系譜
エウドロマエオサウリアの系統進化の新しい仮説 (1)
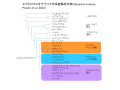
エウドロマエオサウリアとは、ドロマエオサウルス類の中でもウネンラギア類やミクロラプトル類などを除いた、有名なヴェロキラプトルやデイノニクスなどの最も“ラプトルらしい”肉食恐竜のグループである。中には全身骨格が発見されている種もいくつかあるが、多くは部分骨格か断片的であり、アトロキラプトルのように上顎と下顎しかないものもある。上顎骨といくつかの骨しかない種類も多いので、広範なドロマエオサウルス類の系統解析をするためには、上顎骨はかなり重要である。
Powers et al. (2022) は上顎骨に注目した。アケロラプトルの上顎骨は多くのひびが入ってつぶれており、位置関係がゆがんでいる。アトロキラプトルの上顎骨は最初の記載の時には完全にクリーニングされておらず、記載が不完全なところがあった。さらにデイノニクスの上顎骨は他のいくつかの骨とともにつぶれていたため、関節面などの構造がわからない部分があった。そこでPowers et al. (2022)はアケロラプトル、アトロキラプトル、デイノニクスの上顎骨を中心に、多くのドロマエオサウルス類で前上顎骨、鼻骨、歯骨を含めた吻部をCTスキャンし、解析した。例えばアケロラプトルについては3次元的にゆがみを直してデータを取り直した。これにより外側面と内側面の構造の比較や、内部の腔所などの構造、関節面の状態などが新たに解明された。
ドロマエオサウルス類の系統について包括的に解析した研究としてはCurrie and Evans (2019) などがあるが、本来は新しい種類が加わるときには形質の定義などを改訂すべきものである。そこで今回、CTスキャンによって得られた新知見を含めて、分岐分析に用いる上顎骨周辺の形質の表現が適切であるかどうかを注意深く再検討した。そして不適切な表現やスコアを修正して、あらためてドロマエオサウルス類の系統解析を行った。例えばヴェロキラプトルでは上顎骨全体が長いが、前方突起が「長い」ことと「細長い」ことが一緒にされていた。このままだと北米のドロマエオサウルス類はすべて「長くない」で括られてしまう。しかしサウロルニトレステスなどは前方突起が相対的に長いが、前方突起の形自体(長さと高さの比)は細長くないという。
著者らはいくつかの方法で系統解析を行っているが、いずれもエウドロマエオサウリアの中には3つのクレードが形成された。ヴェロキラプトル亜科、ドロマエオサウルス亜科、サウロルニトレステス亜科である。これらのどれが先に分岐したかは場合によって異なっていた。また、デイノニクスの位置は今回も確定せず、ドロマエオサウルス亜科の最も基盤的な位置にくる場合と、サウロルニトレステス亜科の最も基盤的な位置にくる場合があった。
ヴェロキラプトル亜科はベイズ解析の分岐図で12の共有派生形質で支持された。上顎骨に関する共有派生形質としては、広く後方に開いたmaxillary fossa、長い前方突起、細長い前方突起、広い板状のpila interfenestralis、細長い上顎骨などがある。アダサウルスでは吻部の形質はわからないが、方形頬骨や方形骨にリンへラプトルやツァーガンと共通する形質がいくつかある。最尤解析の分岐図でヴェロキラプトル・モンゴリエンシスとヴェロキラプトル sp.はクレードとなったが、ヴェロキラプトル・オスモルスカエはリンへラプトル+ツァーガンとクレードをなした。以前にも指摘されたように、これはヴェロキラプトル属が多系群であることを示唆する。
ドロマエオサウルス亜科にデイノニクスが含まれる場合は確実性は低いが、前上顎骨の外鼻孔の下の丈が高いなど、3つの共有派生形質で支持された。デイノニクスを除いたドロマエオサウルス亜科は、前縁と後縁の鋸歯がほぼ同じ大きさである、閉鎖孔突起が近位にあるなど、4つの共有派生形質で支持された。
最尤解析ではサウロルニトレステス亜科にデイノニクスが含まれたが、その場合は後縁の鋸歯が非対称な形であるなど、4つの共有派生形質で支持された。デイノニクスを除いたサウロルニトレステス亜科は確実性が高く、11の共有派生形質で支持された。サウロルニトレステス亜科の中で、アケロラプトルはアトロキラプトルと姉妹群をなした。このクレードは上顎骨の前眼窩窩が短い、前眼窩窩が歯槽の上限よりも腹側に伸びていない、という2つの共有派生形質で支持された。アケロラプトルは従来の系統解析ではヴェロキラプトル亜科に含まれていたので、この位置づけは新しいものである。
つづく
参考文献
Mark J. Powers, Matteo Fabbri, Michael R. Doschak, Bhart-Anjan S. Bhullar, David C. Evans, Mark A. Norell & Philip J. Currie (2022): A new hypothesis of eudromaeosaurian evolution: CT scans assist in testing and constructing morphological characters, Journal of Vertebrate Paleontology, DOI: 10.1080/02724634.2021.2010087
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
スピノサウルス類の骨密度

スピノサウルスとスコミムスでは骨の組織像が全然違うということは2014年にわかっていたわけだから、今回新しいのはバリオニクスのデータである。スピノサウルス類の中でもほとんど同じ体形のバリオニクスとスコミムスで生態が異なる、というのが面白いところである。
陸生脊椎動物である羊膜類が二次的に水中生活に戻る現象は、独立に30回も起きており、非常によくみられることである。その中で非鳥型恐竜は例外的で、ほとんど陸上生活に限られるとされてきた。その概念を打ち破ったのが、スピノサウルスのネオタイプの発見である。
水中での摂食subaqueous foragingや深い潜水deep divingのような水中生活への適応は、ボディプランの基本的な変更を伴う大きな進化的移行である。にもかかわらず、クジラ類や海生爬虫類のように高度の水生適応を示すグループでさえ、この変形には数百万年かかっている。いくつかの現生種や、最も特殊化した水生動物の系統でも初期の化石種では、比較的わずかな骨格上の変化しか示さない。例えばカバやごく初期のクジラ類などである。よって、現在陸生だったと考えられている恐竜の中にも、実は水生適応の初期段階にあったり、半水生だったりした種類がいるかもしれない。
骨密度の増加は、水中生活への適応として現生の羊膜類に広く生じており、ワニ形類、鳥類、海生爬虫類、クジラ類のような絶滅した四肢動物で水中生活を示唆するのに用いられてきた。骨密度は従来、1つの系統の中で古生態を考察するのに用いられてきたが、骨密度が水生適応の指標として有用であるかどうか評価するためには、もっと系統的に広範な検討が必要である。
そこでFabbri et al.(2022) は、206の現生および174の絶滅した羊膜類について、大腿骨の骨幹と肋骨の近位部の骨密度を定量化した。これらのデータは(1)水中摂食するかどうか(2)飛行するかどうかなどのスコアをつけられた。鳥類では飛行もするし潜水もする種もあれば、飛行できず潜水する種もある。データの中には議論の余地なく水生である現生種と絶滅種、例えば海生哺乳類(クジラ類、鰭脚類)、主竜類以外の海生爬虫類(魚竜類、鰭竜類、モササウルス類)、水生の主竜類(メトリオリンクス類、現生ワニ類)、潜水する鳥類(ペンギン、アビ、カイツブリなど)も含まれている。
最も相関が高かったのは骨密度と水中摂食で、つまり羊膜類全体で“頻繁な水中摂食”は、大腿骨と肋骨の骨密度の増加と相関していた。“頻繁でない水中摂食”や水面上からの摂食は、骨密度の増加と相関していなかった。これは渉禽類(サギ、ペリカン、フラミンゴなど)は陸生の動物と同様の骨密度をもつことと一致する。
ゾウや竜脚類のような巨大な陸上動物では、大腿骨の骨密度が増加する傾向があった。また魚竜類、モササウルス類、クジラ類、アザラシのように深く潜水する動物では、浅く潜水する水中摂食者と比べて低い骨密度を示した。これらの深く潜水する動物では緻密骨が海綿骨に置き換わり、多数の骨梁や血管で占められている。これは水圧への適応や代謝の増加と関連して説明されている。よって高い骨密度は、水生適応の初期段階の良い指標となるが、水面を歩く動物、深く潜水する動物、陸生動物を区別することはできないと考えられた。
著者らの解析の結果、非鳥型恐竜の中でスピノサウルス類だけが、はっきりと水中摂食者と判定された。スピノサウルス類の中でも多様性があり、スピノサウルスとバリオニクスは水中摂食者と予測されたが、スコミムスの骨密度は他の陸生の獣脚類と同様で、水中摂食者でないと判定された。スコミムスの大腿骨はティラノサウルス、ティラノティタン、トルボサウルスなどの大型獣脚類と似ていたが、スピノサウルスとバリオニクスは大きく異なっていた。
オルニトミムス類、ハルシュカラプトル、鳥脚類など他の非鳥型恐竜はすべて、中空の骨髄腔をもち、水中摂食者とは予測されなかった。それに対してバリオニクス(背側肋骨、肩甲骨、恥骨、座骨、大腿骨、腓骨)とスピノサウルスのネオタイプ(背側肋骨、胴椎と尾椎の神経棘、大腿骨、脛骨、腓骨、手の指骨)では多数の骨に高い骨密度が観察され、水中摂食者という予測は確実と思われた。
系統的な比較から、スピノサウルス類の祖先は水中摂食をしていたと考えられ、スコミムスは二次的に高い骨密度を失ったと考えられる。骨密度が高くないからといって、スコミムスが水辺の環境に依存していたことを否定するものではない。長い吻や円錐形の歯などの形態学的特徴は主に魚食性であったことを示している。従来から想定されたように、スコミムスは河岸あるいは浅瀬に立って魚を捕らえるハンターだった可能性が高い。形態学的には同じように見えるバリオニクスとスコミムスで、潜水するものとしないものという大きな生態学的違いがあったことになるが、これはバリオニクス亜科に限ったことではなく、ウ科やカバ上科にもみられるという。これは河川や沼などの水辺がまばらに分布していたなどの環境要因が関係しているかもしれないとある。
つまりバリオニクス「重い爪」は爪だけでなく、体の骨も重かったというオチである。
参考文献
Fabbri, M., Navalón, G., Benson, R.B.J. et al. Subaqueous foraging among carnivorous dinosaurs. Nature 603, 852–857 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04528-0
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
有胎盤哺乳類の脳化の様相:まず体が大きくなり、それから脳が発達した

バリラムブダ(汎歯類)

フェナコドゥス(か節類)

パトリオフェリス(オキシアエナ類、始新世の原始的な肉食獣)
写真は全てwikipedia (en.wikipedia org)
哺乳類は、脊椎動物の中で、最も体の割に大きな脳をもつ動物である。哺乳類の脳の進化については、中生代の間にもいくつかの段階で発達がみられるが、それは現代の哺乳類に比べるとはるかに原始的な脳であった。哺乳類の脳が劇的に発達するのは新生代に入ってからであるという。科学番組などでは恐竜時代に、哺乳類は小型で夜行性の生活をしていたために、聴覚や空間認識など情報処理能が発達したことが紹介されていた。それがそのまま発展したのかというと、そう単純でもないらしい。
白亜紀末に恐竜が絶滅した後、生態系の空白のニッチを埋めるように哺乳類が多種多様に放散した。その後も哺乳類の進化が続いて今日に至るわけだが、その過程で哺乳類の脳がどのように発達したのかについては、詳細が知られていなかったという。
Bertrand et al. (2022) は、中生代から恐竜絶滅後の古第三紀暁新世、始新世にかけて、多数の有胎盤類の脳函をCTスキャンし、脳容量endocranial volume、推定体重、脳化指数PEQ(体の大きさに対する相対的な脳の大きさ)を計算した。最近ニューメキシコ州で発見された、新しい暁新世の哺乳類の脳函も含まれている。その多数のデータを中生代哺乳類、暁新世の哺乳類、始新世の基盤的な哺乳類、始新世の進化的哺乳類に分けてグラフで示している。また脳全体の容量だけでなく、脳の各領域(嗅球など)の容積を算出して各系統で比較した。
従来から、暁新世の哺乳類の脳は中生代哺乳類とあまり変わっておらず、そのまま拡大したバージョンであるという説は提唱されていた。しかしBertrand et al.の結果は少し異なっていた。体のサイズは、中生代に比べて、古第三紀ではみな非常に大きくなっているが、相対的な脳の大きさは、暁新世では中生代よりもむしろ低下しており、始新世になると増加している。そして始新世の中では、原始的な系統に比べて、進化的な系統では明らかに相対的な脳の大きさが増加していた。
脳の各領域についてみると、始新世の進化的な系統では、暁新世や始新世の原始的な系統に比べて変化していた。相対的に嗅球が小さくなり、錐体小葉petrosal lobuleや新皮質が大きくなっていた。錐体小葉は平衡覚、視覚、眼球運動、頸の動きなどに関与する部位である。また新皮質は情報の統合にあずかる。つまり暁新世までは嗅覚に依存した原始的な脳であったが、始新世の一部の系統でその他の感覚や情報処理が大きく発達したということになる。
暁新世における相対的な脳サイズの低下には、“か節類”(ex.フェナコドゥス)、汎歯類(バリラムブダ)、紐歯類(スティリノドン)などの原始的な系統で体のサイズが増大したことが関与している。一方始新世になると、特に進化的な系統で相対的な脳サイズが増加した。例えば偶蹄類(クジラ類を含む)、奇蹄類、食肉類、真霊長類などである。また暁新世では、雑食及び肉食の種類と草食の種類で相対的な脳サイズに有意の差がなかったが、始新世になると雑食及び肉食は、草食を凌駕するようになった。
恐竜絶滅後の哺乳類の放散においては、脳のサイズよりも体のサイズの増加が特徴的であるともいえる。体が大きくなるにつれて脳も大きくなるが、構造的には変化がなかった。独立して体が大きくなったことで、相対的な脳サイズには変異が大きくなった。暁新世の哺乳類にとっては、相対的に大きな脳は必要でなかったかもしれないという。
始新世になると、空いていたニッチが飽和し、種間の競合が起きるようになった。相対的な脳サイズが大きく、また感覚や情報処理、社会行動などの能力がより優れた種類が有利なように自然選択が働くようになったという趣旨である。
感想であるが、確かにバリラムブダのような暁新世の草食哺乳類をみると、頭が小さく、とりあえず体を大きくしたようなバランスが感じられる。正確には植物食の単弓類に近い体形なのか。このままさらに大型化して恐竜的な存在になってくれてもよかったのだが、そこまで生物資源が豊かではなかったか、時間がなかったのだろう。始新世には脳が発達した新しいグループが出現して、競合にさらされ、後に取って代わられることになった。
肉食獣の方は外見ではわからないが、脳のサイズに差があるのだろう。ヒエノドン類と食肉類ではPEQに差があることがグラフに出ている。ただし、ヒエノドン類でも一部の種類は食肉類と遜色ないくらいの脳サイズだったようだ。
そうすると現代型の哺乳類の脳が発達したのは、恐竜におびえて夜の世界に暮らしていたからというよりも、始新世に哺乳類同士の競争が激しくなったからということになる。ジュラ紀や白亜紀の恐竜の間でも熾烈な競合はあっただろうが、脳サイズが増大する方向に進化したようにはあまり見えない。
真獣類全体の脳の初期進化を扱ったすごい研究だと思ったら、獣脚類の研究者でもあるエジンバラ大学のBrusatte博士のラボだった。ただアフリカ獣類や異節類のデータがほとんどないのは、暁新世や始新世の化石が乏しいのだろう。
参考文献
Bertrand et al. (2022) Brawn before brains in placental mammals after the end-Cretaceous extinction. Science 376, 80–85, 1 April 2022
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )




