*****喜三二と春町2*****
蔦重が二十歳代前半で書物の商いを始めた1770年中期以降は、老中・田沼意次の金権政治で享楽的な時代で、浄瑠璃・歌舞伎・狂歌・錦絵・黄表紙・洒落本・滑稽本などが江戸庶民に広く親しまれていきました。1782年(天明2年)蔦重は狂歌集刊行に進出します。蔦重周辺の人物には必ず狂歌号がついてますが、当時上手い下手にかかわらず、お友達グループは狂歌という遊びをしていたようです。現代の子供が集まってカードゲームをするようなものだったんでしょうか。子供は友達の家や公園に集まりますが、蔦重たち大人が集まる場所は吉原遊郭でした。
蔦重が吉原出身であり狂歌仲間に遊女屋の主人などがいたこともあり、勝手がよかったのでしょう。この年の暮れ、四方赤良(よものあから:大田南畝おおたなんぼ)、朱楽菅江(あっけらかんこう:幕臣山崎景貫)、元木網(もとのもくあみ:京橋の湯屋大野屋喜三郎)、唐来参和(とうらいさんな:志水燕十?)、酒上不埒(さけのうえのふらち:恋川春町)、絵師の北尾重政、北尾政演(まさのぶ:山東京伝の画号)、北尾政美(後の鍬形慧斎くわがたけいさい)らが蔦唐丸(つたのからまる:蔦重の狂名)と共に加保茶元成(かぼちゃのもとなり:大文字屋市兵衛の狂名)の遊女屋で遊んでいます。この頃、狂歌のグループが沢山できて(蔦重は吉原連)吉原はそういった人達の交流サロンになり繁栄しました。
その一方で、天明期は大飢饉が何年も続き、各地で打ちこわしが起こっていました。1786年(天明6年)田沼意次が失脚し、翌年老中若年寄など役人が一新し、松平定信が老中首座になり改革に乗り出しました。その政策の一つとして、文武が奨励されるようになりました。
政界の急変に深い関心を示すようになった市民の姿を見て、蔦重は政治諷刺を草双紙に取り入れるアイディアを思いつき、1788年(天明8年)朋誠堂喜三二作、歌麿画『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくどおし)』を出版しました。

序文には「富士の裾野の蔦十が需(もとめ)に応じて作ス(蔦屋重三郎の求めに応じて作った」とある
 『文武二道万石通』
『文武二道万石通』
『文武二道万石通』では、鎌倉時代とし、頼朝の命をうけて畠山重忠(松平定信役)が大小名を文・武・のらくらの三つに分けて、のらくら武士(田沼一派)の財産を大磯の廓でふるい落とさせ、文と武の二道に導くという辛口ストーリーで、田沼一派の失脚から松平定信の登場、寛政の改革の断行とそれに伴う武士達の狼狽ぶりを穿ってみせました。設定が鎌倉時代であっても絵を見れば誰であるか判別できたので、大評判となり飛ぶように売れたそうです。ただあまりに際どかったらしく、蔦重は早々に彫りを改めて再板本を出しています。
これに呼応して、翌1789年(天明9年:寛政元年)恋川春町が北尾政美(山東京伝と同じ絵師の弟子)の画で『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』を執筆して刊行。
 『鸚鵡返文武二道』
『鸚鵡返文武二道』
馬術といえば女装した陰間(かげま:男娼のこと。吉原には多くの男芸者もいた)を相手にお馬の稽古で、笑う茶屋のおかみの傍らで三味線を弾いているのも陰間、公卿は小柄な陰間をリクエストしている。
タイトルは、『文武二道』の鸚鵡返しの意味と、当時読まれていた松平定信の教諭書『鸚鵡言』を掛けたもので、寛政改革治下に動揺する人心を穿ち茶化した内容です。
この本によって春町は定信に召喚されますが、病気を理由に行きませんでした。それから間もなく彼は亡くなります。春町の死の真相は不明で、自殺説もあるそうです。
彼は駿河小島藩の江戸詰家臣でしたが、小藩の武士なので貧しく、生活の足しに画工になろうと鳥山石燕に学んだといいます。森島中良と同じく、彼も封建社会に大きく左右された人物だったのです。
蔦重が二十歳代前半で書物の商いを始めた1770年中期以降は、老中・田沼意次の金権政治で享楽的な時代で、浄瑠璃・歌舞伎・狂歌・錦絵・黄表紙・洒落本・滑稽本などが江戸庶民に広く親しまれていきました。1782年(天明2年)蔦重は狂歌集刊行に進出します。蔦重周辺の人物には必ず狂歌号がついてますが、当時上手い下手にかかわらず、お友達グループは狂歌という遊びをしていたようです。現代の子供が集まってカードゲームをするようなものだったんでしょうか。子供は友達の家や公園に集まりますが、蔦重たち大人が集まる場所は吉原遊郭でした。
蔦重が吉原出身であり狂歌仲間に遊女屋の主人などがいたこともあり、勝手がよかったのでしょう。この年の暮れ、四方赤良(よものあから:大田南畝おおたなんぼ)、朱楽菅江(あっけらかんこう:幕臣山崎景貫)、元木網(もとのもくあみ:京橋の湯屋大野屋喜三郎)、唐来参和(とうらいさんな:志水燕十?)、酒上不埒(さけのうえのふらち:恋川春町)、絵師の北尾重政、北尾政演(まさのぶ:山東京伝の画号)、北尾政美(後の鍬形慧斎くわがたけいさい)らが蔦唐丸(つたのからまる:蔦重の狂名)と共に加保茶元成(かぼちゃのもとなり:大文字屋市兵衛の狂名)の遊女屋で遊んでいます。この頃、狂歌のグループが沢山できて(蔦重は吉原連)吉原はそういった人達の交流サロンになり繁栄しました。
その一方で、天明期は大飢饉が何年も続き、各地で打ちこわしが起こっていました。1786年(天明6年)田沼意次が失脚し、翌年老中若年寄など役人が一新し、松平定信が老中首座になり改革に乗り出しました。その政策の一つとして、文武が奨励されるようになりました。
政界の急変に深い関心を示すようになった市民の姿を見て、蔦重は政治諷刺を草双紙に取り入れるアイディアを思いつき、1788年(天明8年)朋誠堂喜三二作、歌麿画『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくどおし)』を出版しました。

序文には「富士の裾野の蔦十が需(もとめ)に応じて作ス(蔦屋重三郎の求めに応じて作った」とある
 『文武二道万石通』
『文武二道万石通』『文武二道万石通』では、鎌倉時代とし、頼朝の命をうけて畠山重忠(松平定信役)が大小名を文・武・のらくらの三つに分けて、のらくら武士(田沼一派)の財産を大磯の廓でふるい落とさせ、文と武の二道に導くという辛口ストーリーで、田沼一派の失脚から松平定信の登場、寛政の改革の断行とそれに伴う武士達の狼狽ぶりを穿ってみせました。設定が鎌倉時代であっても絵を見れば誰であるか判別できたので、大評判となり飛ぶように売れたそうです。ただあまりに際どかったらしく、蔦重は早々に彫りを改めて再板本を出しています。
これに呼応して、翌1789年(天明9年:寛政元年)恋川春町が北尾政美(山東京伝と同じ絵師の弟子)の画で『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』を執筆して刊行。
 『鸚鵡返文武二道』
『鸚鵡返文武二道』馬術といえば女装した陰間(かげま:男娼のこと。吉原には多くの男芸者もいた)を相手にお馬の稽古で、笑う茶屋のおかみの傍らで三味線を弾いているのも陰間、公卿は小柄な陰間をリクエストしている。
タイトルは、『文武二道』の鸚鵡返しの意味と、当時読まれていた松平定信の教諭書『鸚鵡言』を掛けたもので、寛政改革治下に動揺する人心を穿ち茶化した内容です。
この本によって春町は定信に召喚されますが、病気を理由に行きませんでした。それから間もなく彼は亡くなります。春町の死の真相は不明で、自殺説もあるそうです。
彼は駿河小島藩の江戸詰家臣でしたが、小藩の武士なので貧しく、生活の足しに画工になろうと鳥山石燕に学んだといいます。森島中良と同じく、彼も封建社会に大きく左右された人物だったのです。














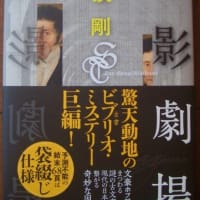

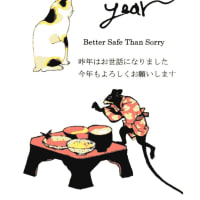
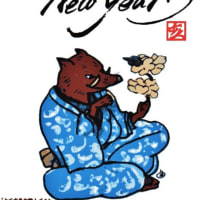
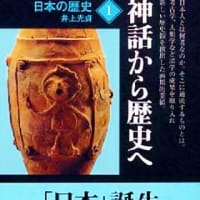


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます