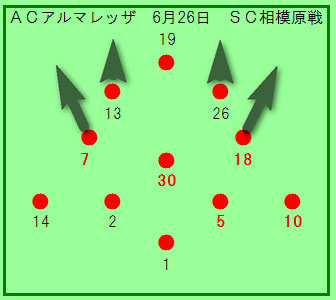最近ビジネスやスポーツで、よくつかわれるようになった言葉「アジリティ~Agility」。「俊敏さ、機敏、敏捷性」というのが基本の意味です。サッカーで使われるアジリティという言葉は、瞬発力・反応及び、細かな方向変化を含む素早い動きをこなす選手の能力の意味でつかわれています。スピードを上げたり、下げたり、あらゆる方向に早く鋭く体を俊敏に動かす能力が高いほど、当然、サッカー選手として能力の高い選手と言えます。試合前のウォーミングアップの時には、SC相模原の選手も、アジリティトレーニングをこなして、体の中の俊敏性・反射神経をどんどん目覚めさせ高めていきます。

ビジネスの中で使われる「アジリティ」という言葉は、変化の激しいこの時代、さまざまなビジネス・ニーズに俊敏に応える企業の能力の事を指します。ビジネス環境が時々刻々と変わる中で、市場の動きや顧客の嗜好を的確につかむための分析を行い、柔軟に経営戦略・企業活動を変えていかなくてはなりません。また日本企業のビジネスは、どんどん新興国シフトが進んでおり、その国々での多様な変化に対して「アジリティ」を発揮することが求められています。

9月11日(日)のSC相模原の試合を見て感じたのは、チームとしての「アジリティ」が十分に発揮できていない事です。試合の流れ、攻撃の手ごたえ、守備の状況、時間帯、スコア、メンバー交代、負傷者・・。サッカーも局面局面でどんどん変化していきます。その変化に対してチームで、サッカーを少しづつ修正していかなくてはなりません。後半40分、1点のビハインド、吉岡が入った。齋藤に代わって松本が入った。こうした状況下で得点を狙う一番高い確率の高いチームプレーは何か。チームとしてビハインドした時の意識・戦術の統一が欠けているように見受けられました。声を掛け合う場面も少なくなりました。だから選手はいらだち始め精神面から崩れていきます。冷静さを失えばますます相手の思う壺です。

幸い、エリースFC東京の敗戦で優勝争いの形成は変わっていません。しかし次は難敵・横浜猛蹴。現在2連敗中で勝てていません。相手は、SC相模原のサッカーを知りつくしています。横浜猛蹴は、SC相模原に勝てば2位浮上の可能性があります。この状況の変化の中でチームとして如何に「アジリティ」を発揮していくか、が勝敗の分かれ目になることは間違いありません。
↓ブログ応援のために下のボタンをクリックしていただけると嬉しいです!↓
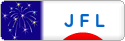

サッカーブログ JFL
↑携帯電話からはこちらをクリック。ありがとうございます。励みになります。↑

ビジネスの中で使われる「アジリティ」という言葉は、変化の激しいこの時代、さまざまなビジネス・ニーズに俊敏に応える企業の能力の事を指します。ビジネス環境が時々刻々と変わる中で、市場の動きや顧客の嗜好を的確につかむための分析を行い、柔軟に経営戦略・企業活動を変えていかなくてはなりません。また日本企業のビジネスは、どんどん新興国シフトが進んでおり、その国々での多様な変化に対して「アジリティ」を発揮することが求められています。

9月11日(日)のSC相模原の試合を見て感じたのは、チームとしての「アジリティ」が十分に発揮できていない事です。試合の流れ、攻撃の手ごたえ、守備の状況、時間帯、スコア、メンバー交代、負傷者・・。サッカーも局面局面でどんどん変化していきます。その変化に対してチームで、サッカーを少しづつ修正していかなくてはなりません。後半40分、1点のビハインド、吉岡が入った。齋藤に代わって松本が入った。こうした状況下で得点を狙う一番高い確率の高いチームプレーは何か。チームとしてビハインドした時の意識・戦術の統一が欠けているように見受けられました。声を掛け合う場面も少なくなりました。だから選手はいらだち始め精神面から崩れていきます。冷静さを失えばますます相手の思う壺です。

幸い、エリースFC東京の敗戦で優勝争いの形成は変わっていません。しかし次は難敵・横浜猛蹴。現在2連敗中で勝てていません。相手は、SC相模原のサッカーを知りつくしています。横浜猛蹴は、SC相模原に勝てば2位浮上の可能性があります。この状況の変化の中でチームとして如何に「アジリティ」を発揮していくか、が勝敗の分かれ目になることは間違いありません。
↓ブログ応援のために下のボタンをクリックしていただけると嬉しいです!↓
サッカーブログ JFL
↑携帯電話からはこちらをクリック。ありがとうございます。励みになります。↑