
加藤直樹さんより「地の塩、海の根」評が寄せられました。
※ ※ ※ ※ ※
燐光群「地の塩、海の根」を見てきた。素晴らしかった。
100年前のウクライナ西部を舞台にユダヤ系ポーランド人が執筆した反戦的、国家批判的な小説「地の塩」。その朗読劇をやろうとしている現代日本の劇団。ポーランド語で書かれたその小説をウクライナ語に翻訳しようとするウクライナ(ヘルソン)の作家。そしてその息子でロシアに拉致され、ロシア化を強要される少年。こうした重層的な物語が、最後に「海の根」という言葉に集約されていく。
ぼくは不覚にも何度か涙が出そうになった。アフタートークで出演しなければいけなかったので何とかこらえた。心を揺さぶられた。
100年前の小説「地の塩」の舞台は、第一次世界大戦下。今のウクライナ西端、カルパチア山中の少数民族「フツル人」であり、飼い犬の他には誰にも心を許していない貧しい孤独な男が、当時この一帯を支配していたオーストリア帝国の臣民として招集され、わけも分からないまま兵士にされていくというものだ。ここには、前近代の人々が戦争を通じて「国民」「民族」へと暴力的に形成されていくさまが描かれている。
一方、100年後。ウクライナの作家の夫とホロドモール研究者の夫婦とその息子は、「ウクライナ人」として確立しつつあるナショナル・アイデンティティをはぎ取ろうとするロシアの侵略という暴力に向き合っている。作家が抱いているナショナリズムは、抵抗民族主義としてのそれである。
「国民」「民族」が上から暴力的に押し付けられていく100年前と、「国民」「民族」を暴力によってはぎ取られようとしている100年後の、同じウクライナの人びと。この合わせ鏡が、この物語に重層性と深みを与え、謎を投げかけてくる。
「国民」「民族」といったフィクションが「人間」にとって何であったかを描きながら、一方で、たった今、それを暴力的に否定されるウクライナの人々の痛みへの共感をはっきりと前提に置いている(だから劇中ではロシア擁護論批判も展開される)。その上で物語は、少年が「その先」を目指すことを暗示して終わるのである。
「海の根」は当初、クリミアを指している。ロシアという内陸の帝国が海に延ばす支配の根。だが、最後にはまったく違う何かとして示される。100年前に「兵士となれ」と言われて動員されていった孤独な男と、「ロシア人になれ」という暴力に抵抗する少年。その二人の無念を受け止めて、しかしその先を指さす何か。つまり、「海に開かれた根」という不思議で力強いイメージへと転身している。歴史的現実の中で人間性を守っていくための根となる、海に開かれた「根」に。
7月7日までやっているので、ぜひ多くの人に観てほしいと思う。
※ ※ ※ ※ ※
加藤直樹さんからのメッセージが寄せられました。Facebookにだが、Facebookをやっていらっしゃらない方のために、こちらにも転載させていただきました。
撮影・姫田蘭。
左より 南谷朝子 武山尚史 円城寺あや 猪熊恒和
上演情報 ↓
https://rinkogun.com/portfolio/20240621_chi_no_shio/














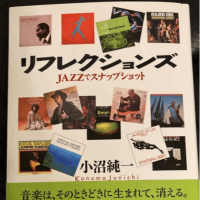











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます