
岡町高弥さんから、「地の塩、海の根」評が寄せられました。
※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※
6月24日、燐光群「地の塩、海の根」(作・演出、坂手洋二)を見るため、ザ・スズナリへ。
燐光群は、11年前、ウクライナ・ヤルタ〈チェーホフ・フェスティバル〉で、「屋根裏」を上演したことがあった。
チェーホフ最後の家は博物館になっていて、「三人姉妹」や「桜の園」もそこで書かれたという。
しかし、今やヤルタは日本から限りなく遠い。もう二度と行けないかもしれない。芝居が出来たのどかな場所は、戦場になってしまった。
なぜ、侵略戦争は終わらないのか。
今回の芝居は、そんな坂手洋二の強い怒りと哀しみから生まれた。
舞台は、とある有名な国立大学の講堂から、ウクライナ、ロシア、クリミアと移っていく。時間も空間もどんどん飛び越えて
彼の地の歴史や民族問題、今に至るロシアとウクライナの関係がたっぷり詰まった濃厚な2時間半だった。
坂手洋二は、一昨年、瀬々敬久監督に呼ばれて京都大学西部講堂にて、ウクライナの反戦小説のリーディングを行なった。
1935年にユダヤ系ボーランド作家ユゼフ・ヴィトリンが発表した未完の反戦小説「地の塩」。
物語は、燐光群の十八番、ドキュメンタリーフィクションといっていい。
ウクライナが舞台でありながら、ロシア語の翻訳はあるもののウクライナ語の翻訳はなかった。
オオミヤ(猪熊恒和)は、再びこのリーディングを行うために役者を集める。
そのリーディング作業とポーランド語で書かれたその小説をウクライナ語に翻訳しようとするウクライナの作家家族(土屋良太、樋尾麻衣子、瓜生田凌矢)の物語が交錯する。
ロシア語を拒否し、ウクライナ語に未来を託す家族は、今のウクライナの状況と重なっていく。
さらに、小説の世界も繋がっていく。主人公で鉄道員のピョートル(猪熊)は、オーストリア帝国の兵士としてロシアとの戦争に徴兵される。他民族軍隊のカオスが、戦争を難しくしていた。ウクライナとロシアは、昔から戦っていたのだ。
小説は、ピョートルが戦場に行く前に中断している。
ウクライナの翻訳家の息子がロシア軍に拉致されてロシアの正義、プーチンの説く平和を教えられる。
息子の父親は「地の塩」のウクライナ語翻訳と続編としてクリミアを舞台にした平和を祈願した「海の根」という小説も準備していた。
ウクライナ侵略にまつわるフェイクニュースの数々を織り交ぜるが、答えは明確だ。
なぜ侵略戦争について、賛否を問うのか、演劇祭もできて穏やかだった場所を戦場にしたのは誰かという「反侵略」への想いが、芝居を突き動かしていた。
今の時代に芝居を作るということは何か、観客とともに考え続ける。答えは出ないが希望を失わないラストに勇気づけられた。
南谷朝子のウクライナ地方の民謡を取り入れたギター、森尾舞の力強い芝居は胸をうつ。
7月7日まで
※ ※ ※ ※ ※
岡町高弥さんのFacebookでの評ですが、Facebookをやっていらっしゃらない方のために、こちらにも転載させていただきました。
撮影・姫田蘭。
左より 川中健次郎 徳永達哉 猪熊恒和 大対源 坂下可甫子 土屋良太 武山尚史 瓜生田凌矢
上演情報 ↓
https://rinkogun.com/portfolio/20240621_chi_no_shio/














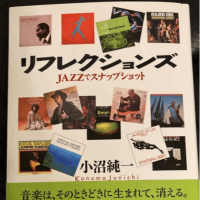











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます