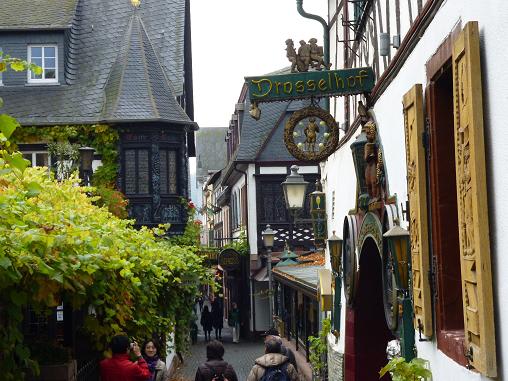京都はまだ名残の紅葉が美しく、モミジの名所はどこも混雑、名刹・名庭は避けて、府立植物園に。

府立植物園は桜もモミジも穴場的おススメスポット。今回の
目的は「フウ」の木。

切符売り場のおじさんに「いい時に来ましたね、あと2~3日ですよ」と言われました。
高い高い梢の葉は少し枯れかかっていましたから、まさににラストシャイニングです。

樹齢100年、樹高26m、大きく枝を広へて錦の衣装を見せてくれているようです。

実がいっぱい。

枝先まで美しく染まって。

よく街路樹でみかけるモミジバフウとは親戚です。原産地では60mもの大木があるそうです。

日本庭園のあたりのモミジもまだまだいい色。池に映る姿も鮮やか。

赤、また赤、枝々を忙しく飛び回っている小さな野鳥の集団を沢山のカメラが狙っていました。
(私も一応狙ってみたけど、これもマイデジカメでは無理!)
たった一日の京もみじだったけれど堪能しました。

府立植物園は桜もモミジも穴場的おススメスポット。今回の
目的は「フウ」の木。

切符売り場のおじさんに「いい時に来ましたね、あと2~3日ですよ」と言われました。
高い高い梢の葉は少し枯れかかっていましたから、まさににラストシャイニングです。

樹齢100年、樹高26m、大きく枝を広へて錦の衣装を見せてくれているようです。

実がいっぱい。

枝先まで美しく染まって。

よく街路樹でみかけるモミジバフウとは親戚です。原産地では60mもの大木があるそうです。

日本庭園のあたりのモミジもまだまだいい色。池に映る姿も鮮やか。

赤、また赤、枝々を忙しく飛び回っている小さな野鳥の集団を沢山のカメラが狙っていました。
(私も一応狙ってみたけど、これもマイデジカメでは無理!)
たった一日の京もみじだったけれど堪能しました。


















 )
) 300km弱ありますから。
300km弱ありますから。