2020年9月27日(日)
今日は「水辺の生き物調査」のボランティア。
採集した魚たちの同定(判別)の係。
一昨年は、西日本豪雨で中止となり・・・他のグループにもぐりこみ👇
水の生き物観察会と西日本豪雨の爪痕
去年は、のほほんと出かけたら、いきなり檀上へ👇
『水辺の生き物調査』ボランティア悲喜こもごも
なので、今年は裏方を強く強く嘆願して、お代官様に許してもろたからね~。
はよ帰れるし、むっちゃラッキーなこともあったし・・・
その話は、またいずれ書くとして・・・
さて、9月23日のこと、「やまごん」探索隊隊長の私は、即座に決断した!
「やまごんが類人猿や猿人であるならば、昼間の行動は避けるのではないか?」
「ねぐらにしてる場所があるのではないか?」
「ならば、近くの岩屋権現があやしい・・・」
さっそく車で5分、その後の急坂徒歩10分の岩屋権現へ向かった。
着いた!(はしょるぞ~)
権現さんの看板
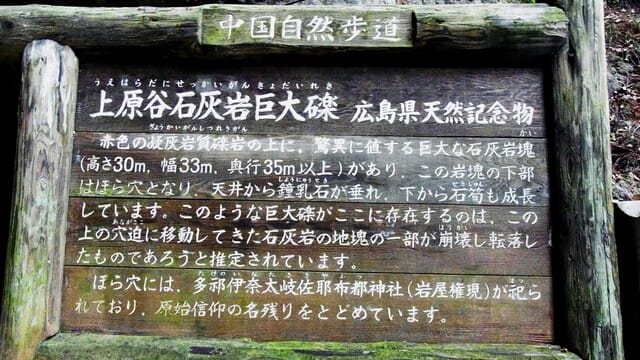
要は、凝灰れき岩の上に巨大石灰岩があって、下部がもろいから穴が開き、鍾乳石もできちゃったってことだな?
と、隊員のかみさん、穴の奥へ奥へと探索に向かうではないか!
何と勇気のあるお方だ。
隊長の命令の間もあたえず、自己責任で「やまごん」に立ち向かうつもりだ。(まさかですケド、本気読んだらあきませんで!)

あわてて後を追う。
フローストーン(流華石)だ。

洞窟の壁に沿って流下し壁を覆うように沈着した石灰石だ。
小さな鍾乳石もぶらさがってる。

一般に、常に流下してる場合100年で1cmというから、雨の少ないこの地域では数百年はたっているなあ。
「やまごん」はいなかった。(当たり前じゃケド)
ただ、奥の奥までもぐりこんでいるのかもしれない。
他の地域へと移動したのかもしれない。
探索を断念し、帰路につく。
登ってきた道は急坂だと、反対の緩やかな道を選ぶ。
サカハチチョウ夏型だあ~っ!

いやあ、この道、大正解!

でもね、喜びもつかの間、車まで遠くて遠くて・・・
途中何度も下ったり登ったり・・・
サカハチチョウに出会ったから坂八町(さかはっちょう)なのに、坂八十町の倍は優に越えてたぞ!(オッサンこのシャレが言いたくて)
(1町≒109m)
さてさて、「やまごん」のこと、帰宅後調べてみた。
1970年、旧比婆郡西城町で目撃され、地方新聞ざたになり
以後、次々と目撃者が現れ、写真まで撮られ、全国紙にものり
まんじゅうその他さまざまなお土産も売られるようになったのが「ヒバゴン」
その後、1980年、福山市山野町に現れたのが「やまごん」

わずか2年後の1982年、三原市久井町に現れたのが「くいごん」
これらは、同一の未確認動物だというもっともらしい話もあるにはあるが・・・
ま、これらの話はね・・・
タンスに現れたら・・・「タンスにゴン」か?
権太坂に現れたら・・・「ゴンゴン」か?
町おこしにうまくつながったのは、西城町などの比婆連峰周辺の町々かな?
お、府中市上下町 のツチノコ発見「賞金300万円」もすてがたいな?
かくして、「やまごん」探索隊は隊長の心の中だけで結成され、静かに解散したのであった。
追記:かみさんが会でほめられた俳句を掲載許可の下
やまごんの出没の碑や木の実降る
今日は「水辺の生き物調査」のボランティア。
採集した魚たちの同定(判別)の係。
一昨年は、西日本豪雨で中止となり・・・他のグループにもぐりこみ👇
水の生き物観察会と西日本豪雨の爪痕
去年は、のほほんと出かけたら、いきなり檀上へ👇
『水辺の生き物調査』ボランティア悲喜こもごも
なので、今年は裏方を強く強く嘆願して、お代官様に許してもろたからね~。
はよ帰れるし、むっちゃラッキーなこともあったし・・・
その話は、またいずれ書くとして・・・
さて、9月23日のこと、「やまごん」探索隊隊長の私は、即座に決断した!
「やまごんが類人猿や猿人であるならば、昼間の行動は避けるのではないか?」
「ねぐらにしてる場所があるのではないか?」
「ならば、近くの岩屋権現があやしい・・・」
さっそく車で5分、その後の急坂徒歩10分の岩屋権現へ向かった。
着いた!(はしょるぞ~)
権現さんの看板
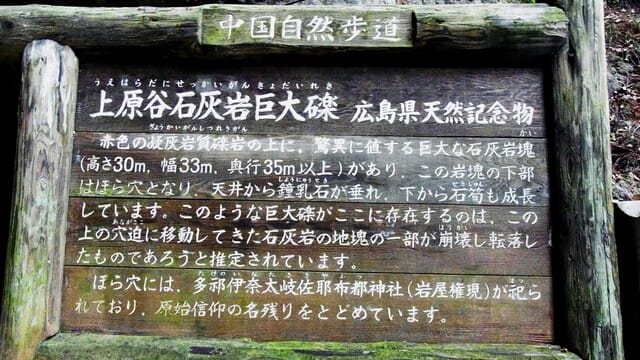
要は、凝灰れき岩の上に巨大石灰岩があって、下部がもろいから穴が開き、鍾乳石もできちゃったってことだな?
と、隊員のかみさん、穴の奥へ奥へと探索に向かうではないか!
何と勇気のあるお方だ。
隊長の命令の間もあたえず、自己責任で「やまごん」に立ち向かうつもりだ。(まさかですケド、本気読んだらあきませんで!)

あわてて後を追う。
フローストーン(流華石)だ。

洞窟の壁に沿って流下し壁を覆うように沈着した石灰石だ。
小さな鍾乳石もぶらさがってる。

一般に、常に流下してる場合100年で1cmというから、雨の少ないこの地域では数百年はたっているなあ。
「やまごん」はいなかった。(当たり前じゃケド)
ただ、奥の奥までもぐりこんでいるのかもしれない。
他の地域へと移動したのかもしれない。
探索を断念し、帰路につく。
登ってきた道は急坂だと、反対の緩やかな道を選ぶ。
サカハチチョウ夏型だあ~っ!

いやあ、この道、大正解!

でもね、喜びもつかの間、車まで遠くて遠くて・・・
途中何度も下ったり登ったり・・・
サカハチチョウに出会ったから坂八町(さかはっちょう)なのに、坂八十町の倍は優に越えてたぞ!(オッサンこのシャレが言いたくて)
(1町≒109m)
さてさて、「やまごん」のこと、帰宅後調べてみた。
1970年、旧比婆郡西城町で目撃され、地方新聞ざたになり
以後、次々と目撃者が現れ、写真まで撮られ、全国紙にものり
まんじゅうその他さまざまなお土産も売られるようになったのが「ヒバゴン」
その後、1980年、福山市山野町に現れたのが「やまごん」

わずか2年後の1982年、三原市久井町に現れたのが「くいごん」
これらは、同一の未確認動物だというもっともらしい話もあるにはあるが・・・
ま、これらの話はね・・・
タンスに現れたら・・・「タンスにゴン」か?
権太坂に現れたら・・・「ゴンゴン」か?
町おこしにうまくつながったのは、西城町などの比婆連峰周辺の町々かな?
お、府中市上下町 のツチノコ発見「賞金300万円」もすてがたいな?
かくして、「やまごん」探索隊は隊長の心の中だけで結成され、静かに解散したのであった。
追記:かみさんが会でほめられた俳句を掲載許可の下
やまごんの出没の碑や木の実降る










































