2020年12月26日(土)
2020年もあと6日
今年タナゴ竿・仕掛けで初めて釣った生き物たちをまとめてみたら・・・
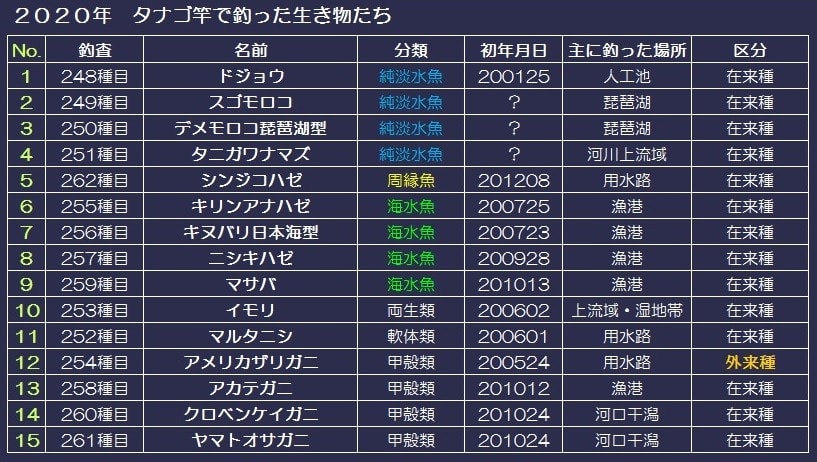
な、なんとわずか15種類。
初物に出会う機会は徐々に減ってくとはいえ、昨年で29種類👇
2019年 初めて釣った生き物たち
半減なのである。
しかも、そのうち東海支部長の日付のない記録3種を含めてだから、しょぼいのなんの。
釣りそのものが遊びだからと、外出自粛を守ってたせいもあるかなあ・・・
遠出とか、最近は毎年のように出かけてた「アジア極貧旅行」もできなかったしなあ・・・
人との接触も極力ひかえてきたしなあ・・・
今年を漢字一字で表すと『疎』
スッカスカやんね。
ま、いい。
そのぶん、虫たちや野草なんぞ、身近な生き物たちに、散策ついでに出会えたしね。
虫や鳥好きのブログ先輩たちともお近づきになれたしね。
物は考えようだ。
2020年もあと6日
今年タナゴ竿・仕掛けで初めて釣った生き物たちをまとめてみたら・・・
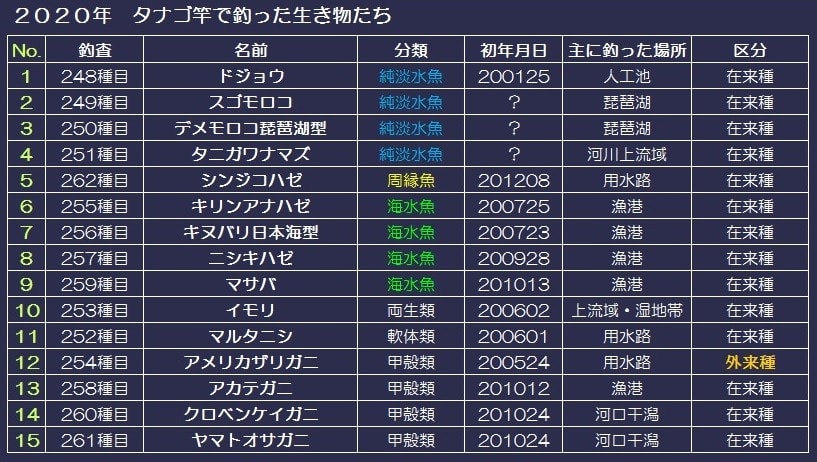
な、なんとわずか15種類。
初物に出会う機会は徐々に減ってくとはいえ、昨年で29種類👇
2019年 初めて釣った生き物たち
半減なのである。
しかも、そのうち東海支部長の日付のない記録3種を含めてだから、しょぼいのなんの。
釣りそのものが遊びだからと、外出自粛を守ってたせいもあるかなあ・・・
遠出とか、最近は毎年のように出かけてた「アジア極貧旅行」もできなかったしなあ・・・
人との接触も極力ひかえてきたしなあ・・・
今年を漢字一字で表すと『疎』
スッカスカやんね。
ま、いい。
そのぶん、虫たちや野草なんぞ、身近な生き物たちに、散策ついでに出会えたしね。
虫や鳥好きのブログ先輩たちともお近づきになれたしね。
物は考えようだ。





































