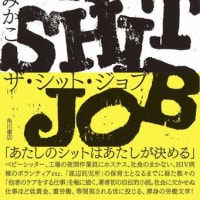佐々木千賀子『立花隆秘書日記』(ポプラ社、2003年)
 1993年5月から1998年末までのあいだ立花隆の秘書を経験した著者がその体験を時系列におもな出来事を中心にして回想風に書き綴ったもので、たいへん面白かった。もちろんこれほど高名な著述家の秘書ということもそうだし、その働きぶりのすごさということでもそうだった。なによりもこの人の文章の上手さには感心した。とくに「1冬の海辺で」だけは特別に詩情豊かな文体で書かれており、この部分をもっと引き伸ばすなり、小説の一部にするなりして、なにかフィクションものとかを書けば、きっとすばらしいものが書けるのではないかと思うほど素晴らしい。ここだけがそれ以外のどちらかと言うとルポルタージュ風の書き方から浮いている。まるで散文詩とでも言ってもいいくらいの詩情を湛えている。
1993年5月から1998年末までのあいだ立花隆の秘書を経験した著者がその体験を時系列におもな出来事を中心にして回想風に書き綴ったもので、たいへん面白かった。もちろんこれほど高名な著述家の秘書ということもそうだし、その働きぶりのすごさということでもそうだった。なによりもこの人の文章の上手さには感心した。とくに「1冬の海辺で」だけは特別に詩情豊かな文体で書かれており、この部分をもっと引き伸ばすなり、小説の一部にするなりして、なにかフィクションものとかを書けば、きっとすばらしいものが書けるのではないかと思うほど素晴らしい。ここだけがそれ以外のどちらかと言うとルポルタージュ風の書き方から浮いている。まるで散文詩とでも言ってもいいくらいの詩情を湛えている。
秘書の仕事と言うことでいえばまさに知的世界である。もちろんそれ以外の力仕事もたくさんあるのだろうが、だからといってだれにでもできるものではないが、それを最終的には雇い主である立花隆は理解していなかった、まるで自分ひとりの力で仕事をしてきたかのような扱い方で、つまり役にも立たぬものに給料を払っているというようなことを公の場で口にしたことが、著者の立花にたいする軽蔑に似た感情を抱かせることになったようだ。
数多くのノンフィクションを書いてきた巨人であることを前提にしたうえで、なおかつ思うのだが、たとえば東大での教員生活を終えたころに彼が感じた疲れのことが書かれているが、それは私にはたしかに自分の好奇心に忠実に現実を調査して、立花自身の言葉によれば百のインプットから一のアウトプットをすることでノンフィクションを書いてきたわけだが、彼が東大で目にしてきた専門家たちとちがって何一つ「極める」ことがなかったことに、本当に自分の人生はこれでよかったのだろうかと言うような思いを抱いたのではないかと想像するのだ。東大で彼が目にしてきた研究者や研究者の卵たちはまさにその分野を極めたり極めることを目指して日夜研究に励んでいる。たしかに立花と同じように百のインプットから一のアウトプットしかできないかもしれないが、彼らはまさにオリジナルな一をアウトプットしているし、することを目指しているのであって、立花のような現実の忠実なアウトプットではない。そこにはオリジナルなものは何一つないことを、この元秘書はリアルに見抜いていたのだろう。それがこの著作の最後における辛辣な発言となって、自分に対する無理解者であった雇い主へ向けられることになったのだろう。
こうした広く深くという知のあり方は一見すると百科全書的な知の巨人を思わせるが、そのじつ松岡正剛の著作について指摘したことがあるように、その専門の筋の人が読むと明らかな間違いを含んでいることがある、あるいはそうした間違った知識を土台にして議論が進められているというようなことが必ずあるものだ。そういう危うさをはたして立花が自覚していたのかどうか。そういうことへの自覚あるいは謙虚な態度が、この元秘書が立花のもとを去る頃には欠落していることが見えていたような指摘がされている。
これを読んで私が違和感を感じたのは大江健三郎にたいする立花の無批判的尊敬の念である。まぁだれがだれを尊敬しようと軽蔑しようと勝手なので、目くじらを立てることではないが、大江健三郎がサヨクの運動において(とりわけ反核平和の運動)サヨクに位置する立場からサヨクをないがしろにするような行動をとってきたことについて本多勝一が書いていたが、私はこちらに与する。けっして大江は尊敬できるような人間ではないと思うのだ。
そうした落とし穴に立花を落とし込む方向に作用したのは、この元秘書がいみじくも鋭く見抜いたように、立花は好奇心だけが生命であってほんとうにその対象を味わうことはどうでもいいのだ。ワインしかり音楽しかり。それと同じことが武満にたいしても作用していたらしい。立花は武満の音楽なんかには興味がない。武満がどうやって音楽を作り出すのかということにしか興味がないというのだ。同じことが大江健三郎を対象にしても起こっていたのだろう。大江が日本の文学界の中でどのような文学を作りどのような役割を果たしていたのかなんかは興味がない。東大の先輩でありノーベル賞作家であり障害者の父親であるということにしか興味がない。そしてそれは立花にとっては先験的に敬意の対象になるのだろう。
この本を読んで私がしみじみ感じたことは、クリエイティブこそがオリジナリティーこそが大事なのだ、滅びることなく、古びることのないものなんだということだった。
 1993年5月から1998年末までのあいだ立花隆の秘書を経験した著者がその体験を時系列におもな出来事を中心にして回想風に書き綴ったもので、たいへん面白かった。もちろんこれほど高名な著述家の秘書ということもそうだし、その働きぶりのすごさということでもそうだった。なによりもこの人の文章の上手さには感心した。とくに「1冬の海辺で」だけは特別に詩情豊かな文体で書かれており、この部分をもっと引き伸ばすなり、小説の一部にするなりして、なにかフィクションものとかを書けば、きっとすばらしいものが書けるのではないかと思うほど素晴らしい。ここだけがそれ以外のどちらかと言うとルポルタージュ風の書き方から浮いている。まるで散文詩とでも言ってもいいくらいの詩情を湛えている。
1993年5月から1998年末までのあいだ立花隆の秘書を経験した著者がその体験を時系列におもな出来事を中心にして回想風に書き綴ったもので、たいへん面白かった。もちろんこれほど高名な著述家の秘書ということもそうだし、その働きぶりのすごさということでもそうだった。なによりもこの人の文章の上手さには感心した。とくに「1冬の海辺で」だけは特別に詩情豊かな文体で書かれており、この部分をもっと引き伸ばすなり、小説の一部にするなりして、なにかフィクションものとかを書けば、きっとすばらしいものが書けるのではないかと思うほど素晴らしい。ここだけがそれ以外のどちらかと言うとルポルタージュ風の書き方から浮いている。まるで散文詩とでも言ってもいいくらいの詩情を湛えている。秘書の仕事と言うことでいえばまさに知的世界である。もちろんそれ以外の力仕事もたくさんあるのだろうが、だからといってだれにでもできるものではないが、それを最終的には雇い主である立花隆は理解していなかった、まるで自分ひとりの力で仕事をしてきたかのような扱い方で、つまり役にも立たぬものに給料を払っているというようなことを公の場で口にしたことが、著者の立花にたいする軽蔑に似た感情を抱かせることになったようだ。
数多くのノンフィクションを書いてきた巨人であることを前提にしたうえで、なおかつ思うのだが、たとえば東大での教員生活を終えたころに彼が感じた疲れのことが書かれているが、それは私にはたしかに自分の好奇心に忠実に現実を調査して、立花自身の言葉によれば百のインプットから一のアウトプットをすることでノンフィクションを書いてきたわけだが、彼が東大で目にしてきた専門家たちとちがって何一つ「極める」ことがなかったことに、本当に自分の人生はこれでよかったのだろうかと言うような思いを抱いたのではないかと想像するのだ。東大で彼が目にしてきた研究者や研究者の卵たちはまさにその分野を極めたり極めることを目指して日夜研究に励んでいる。たしかに立花と同じように百のインプットから一のアウトプットしかできないかもしれないが、彼らはまさにオリジナルな一をアウトプットしているし、することを目指しているのであって、立花のような現実の忠実なアウトプットではない。そこにはオリジナルなものは何一つないことを、この元秘書はリアルに見抜いていたのだろう。それがこの著作の最後における辛辣な発言となって、自分に対する無理解者であった雇い主へ向けられることになったのだろう。
こうした広く深くという知のあり方は一見すると百科全書的な知の巨人を思わせるが、そのじつ松岡正剛の著作について指摘したことがあるように、その専門の筋の人が読むと明らかな間違いを含んでいることがある、あるいはそうした間違った知識を土台にして議論が進められているというようなことが必ずあるものだ。そういう危うさをはたして立花が自覚していたのかどうか。そういうことへの自覚あるいは謙虚な態度が、この元秘書が立花のもとを去る頃には欠落していることが見えていたような指摘がされている。
これを読んで私が違和感を感じたのは大江健三郎にたいする立花の無批判的尊敬の念である。まぁだれがだれを尊敬しようと軽蔑しようと勝手なので、目くじらを立てることではないが、大江健三郎がサヨクの運動において(とりわけ反核平和の運動)サヨクに位置する立場からサヨクをないがしろにするような行動をとってきたことについて本多勝一が書いていたが、私はこちらに与する。けっして大江は尊敬できるような人間ではないと思うのだ。
そうした落とし穴に立花を落とし込む方向に作用したのは、この元秘書がいみじくも鋭く見抜いたように、立花は好奇心だけが生命であってほんとうにその対象を味わうことはどうでもいいのだ。ワインしかり音楽しかり。それと同じことが武満にたいしても作用していたらしい。立花は武満の音楽なんかには興味がない。武満がどうやって音楽を作り出すのかということにしか興味がないというのだ。同じことが大江健三郎を対象にしても起こっていたのだろう。大江が日本の文学界の中でどのような文学を作りどのような役割を果たしていたのかなんかは興味がない。東大の先輩でありノーベル賞作家であり障害者の父親であるということにしか興味がない。そしてそれは立花にとっては先験的に敬意の対象になるのだろう。
この本を読んで私がしみじみ感じたことは、クリエイティブこそがオリジナリティーこそが大事なのだ、滅びることなく、古びることのないものなんだということだった。