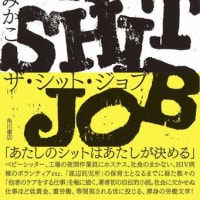中村孝義『室内楽の歴史』(東京書籍、1994年)
 この人は、大阪音大の学長をしている人で、私が毎年のように行っている大阪音大の学生オペラの冊子に挨拶を書いているので、なんだか面識があるような気になっているが、もちろんまったく知らない。いわゆる音大出身ではないのに(たぶんドイツに留学したことでそうしたマイナス面はチャラになったのだと思うが)、音大の音楽史の教員になるという経歴をもつ。しかしこの本を読むと、そういう経歴も見かけだけのものではないと分かる。
この人は、大阪音大の学長をしている人で、私が毎年のように行っている大阪音大の学生オペラの冊子に挨拶を書いているので、なんだか面識があるような気になっているが、もちろんまったく知らない。いわゆる音大出身ではないのに(たぶんドイツに留学したことでそうしたマイナス面はチャラになったのだと思うが)、音大の音楽史の教員になるという経歴をもつ。しかしこの本を読むと、そういう経歴も見かけだけのものではないと分かる。
私の関心のあるところでいうと、第二章から第四章のバロックから古典派へいたる室内楽、とくにこの場合はトリオ・ソナタから弦楽四重奏への変遷の道のりが、社会文化史、音楽史などを織り込んで丁寧に記述してある。
たとえばバロック音楽によって始まったモノディー様式は、歌詞の情緒的内容を表現するために、レチタティーヴォとそれを支える通奏低音による和音的伴奏という形をもつが、旋律の自由な扱いが可能であることから、表現の幅が広がったが、だからと言って、それは決して音楽家の主観的感情を表すためのものではなく、歌詞がもつ普遍的な情感の表現であって、まさに「情緒論」とか「情念論」と言われるような普遍的な情念を一定の音型や音楽的手法という外的現象にむすびつけるものだったと説明されている。(p.31-32)
これは上声部の旋律(あるいはレチタティーヴォ)が好き勝手に動き回れるわけではなくて、通奏低音が示す和声の枠内でしか動けいないことを意味する。しかもこの通奏低音による和声連結が、前のカデンツの終結和音が次の段落の開始和音になるという決まりがあることから、極端に言えば、通奏低音に基づいて作られている作品は、最初の開始和音が演奏された時点ですでにもうその曲の流れ全体が必然的に決定され、ある意味で終結まで見通せてしまうということになる。そしてこうしたバロックの通奏低音によって作られる作品世界の特徴について、つぎのように説明される
「このような在り方は、われわれの現実の感情がそのまま投影されたような、リアリティーにとんだ世界を表現するのは難しいが、逆に「あるべき」理想的な、あるいは現実には存在しない仮構の世界を表現するにはうってつけなのである。そしてこのような音楽の性格が、一つの情緒が楽章全体を支配しているという印象をわれわれに強く感じさせることになる。」(p.34-35)
だからバロックにおける通奏低音はたんに和声上のバス声部ではなくて、上に乗るすべての声部の可能性を含みこんだ曲全体の土台であり、中核であると言える。まさに絶対的国王が社会を支配し、その上で彼を称えるように経済、政治、文化の様々な活動が華やかに行われるが、あくまでもこの王政の枠の中でしかないという絶対王政のイデオロギーにマッチする音楽の姿ではないだろうか。
この本は室内楽のためのものなので、こうした観点から、トリオ・ソナタの特徴についてコレッリなどを中心に記述されている。
さらに第四章になるとハイドンとかモーツァルトの弦楽四重奏の話になる。このあたりになると、かつて知り合いと初期のモーツァルトとかハイドンの弦楽四重奏を弾いて楽しんでいたことがあったので、書かれていることもすっと頭に入っていく。これを読んで、久しぶりにモーツァルトのK80とかK179などを聞いてみたが、まだこの時期のものは、チェロとかビオラが、通奏低音のように、リズムをとったり、バスを鳴らすだけの動きしかないので、チェロの人が嫌がっていたのを思い出す。だからといって、ハイドンセットなんかは、今度はヴァイオリンの担当が弾けないのだ。しかしそういう力量の問題はあっても、ただ黙々と、それぞれが自分のパートの音符を追っているだけに見えても、じつは突然入ってくるチェロの低くて太い音に心揺すぶられたり、ビオラの甘い音色に聞き惚れたりと、弦楽四重奏ならではの味わい方がある。それはやはり演奏してみないと経験できない面白みだろう。
この本ではそのあたりのことが、バロック時代には領主や国王たちの室内という限られた場所での彼らの要求に応じて作られたいたトリオ・ソナタなどの室内楽が、一般に作品を売らねばならないという、かつて経験したことのなかった世界に投げ込まれるようになった作曲家たちが、交響曲や協奏曲のような公開演奏会などで演奏される華やかで効果のある曲種を作曲することで大衆の直接的で激しい感情の起伏を提示してみせると同時にに、自分の内面に生きていく上での苦悩や葛藤や危機感を抱くことになり、そうすることで職人から芸術家としての意識に目覚め、それが室内楽の意味に変化を引き起こさせることになり、弦楽四重奏という古典派に固有のジャンルを誕生させることになったと説明されている(p.103-105)。実に巧みな説明だと思う。
 この人は、大阪音大の学長をしている人で、私が毎年のように行っている大阪音大の学生オペラの冊子に挨拶を書いているので、なんだか面識があるような気になっているが、もちろんまったく知らない。いわゆる音大出身ではないのに(たぶんドイツに留学したことでそうしたマイナス面はチャラになったのだと思うが)、音大の音楽史の教員になるという経歴をもつ。しかしこの本を読むと、そういう経歴も見かけだけのものではないと分かる。
この人は、大阪音大の学長をしている人で、私が毎年のように行っている大阪音大の学生オペラの冊子に挨拶を書いているので、なんだか面識があるような気になっているが、もちろんまったく知らない。いわゆる音大出身ではないのに(たぶんドイツに留学したことでそうしたマイナス面はチャラになったのだと思うが)、音大の音楽史の教員になるという経歴をもつ。しかしこの本を読むと、そういう経歴も見かけだけのものではないと分かる。私の関心のあるところでいうと、第二章から第四章のバロックから古典派へいたる室内楽、とくにこの場合はトリオ・ソナタから弦楽四重奏への変遷の道のりが、社会文化史、音楽史などを織り込んで丁寧に記述してある。
たとえばバロック音楽によって始まったモノディー様式は、歌詞の情緒的内容を表現するために、レチタティーヴォとそれを支える通奏低音による和音的伴奏という形をもつが、旋律の自由な扱いが可能であることから、表現の幅が広がったが、だからと言って、それは決して音楽家の主観的感情を表すためのものではなく、歌詞がもつ普遍的な情感の表現であって、まさに「情緒論」とか「情念論」と言われるような普遍的な情念を一定の音型や音楽的手法という外的現象にむすびつけるものだったと説明されている。(p.31-32)
これは上声部の旋律(あるいはレチタティーヴォ)が好き勝手に動き回れるわけではなくて、通奏低音が示す和声の枠内でしか動けいないことを意味する。しかもこの通奏低音による和声連結が、前のカデンツの終結和音が次の段落の開始和音になるという決まりがあることから、極端に言えば、通奏低音に基づいて作られている作品は、最初の開始和音が演奏された時点ですでにもうその曲の流れ全体が必然的に決定され、ある意味で終結まで見通せてしまうということになる。そしてこうしたバロックの通奏低音によって作られる作品世界の特徴について、つぎのように説明される
「このような在り方は、われわれの現実の感情がそのまま投影されたような、リアリティーにとんだ世界を表現するのは難しいが、逆に「あるべき」理想的な、あるいは現実には存在しない仮構の世界を表現するにはうってつけなのである。そしてこのような音楽の性格が、一つの情緒が楽章全体を支配しているという印象をわれわれに強く感じさせることになる。」(p.34-35)
だからバロックにおける通奏低音はたんに和声上のバス声部ではなくて、上に乗るすべての声部の可能性を含みこんだ曲全体の土台であり、中核であると言える。まさに絶対的国王が社会を支配し、その上で彼を称えるように経済、政治、文化の様々な活動が華やかに行われるが、あくまでもこの王政の枠の中でしかないという絶対王政のイデオロギーにマッチする音楽の姿ではないだろうか。
この本は室内楽のためのものなので、こうした観点から、トリオ・ソナタの特徴についてコレッリなどを中心に記述されている。
さらに第四章になるとハイドンとかモーツァルトの弦楽四重奏の話になる。このあたりになると、かつて知り合いと初期のモーツァルトとかハイドンの弦楽四重奏を弾いて楽しんでいたことがあったので、書かれていることもすっと頭に入っていく。これを読んで、久しぶりにモーツァルトのK80とかK179などを聞いてみたが、まだこの時期のものは、チェロとかビオラが、通奏低音のように、リズムをとったり、バスを鳴らすだけの動きしかないので、チェロの人が嫌がっていたのを思い出す。だからといって、ハイドンセットなんかは、今度はヴァイオリンの担当が弾けないのだ。しかしそういう力量の問題はあっても、ただ黙々と、それぞれが自分のパートの音符を追っているだけに見えても、じつは突然入ってくるチェロの低くて太い音に心揺すぶられたり、ビオラの甘い音色に聞き惚れたりと、弦楽四重奏ならではの味わい方がある。それはやはり演奏してみないと経験できない面白みだろう。
この本ではそのあたりのことが、バロック時代には領主や国王たちの室内という限られた場所での彼らの要求に応じて作られたいたトリオ・ソナタなどの室内楽が、一般に作品を売らねばならないという、かつて経験したことのなかった世界に投げ込まれるようになった作曲家たちが、交響曲や協奏曲のような公開演奏会などで演奏される華やかで効果のある曲種を作曲することで大衆の直接的で激しい感情の起伏を提示してみせると同時にに、自分の内面に生きていく上での苦悩や葛藤や危機感を抱くことになり、そうすることで職人から芸術家としての意識に目覚め、それが室内楽の意味に変化を引き起こさせることになり、弦楽四重奏という古典派に固有のジャンルを誕生させることになったと説明されている(p.103-105)。実に巧みな説明だと思う。