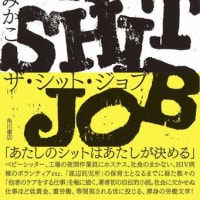金容雲『日本語の正体―倭の大王は百済語で話す』(三五館、2009年)
私は前々から、日本語のルーツを明らかにするには、日本語から韓国語とか中国語あるいはアジアの諸国の言語を見ていてはだめで、どう考えても、日本語は辺境の地なのだから、起源にあたる韓国語や中国語のほうから日本語を見ていかなければならないのではないかと考えていたのだが、幼少時代を日本で過ごし、日本語にも堪能で(この本は著者が自ら日本語で書いたというから、相当の日本語力を持っている)韓国語も古い時代のものも読めるような人が、やっと日韓両国の言語の関係を解き明かしてくれたので、非常に面白く読んだ。
日本語韓国語の関係を示す図表が175ページにあるが、これを見るとよくわかる。もともと縄文時代のあとに朝鮮半島から百済系の人々が入ってきて稲作などの文化を持ち込み、その後新羅系も入ってきたが、最終的に天智天皇の頃までは、大和朝廷では百済系の人々が支配していたので、百済語が使われていた。といっても当時の百済語と新羅語は方言程度の違いしかなかったので、ほとんど通訳なども必要なかったが、白村江の戦いが転機になったらしい。
新羅が唐と連合して半島を統一してから朝鮮は新羅語に染まった。新羅が唐のおかげで半島を統一できたことから、中国化を強力に推し進めたために、漢字の中国語読みが導入され、母音が増えていき、この時期から、朝鮮語そのものが大きく変化するようになった。その結果、当時の唐の中国語の音韻が朝鮮にずっと残ることになり、その後中国は北方系の民族が支配するようになったために変わってしまったが、朝鮮語の音韻が古い中国語の音韻研究に役立ったという。他方日本列島のほうは、辺境の地の言語が保守化するという一般法則通り、かつての韓国語をそのまま残して少しずつ変化していって現代日本語になったという。つまり古い韓国語の音韻を調べるには日本語を調べるほうが役に立つということらしい。
私のまとめは、もちろんかなり大雑把なやり方なのだが、日韓両言語の大きな流れを俯瞰するにはこんなものなのだろう。辺境の地の言語が保守化するというのはたしかにそうで、たとえばかつてフランス人が移植していたことから現在でもフランス語圏となっているカナダのケベックでは17世紀のフランス語の発音が残っているという。私自身もfrancaiseを「フランセーズ」ではなくて「フランサイズ」と発音するケベック人に会ったことがある。
面白い。もっとこういう方面の研究をやる人がたくさん出てきて欲しいものだ。
 | 日本語の正体―倭の大王は百済語で話す |
| 金 容雲 | |
| 三五館 |
日本語韓国語の関係を示す図表が175ページにあるが、これを見るとよくわかる。もともと縄文時代のあとに朝鮮半島から百済系の人々が入ってきて稲作などの文化を持ち込み、その後新羅系も入ってきたが、最終的に天智天皇の頃までは、大和朝廷では百済系の人々が支配していたので、百済語が使われていた。といっても当時の百済語と新羅語は方言程度の違いしかなかったので、ほとんど通訳なども必要なかったが、白村江の戦いが転機になったらしい。
新羅が唐と連合して半島を統一してから朝鮮は新羅語に染まった。新羅が唐のおかげで半島を統一できたことから、中国化を強力に推し進めたために、漢字の中国語読みが導入され、母音が増えていき、この時期から、朝鮮語そのものが大きく変化するようになった。その結果、当時の唐の中国語の音韻が朝鮮にずっと残ることになり、その後中国は北方系の民族が支配するようになったために変わってしまったが、朝鮮語の音韻が古い中国語の音韻研究に役立ったという。他方日本列島のほうは、辺境の地の言語が保守化するという一般法則通り、かつての韓国語をそのまま残して少しずつ変化していって現代日本語になったという。つまり古い韓国語の音韻を調べるには日本語を調べるほうが役に立つということらしい。
私のまとめは、もちろんかなり大雑把なやり方なのだが、日韓両言語の大きな流れを俯瞰するにはこんなものなのだろう。辺境の地の言語が保守化するというのはたしかにそうで、たとえばかつてフランス人が移植していたことから現在でもフランス語圏となっているカナダのケベックでは17世紀のフランス語の発音が残っているという。私自身もfrancaiseを「フランセーズ」ではなくて「フランサイズ」と発音するケベック人に会ったことがある。
面白い。もっとこういう方面の研究をやる人がたくさん出てきて欲しいものだ。