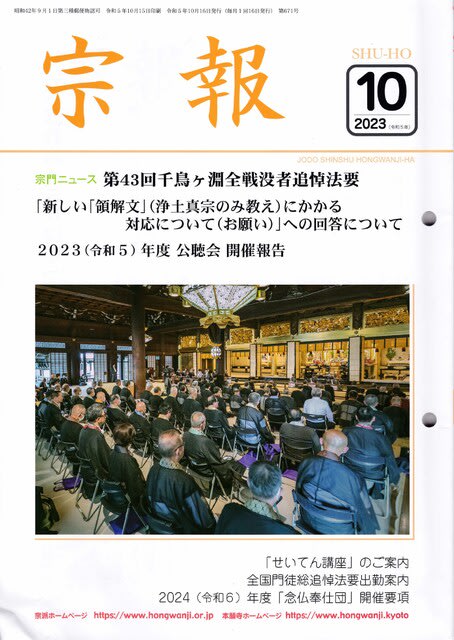
『宗報』(2023.10月号)『現代社会と「いきづらさ」―通俗道徳のわな』から一部転載します。
生きづらさと通俗道徳
現代において人びとが「生きづらさ」を感じてしまう原因は何か。この問いには多様な答えがありうるはずですが、ここでは、明治時代もまた「生きづらい」社会であったことを「通俗道徳のわな」として明らかにした松沢裕作氏の主張(『生きづらい明治社会-不安と競争の時代』(二〇一八年)に注目したいと思います。
松沢氏は、明治時代の社会を貧富の差が大きい社会であり、貧困は自己責任として困窮者への政策を限定的にしか「弱者に冷たい社会」と評し、その背景に「人びとが通俗道徳のわなにはまっていた」ことがあると指摘しています。通俗道徳とは、「人生で失敗したり貧困に陥ったりするのは、その人の努力が足りないからだ」とする考え方で、松沢氏は歴史学者の安丸良夫氏の研究に従いながら、市場経済がひろがり、入びとの生活が不安定になった江戸時代の後半に、自分で自分を律するための基準として広まったといわれます。では、通俗道徳が広がるとどうなるか。人びとは努力、勤勉さ、倹約などを大事にして生活します。そうしたことの結果として成功する人、目標を達成できる人がいることは間違いありません。しかしながら、誰もが成功できるとは限りません。中には失敗してしまう人もいるはずです。このとき、人びとは通俗道徳を大切にするから失敗した人たちに対して、こう考えてしまいます。
「努力してないからだ」「努力が足りないからだ」「もっとやらないと成功しない」。これが「通俗道徳のわな」です。そして、誰もが「通俗道徳のわな」にはまってしまうからこそ、一見するとまっとうな、「成功するためには努力しなければならない」という通俗道徳の教えは、「どんな手段をつかっても、他人を蹴落としてでも成功しなければならない」という、過酷な競争社会を生み出してしまうのです。
と松沢氏は述べられています。
「通俗道徳のわな」に誰もがはまってしまっているからこそ、人びとはとにかく自分が頑張るしかない。成功しないのは自分か悪いからだといっそう自分自身を苦しめてしまう状況に追い込まれてしまう。松沢氏はこうしか社会を「生きづらい」社会といい、社会の中で「努力しても報われなかった人」「どうしても頑張りきれなかった人」、そうした人びとを受け止める仕組みが充分に用意されていないのではないかと述べています。(つづく)
生きづらさと通俗道徳
現代において人びとが「生きづらさ」を感じてしまう原因は何か。この問いには多様な答えがありうるはずですが、ここでは、明治時代もまた「生きづらい」社会であったことを「通俗道徳のわな」として明らかにした松沢裕作氏の主張(『生きづらい明治社会-不安と競争の時代』(二〇一八年)に注目したいと思います。
松沢氏は、明治時代の社会を貧富の差が大きい社会であり、貧困は自己責任として困窮者への政策を限定的にしか「弱者に冷たい社会」と評し、その背景に「人びとが通俗道徳のわなにはまっていた」ことがあると指摘しています。通俗道徳とは、「人生で失敗したり貧困に陥ったりするのは、その人の努力が足りないからだ」とする考え方で、松沢氏は歴史学者の安丸良夫氏の研究に従いながら、市場経済がひろがり、入びとの生活が不安定になった江戸時代の後半に、自分で自分を律するための基準として広まったといわれます。では、通俗道徳が広がるとどうなるか。人びとは努力、勤勉さ、倹約などを大事にして生活します。そうしたことの結果として成功する人、目標を達成できる人がいることは間違いありません。しかしながら、誰もが成功できるとは限りません。中には失敗してしまう人もいるはずです。このとき、人びとは通俗道徳を大切にするから失敗した人たちに対して、こう考えてしまいます。
「努力してないからだ」「努力が足りないからだ」「もっとやらないと成功しない」。これが「通俗道徳のわな」です。そして、誰もが「通俗道徳のわな」にはまってしまうからこそ、一見するとまっとうな、「成功するためには努力しなければならない」という通俗道徳の教えは、「どんな手段をつかっても、他人を蹴落としてでも成功しなければならない」という、過酷な競争社会を生み出してしまうのです。
と松沢氏は述べられています。
「通俗道徳のわな」に誰もがはまってしまっているからこそ、人びとはとにかく自分が頑張るしかない。成功しないのは自分か悪いからだといっそう自分自身を苦しめてしまう状況に追い込まれてしまう。松沢氏はこうしか社会を「生きづらい」社会といい、社会の中で「努力しても報われなかった人」「どうしても頑張りきれなかった人」、そうした人びとを受け止める仕組みが充分に用意されていないのではないかと述べています。(つづく)






























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます