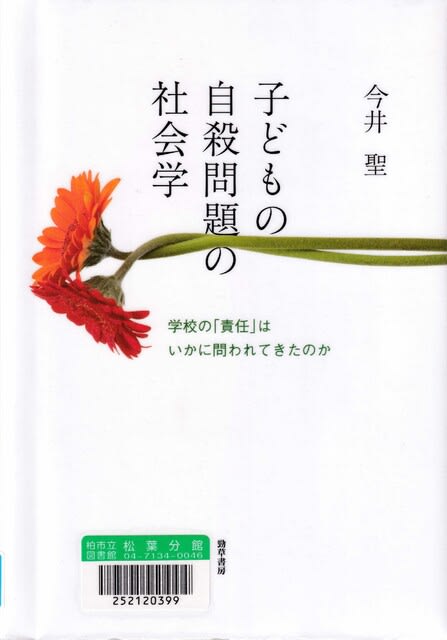
『子どもの自殺問題の社会学: 学校の「責任」はいかに問われてきたのか』(2025/3/3・今井聖著)、この本で「指導死」という自殺の概念がることを知りました。その部分だけ転載します。
ある新たな概念が登場することによって,人びとの生き方や経験のありようがそれまでとはまったく異なったものになる場合がある。このことは,すでによく知られた事実であるとも言える。たとえば,ある時期以降,性的な事柄に関わる嫌がらせの行為が「セクシュアル・ハラスメント」として捉えられるようになったことや,一定の性格特性や行動の傾向を備えるとされた子どもが「発達障害児」と捉えられるようになったことなどはよく知られたことであろう。とはいえ,通常の日常生活のコンテクストで目を向けられるのは,たとえばある行為が[セクハラ]かどうかという点であるはずだ。その意味で,ある特定の概念の歴史に目を向けることはあまり日常的でない,特別な関心の向け方だと言えるだろ佰。
既述のとおり,子どもの自殺に関するこれまでの社会学研究では,とりわけ[いじめ自殺]に対して,そうした特別な関心が向けられてきた。それらの研究が共通して指摘していたのは,[いじめ自殺]という概念一類型が社会的に広く認識されたのは,1980年代においてだということであった。
その例として,「指導巡る死『真摯に向き合って』調査求める母親。応じない道教委 道立高生自殺]という見出しの記事仟朝日新聞J 2021/11/10朝刊,北海道面)など。
本章ではこれまで,「指導死」という新たな概念のもとで。子どもの自殺に関する人びとの経験の可能性がいかに変容したのかを,遺族たちの語りにもとづいて考察してきた。
そうした議論の前提として,「指導死」をめぐっては,「指導」と「自殺」が通常結びつきうるものとして用いられていないことに由来する,表現にの問題が存在していたことを確認した。その上で,そうした問題は単に表現上の問題であるばかりか,「指導死」概念を提起した遺族たちの当初の目的にとっても直接関わる問題であったことを,[体罰自殺]と「指導死」の関係を問うことによって示した。
当初よりそうした微妙な問題をはらんでいた「指導死」という概念であるが,結果的には,今日に至るまでに一定の社会的認知を獲得してきたと言える。では,そうした概念の登場とその広まりは,何をもたらしたのだろうか。
この問いに対する答えとして本章での議論からまず言えるのは,教師の指導をきっかけに自殺したとされる子どもの自殺をめぐって,その遺族が置かれることになる社会的状況や可能な経験のあり方に「指導死」概念は一定の変化をもたらしてきたということである。「指導死」という概念が,「指導死」という出来事の存在を可能にするものでもある以上,それがまったく[ない]とすら語られていた頃に遺族たちが強いられていたような立場は,今日では解消されるに至ったと言える(とはいえ,それは経験の可能性という水準でのことであって,個別具体的な事例においてそれぞれの遺族が実際にどのような他者の反応に哂されることになるのかはまた別であることは言うまでもない)。そして,より近年の「指導死」事件について見ることで確認できたように遺族が置かれうる社会的状況の変化には,子どもの自殺事件に関して組織される第三者調査委員会の広まりといった制度的な要因も関係している。[指導死]に関する言説とともに制度的条件も変化しつつあるということである。
本章で見てきたように「指導死」という新たな概念の登場は,遺族となった人たちの経験の可能性を変容させてきた。重要なのは,同時にそれが,社会一般のより広範な人びとにとっての可能な経験の変化でもあるということだ。「指導死」という出来事が成立した後の時点である今日,この社会に生きる人であれば誰であれ,「指導死」は存在しない等といったことを有意味に述べることはできない。その意味で,[指導死]という新たな概念の登場とその広まりは,子どもの自殺をめぐる「現実」や,人びとにとって可能な社会的経験を変容させてきたのだと言える。
最後にではそうした新たな概念の登場という事態は,「いじめ自殺」がそうであったとされるように「不幸」な帰結を導いてしまったのか,それとも「セクハラ」や[児童虐待]がそうであったように人びとの「救済」につながったと言えるのかという問題を考えてみたい。筆者の見るところ,少なくとも「いじめられて死ぬほど苦しい」子どもが実際に自殺してしまう事態ほど,「指導が死ぬほど苦しい」子どもが自殺するという事態は,今日においても容易に理解可能なものと見なされていないように思われる。言い換えれば,今日でも,ある教師の指導が子どもの自殺の原因として社会的に認められるためには,当該の指導が通常許容されうる範囲を相当程度逸脱した「不適切な」ものであることの証明が必要とされている。それは,「不適切な」ものであることが前提第7章 「子どもの自殺」に関する新たな概念としての[指導死]とされている(それゆえ,加害・被害関係をもとより含意している)「いじめ」が子どもの自殺の原因として語られる場合とは異なる。そしてそうである以上,「指導死」は少なくとも「いじめ自殺」と同じように「不幸」な帰結を導くことにはなっていないと考えられる。他方で,「指導死」は,まずはそれまでその出来事を語ることができなかった遺族たちを「救済」する役目を果たしてきたと言える。その意味では,これまでのところ「指導死」概念を必要としてきたのも第一義的には遺族たち自身であったと言えるのかもしれない。
「指導死」概念がある人びとを[救済]する意味を有してきたというここでの議論に関しては,さらに[被害者]である子どもの[救済]という点を考える必要もあるだろう。必ずしも「指導死」概念が登場することのみによって可能になるわけではないものの,そうした概念の広まりが,教師の指導のあり方をけじめとし,学校教育現場での様々なやりとりのあり方を問い直していくためのひとつの契機となりうることは明らかである。そうした社会的状況の変化はまた,子どもやその親といった「当事者」にとって,教師の「不適切な」指導やそれによる被害経験に対する訴えをより容易にするものでもあるだろう。
なお,そのような新たな概念の登場による「被害者の救済」という点に限って言えば,「いじめ」や「いじめ自殺」という概念にも,子どもやその親といった「当事者」たち匚とっての「救済」に役立ってきた側面があることも否定できない。「いじめ自殺」に関する既存研究では十分注意が向けられてこなかったが,そうした側面が[いじめ自殺]概念の「解体」(北洋2015)を困難にしている可能性には,より注意が向けられて然るべきであるだろう。そうした今日の「現実」のありようを踏まえたその上で,いかに「いじめ問題」や「いじめ」という「物語」を組み替えていけるのかが問われなければならないと思われるのだ。次章では,このような関心のもとで,「いじめ自殺」事件の遺族たちの経験を問うことを試みる。(以上)
ある新たな概念が登場することによって,人びとの生き方や経験のありようがそれまでとはまったく異なったものになる場合がある。このことは,すでによく知られた事実であるとも言える。たとえば,ある時期以降,性的な事柄に関わる嫌がらせの行為が「セクシュアル・ハラスメント」として捉えられるようになったことや,一定の性格特性や行動の傾向を備えるとされた子どもが「発達障害児」と捉えられるようになったことなどはよく知られたことであろう。とはいえ,通常の日常生活のコンテクストで目を向けられるのは,たとえばある行為が[セクハラ]かどうかという点であるはずだ。その意味で,ある特定の概念の歴史に目を向けることはあまり日常的でない,特別な関心の向け方だと言えるだろ佰。
既述のとおり,子どもの自殺に関するこれまでの社会学研究では,とりわけ[いじめ自殺]に対して,そうした特別な関心が向けられてきた。それらの研究が共通して指摘していたのは,[いじめ自殺]という概念一類型が社会的に広く認識されたのは,1980年代においてだということであった。
その例として,「指導巡る死『真摯に向き合って』調査求める母親。応じない道教委 道立高生自殺]という見出しの記事仟朝日新聞J 2021/11/10朝刊,北海道面)など。
本章ではこれまで,「指導死」という新たな概念のもとで。子どもの自殺に関する人びとの経験の可能性がいかに変容したのかを,遺族たちの語りにもとづいて考察してきた。
そうした議論の前提として,「指導死」をめぐっては,「指導」と「自殺」が通常結びつきうるものとして用いられていないことに由来する,表現にの問題が存在していたことを確認した。その上で,そうした問題は単に表現上の問題であるばかりか,「指導死」概念を提起した遺族たちの当初の目的にとっても直接関わる問題であったことを,[体罰自殺]と「指導死」の関係を問うことによって示した。
当初よりそうした微妙な問題をはらんでいた「指導死」という概念であるが,結果的には,今日に至るまでに一定の社会的認知を獲得してきたと言える。では,そうした概念の登場とその広まりは,何をもたらしたのだろうか。
この問いに対する答えとして本章での議論からまず言えるのは,教師の指導をきっかけに自殺したとされる子どもの自殺をめぐって,その遺族が置かれることになる社会的状況や可能な経験のあり方に「指導死」概念は一定の変化をもたらしてきたということである。「指導死」という概念が,「指導死」という出来事の存在を可能にするものでもある以上,それがまったく[ない]とすら語られていた頃に遺族たちが強いられていたような立場は,今日では解消されるに至ったと言える(とはいえ,それは経験の可能性という水準でのことであって,個別具体的な事例においてそれぞれの遺族が実際にどのような他者の反応に哂されることになるのかはまた別であることは言うまでもない)。そして,より近年の「指導死」事件について見ることで確認できたように遺族が置かれうる社会的状況の変化には,子どもの自殺事件に関して組織される第三者調査委員会の広まりといった制度的な要因も関係している。[指導死]に関する言説とともに制度的条件も変化しつつあるということである。
本章で見てきたように「指導死」という新たな概念の登場は,遺族となった人たちの経験の可能性を変容させてきた。重要なのは,同時にそれが,社会一般のより広範な人びとにとっての可能な経験の変化でもあるということだ。「指導死」という出来事が成立した後の時点である今日,この社会に生きる人であれば誰であれ,「指導死」は存在しない等といったことを有意味に述べることはできない。その意味で,[指導死]という新たな概念の登場とその広まりは,子どもの自殺をめぐる「現実」や,人びとにとって可能な社会的経験を変容させてきたのだと言える。
最後にではそうした新たな概念の登場という事態は,「いじめ自殺」がそうであったとされるように「不幸」な帰結を導いてしまったのか,それとも「セクハラ」や[児童虐待]がそうであったように人びとの「救済」につながったと言えるのかという問題を考えてみたい。筆者の見るところ,少なくとも「いじめられて死ぬほど苦しい」子どもが実際に自殺してしまう事態ほど,「指導が死ぬほど苦しい」子どもが自殺するという事態は,今日においても容易に理解可能なものと見なされていないように思われる。言い換えれば,今日でも,ある教師の指導が子どもの自殺の原因として社会的に認められるためには,当該の指導が通常許容されうる範囲を相当程度逸脱した「不適切な」ものであることの証明が必要とされている。それは,「不適切な」ものであることが前提第7章 「子どもの自殺」に関する新たな概念としての[指導死]とされている(それゆえ,加害・被害関係をもとより含意している)「いじめ」が子どもの自殺の原因として語られる場合とは異なる。そしてそうである以上,「指導死」は少なくとも「いじめ自殺」と同じように「不幸」な帰結を導くことにはなっていないと考えられる。他方で,「指導死」は,まずはそれまでその出来事を語ることができなかった遺族たちを「救済」する役目を果たしてきたと言える。その意味では,これまでのところ「指導死」概念を必要としてきたのも第一義的には遺族たち自身であったと言えるのかもしれない。
「指導死」概念がある人びとを[救済]する意味を有してきたというここでの議論に関しては,さらに[被害者]である子どもの[救済]という点を考える必要もあるだろう。必ずしも「指導死」概念が登場することのみによって可能になるわけではないものの,そうした概念の広まりが,教師の指導のあり方をけじめとし,学校教育現場での様々なやりとりのあり方を問い直していくためのひとつの契機となりうることは明らかである。そうした社会的状況の変化はまた,子どもやその親といった「当事者」にとって,教師の「不適切な」指導やそれによる被害経験に対する訴えをより容易にするものでもあるだろう。
なお,そのような新たな概念の登場による「被害者の救済」という点に限って言えば,「いじめ」や「いじめ自殺」という概念にも,子どもやその親といった「当事者」たち匚とっての「救済」に役立ってきた側面があることも否定できない。「いじめ自殺」に関する既存研究では十分注意が向けられてこなかったが,そうした側面が[いじめ自殺]概念の「解体」(北洋2015)を困難にしている可能性には,より注意が向けられて然るべきであるだろう。そうした今日の「現実」のありようを踏まえたその上で,いかに「いじめ問題」や「いじめ」という「物語」を組み替えていけるのかが問われなければならないと思われるのだ。次章では,このような関心のもとで,「いじめ自殺」事件の遺族たちの経験を問うことを試みる。(以上)





























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます