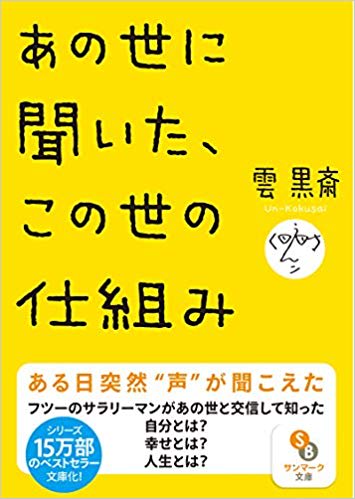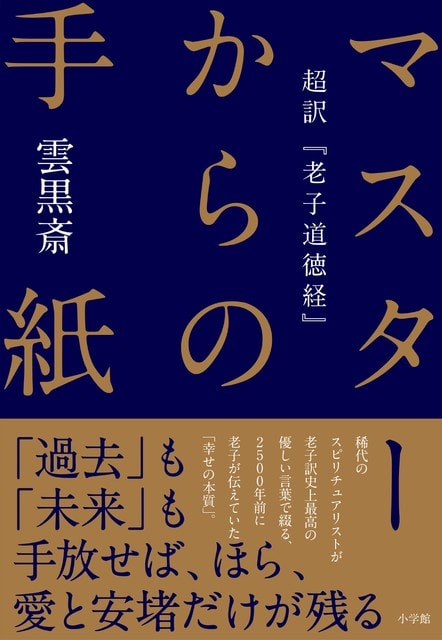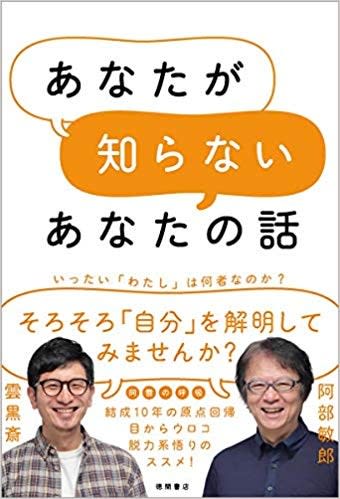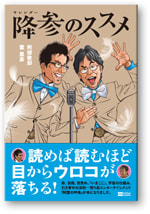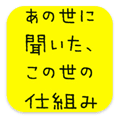2025年、gooブログのサービス終了に伴い、noteへお引越ししました。
あの世に聞いた、この世の仕組み
正思惟
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
あまり知られていない真実。
『スナフキンとミイは、異父兄弟。(しかも、ミイがお姉さんで、スナフキンが弟。)』
(出典:ムーミン公式サイト)
…
突然のトリビアと共にこんにちは。黒斎(悪いムーミン)です。
っていうか、悪いムーミンって何だ。
(話の流れが見えない方は、前エントリのコメント欄参照のこと。)
…あ、そんな事より続きですね。では。
( ̄д ̄ ) 『さて、ここまで「正見」「正念」「正定」と、とりあえず3項目を説明しましたが、この3つ、それぞれに名前をつけて説明しているため、バラバラのものに見えるかもしれませんが、密接に関わる一つの流れです。それぞれが独立しているモノではありません。』
( ゜д゜)( ゜ー゜)( ゜ゝ゜)( ゜∀゜)( ゜ω゜) ふむふむ
( ̄д ̄ ) 『(正見)当たり前の事、事実を認める勇気を持ち…(正定)落ち着き、集中し、心が統一されている状態で…(正念)メタ認知による自己観察を行う。 この一連の流れによって、ひらめきや気付きを受け入れる体制を整えます。皆さん、実際に経験されたのでわかっていただけるかと思いますが、本当に思考がクリアになっていくんです。』
(;゜ ー゜) 「そうですね。まだまだ難しいですが…」
( ̄д ̄ ) 『うん。最初は難しいかもしれませんね。でも、他の何かと同じで、繰り返すことで徐々になれていきますよ。』
(;゜ ゝ゜) 「はい。頑張ってみます。」
( ̄д ̄ ) 『頑張るといっても、また苦行のように、あんまり躍起にならないでくださいね。リラックスが大事なんですから。』
(;゜ ∀゜) 「はい…。」
( ̄д ̄ ) 『さてここで。この瞑想状態をさらに深めるために、大切となる事があります。』
( ゜ ω゜) 「なんですか?大切になる事って。」
( ̄д ̄ ) 『自分の「あり方」です。自分の行動に伴う「結果」というのは、自分の「あり方」次第で異なってしまうモノなので「やり方」ではなく、「あり方」が大切になるんです。』
(;゜ д゜) 「“あり方”ですか…」
( ̄д ̄ ) 『「悟りを得るために瞑想をする」という姿勢ではなく、「悟りを受け入れられる状態である」という、「結果にふさわしい状態に、今なっている」ということが大切なんです。八正道の残りの5項目は、この「あり方」を示すモノなんです。』
( ゜д゜)( ゜ー゜)( ゜ゝ゜)( ゜∀゜)( ゜ω゜) ふむふむ
( ̄д ̄ ) 『まずは「正思惟(しょうしゆい)」。これは、「正しい目的意識を持つ」、もっと簡単に言えば「正しい考え方を持つ」と言うことです。例え行動に起こさず「頭の中だけ」だとしても、悪いことを考えるのは止めましょう、ということです。』
( ゜ д゜) 「悪いことって、どういうことです?どんなことを“良い”とし、どんなことを“悪い”と定義すればいいのでしょう?」
( ̄д ̄ ) 『なるほど、いい質問ですね。確かに、自分にとっては良いことでも、誰かにとっては悪いことだってありますからね。ではこうしましょう。正思惟をさらに「無害心(むがいしん)」「無瞋恚(むしんい)」「無貪欲(むとんよく)」の3つに分けてみます。』
(;゜ ー゜) 「さぁ、また難しくなってきたぞ。」
( ̄д ̄ ) 『いえ、難しいのは単語だけです。この3つは単に、「誰かや何かを傷つけない」「怒らない」「欲張らない」ということです。』
(;゜ ゝ゜) 「それだけ?」
( ̄д ̄ ) 『それだけ。』
(;゜ ∀゜) 「ホントに?」
( ̄д ̄ ) 『じゃ、もう少し説明を付け加えますね。「良い」「悪い」を判断するときは、自分だけではなく、他の誰かや何か、生きとし生けるもの全てにとって良いかどうかを考えましょう。誰かを傷つけないと言うことだけに留まらず、どうすれば助けられるか、どうすれば幸せでいれるかという慈しみを持って行動することを「無害心」、自分の都合だけにこだわって誰かや何かに怒りをぶつけたり、排除しようとしたり、恨みを持ったり、また、その感情をモチベーションにしたりする事を止めることを「無瞋恚」とします。また、「怒り」は「自分の思い通りにならない」という思いに対して現れる感情です。つまり、この「怒り」という感情の裏には必ず「欲望」があるんです。勿論人間が生きていくためには色々なモノが必要になります。だからといってそれらを際限なく求める必要はありません。ですから、余計な欲はいりません。余計な欲は、余計な怒りを生むだけです。だから、欲張ることは止めましょう、というのです。これを「無貪欲」とします。』
( ゜ ω゜) 「傷つけない・怒らない・欲張らない…。ふむ。確かに“やり方”ではなく、“あり方”の問題ですね。」
( ̄д ̄ ) 『でね、よく考えてみてください。人は、何かとこれらと逆の行動に走ってしまうのですが、「傷つけない・怒らない・欲張らない」を選択して、自分が損をするという事はないんです。むしろ、「傷つける・怒る・欲張る」という行動を選択するが故に苦しみを増しているんですよ。』
 ←ねぇムーミン、ちょっと押して。(恥ずかしがらないで)
←ねぇムーミン、ちょっと押して。(恥ずかしがらないで)
********************************************
あまり知られていない真実。
『スナフキンとミイは、異父兄弟。(しかも、ミイがお姉さんで、スナフキンが弟。)』
(出典:ムーミン公式サイト)
…
突然のトリビアと共にこんにちは。黒斎(悪いムーミン)です。
っていうか、悪いムーミンって何だ。
(話の流れが見えない方は、前エントリのコメント欄参照のこと。)
…あ、そんな事より続きですね。では。
( ̄д ̄ ) 『さて、ここまで「正見」「正念」「正定」と、とりあえず3項目を説明しましたが、この3つ、それぞれに名前をつけて説明しているため、バラバラのものに見えるかもしれませんが、密接に関わる一つの流れです。それぞれが独立しているモノではありません。』
( ゜д゜)( ゜ー゜)( ゜ゝ゜)( ゜∀゜)( ゜ω゜) ふむふむ
( ̄д ̄ ) 『(正見)当たり前の事、事実を認める勇気を持ち…(正定)落ち着き、集中し、心が統一されている状態で…(正念)メタ認知による自己観察を行う。 この一連の流れによって、ひらめきや気付きを受け入れる体制を整えます。皆さん、実際に経験されたのでわかっていただけるかと思いますが、本当に思考がクリアになっていくんです。』
(;゜ ー゜) 「そうですね。まだまだ難しいですが…」
( ̄д ̄ ) 『うん。最初は難しいかもしれませんね。でも、他の何かと同じで、繰り返すことで徐々になれていきますよ。』
(;゜ ゝ゜) 「はい。頑張ってみます。」
( ̄д ̄ ) 『頑張るといっても、また苦行のように、あんまり躍起にならないでくださいね。リラックスが大事なんですから。』
(;゜ ∀゜) 「はい…。」
( ̄д ̄ ) 『さてここで。この瞑想状態をさらに深めるために、大切となる事があります。』
( ゜ ω゜) 「なんですか?大切になる事って。」
( ̄д ̄ ) 『自分の「あり方」です。自分の行動に伴う「結果」というのは、自分の「あり方」次第で異なってしまうモノなので「やり方」ではなく、「あり方」が大切になるんです。』
(;゜ д゜) 「“あり方”ですか…」
( ̄д ̄ ) 『「悟りを得るために瞑想をする」という姿勢ではなく、「悟りを受け入れられる状態である」という、「結果にふさわしい状態に、今なっている」ということが大切なんです。八正道の残りの5項目は、この「あり方」を示すモノなんです。』
( ゜д゜)( ゜ー゜)( ゜ゝ゜)( ゜∀゜)( ゜ω゜) ふむふむ
( ̄д ̄ ) 『まずは「正思惟(しょうしゆい)」。これは、「正しい目的意識を持つ」、もっと簡単に言えば「正しい考え方を持つ」と言うことです。例え行動に起こさず「頭の中だけ」だとしても、悪いことを考えるのは止めましょう、ということです。』
( ゜ д゜) 「悪いことって、どういうことです?どんなことを“良い”とし、どんなことを“悪い”と定義すればいいのでしょう?」
( ̄д ̄ ) 『なるほど、いい質問ですね。確かに、自分にとっては良いことでも、誰かにとっては悪いことだってありますからね。ではこうしましょう。正思惟をさらに「無害心(むがいしん)」「無瞋恚(むしんい)」「無貪欲(むとんよく)」の3つに分けてみます。』
(;゜ ー゜) 「さぁ、また難しくなってきたぞ。」
( ̄д ̄ ) 『いえ、難しいのは単語だけです。この3つは単に、「誰かや何かを傷つけない」「怒らない」「欲張らない」ということです。』
(;゜ ゝ゜) 「それだけ?」
( ̄д ̄ ) 『それだけ。』
(;゜ ∀゜) 「ホントに?」
( ̄д ̄ ) 『じゃ、もう少し説明を付け加えますね。「良い」「悪い」を判断するときは、自分だけではなく、他の誰かや何か、生きとし生けるもの全てにとって良いかどうかを考えましょう。誰かを傷つけないと言うことだけに留まらず、どうすれば助けられるか、どうすれば幸せでいれるかという慈しみを持って行動することを「無害心」、自分の都合だけにこだわって誰かや何かに怒りをぶつけたり、排除しようとしたり、恨みを持ったり、また、その感情をモチベーションにしたりする事を止めることを「無瞋恚」とします。また、「怒り」は「自分の思い通りにならない」という思いに対して現れる感情です。つまり、この「怒り」という感情の裏には必ず「欲望」があるんです。勿論人間が生きていくためには色々なモノが必要になります。だからといってそれらを際限なく求める必要はありません。ですから、余計な欲はいりません。余計な欲は、余計な怒りを生むだけです。だから、欲張ることは止めましょう、というのです。これを「無貪欲」とします。』
( ゜ ω゜) 「傷つけない・怒らない・欲張らない…。ふむ。確かに“やり方”ではなく、“あり方”の問題ですね。」
( ̄д ̄ ) 『でね、よく考えてみてください。人は、何かとこれらと逆の行動に走ってしまうのですが、「傷つけない・怒らない・欲張らない」を選択して、自分が損をするという事はないんです。むしろ、「傷つける・怒る・欲張る」という行動を選択するが故に苦しみを増しているんですよ。』
 ←ねぇムーミン、ちょっと押して。(恥ずかしがらないで)
←ねぇムーミン、ちょっと押して。(恥ずかしがらないで)コメント ( 15 ) | Trackback ( )
ヴィパッサナー
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
う~ん…
やっぱり伝わってないのかな…
「私が、知っているということを知っている」
「私が、感じているということを感じている」
「私は、理解していないということを理解している」
などのように、自分の置かれている状況、自分が感じていることを、外から客観的に捉える事を『メタ認知』と言い、
また、
ありのままの自分を観察することを『ヴィパッサナー』と言います。
それは、「何かをする」ということではなく、心身を「今」「ここ」に集中させ「“今ここ”に戻っている状態」のことです。
何をしていても構いません。
座禅を例に取ると、座りながら自分を観察して「今ここ」に戻る。普段忘れている、息を「吸う・吐く」などの行為をきちんと意識する。座りっぱなしで足が痛くなっても、それを痛いと思うのではなく、痛い自分を観察する。余計なことが頭に浮かんできたら、それを否定するのでも、追いかけるのでもなく、「余計なことを考えている、余計なことを考えている…」とそれだけを観察する。
というお話をさせていただき、 次いで『大切なのは、「やり方」ではなく、「あり方」』です。
と書いた傍から
「質問なのですが、ヴィパッサナー・メタ認知はどうすればできるのですか?」
と聞かれて…
僕はなんと答えれば良いのでしょう?
いえ、このコメントを残してくれた、まことさんを責めているわけではないのです。
それは多分素直な気持ちでしょうし、まことさんと同じ事を思っている方も少なからずおられるんだと思います。
ただ…。僕自身、そんなに難しい事を書いたつもりもないし、どちらかというと、かなりわかりやすく説明できているつもりでいたものですから、その反応に困惑しているんです。
まさに、「思い通りにならないことばかり」ですね。w
と、言うわけで、今日はもう少しヴィパッサナーについて書いてみたいと思います。(とはいえ、どうしてもお話する内容は、同じ事の繰り返しになってしまうのですが…)
「ヴィパッサナー」はパーリ語です。
Vi(ヴィ)が「ありのままに・客観的に」と言う意味で、Passanaa(パッサナー)が「(心の目で)観る・観察する」と言う意味です。
つまり、『今という瞬間の自分を感じる(心の目で観察する)』というニュアンス。
ですから、「ヴィパッサナー」と「メタ認知」というこの2つ、言葉は違えど、言っていることは同じです。
その言葉の意味するところは、『自分を観察する』ということです。
なんてことはない、ホントにそれだけの事なんですよ。いたってシンプルでしょ?
(だから、「どうすればできるんですか?」と聞かれても、「どうするもこうするも、自分で自分を観察してください。」としか答えようがないんです。)
では次に…
「ありのままに観る」ということは、必然的に、イコール「今を観る」ということなるのですが、これはわかってもらえますか?
過去に起こった事が、今もそのままということはありません。
物事は絶えず変化するから、1分前に起こったことを観察することもできません。
何かに記録したものを観察するのでは、「ありのまま」を観察しているとはいえませんよね?
(仮に、ビデオに撮った自分の姿を、モニターを通して観察しても、それは「ありのままの自分」を観察してるんじゃなくて、「モニターに映った自分」を観察しているに過ぎないんです。まして、撮影時の自分と、観察時の自分とでは、すでに変化しています。)
未来に何が起こるかを予測するということも、その対象を観察しているとは言えません。
「こうであって欲しい」という希望的観測を交えることも、当然「ありのまま」とは言えません。
「ありのままを観察する」ということは、「今を見る」ことでしか実現出来ないわけですよ。めっさ当たり前の話だけど。
ですから、「ありのままを観察する」ということ自体が、「今に戻る」という状態に繋がるわけです。
でね、何かを観察していると、そこに「発見」が生まれるじゃないですか。
「お湯が沸騰している」という現象を観察していれば、「あ、水は熱すると蒸発するんだ。液体から気体へ変わっていくんだ。」ということに気付けるじゃないですか。
だから、それと同じことで、「自分」という現象を観察すれば、「あ、自分ってこうなんだ。」ってことに気付けるんです。
小学校の理科で習っていたことと同じわけですよ。やってることは。
ただ、小学校では「アリ」とか「葉っぱ」とかは散々観察してるわりには、「自分」ってものを観察してないんですよ。驚くことに。
そりゃ、「皮膚や毛の様子を顕微鏡で覗いてみよう」ってな事はしてましたけど、それはあくまで「皮膚」や「毛」を観察しただけであって、「自分」を観察したことになっていないですよね。
顕微鏡を覗いて「へー!毛ってこういう構造になってるんだー!」という気付きが起こるように、アリの巣を覗くことで、その生態を知ることが出来るように、自分を観察することで、必ず「へー!自分ってこういう仕組みになってるんだー!」という発見に出会えるんです。
だから、自分を知るために、自分を発見するために、「ありのままの自分を観察する」んです。
たんに、それをしましょう、というだけのことなんですよ。
「瞑想」っていうと、どこか神様に出会うための儀式とか、何かを念じたりとか思っちゃってるとこがあるかもしれないけど、全然そんな事じゃないんです。
精神論とか、思想とか、信仰とか、そういうことじゃないんですよ。むしろ、すっげー科学的です。
ただ、科学と違うのは、観察する対象が「物質ではない」ということぐらい。
顕微鏡で覗くことのできない、「心」や「心と体の繋がり」を観察するんです。
とにもかくにも、「偏見や思い込みに囚われることなく、注意深く観察する」というだけの話ですから、「テクニック」とか「コツ」とか、そういう事じゃないんです。
「ありのままに観る」というスタンス(あり方)があればいいだけ。
わかりますか?
「今の自分を観察する」=「今という瞬間を意識する」=「今、ここにいる自分に気付いていく」なんです。
自分の動作、行動、感情、それらに気付いているかどうか、それだけの話なんです。
それだけの話なのですが、実際にやってみればわかります。
不思議と、自分を観察するのは難しいです。
自分で自分を観察しようと思っている時に、「自我」が、自分を観察することを邪魔しに来るんです。
そこで初めて、「自分」と「自我」の違いが見えてくると思います。
ってとこでどうでしょう?
伝わってる?
 ←なんらかのレスポンスをいただけると嬉しいです。
←なんらかのレスポンスをいただけると嬉しいです。
********************************************
う~ん…
やっぱり伝わってないのかな…
「私が、知っているということを知っている」
「私が、感じているということを感じている」
「私は、理解していないということを理解している」
などのように、自分の置かれている状況、自分が感じていることを、外から客観的に捉える事を『メタ認知』と言い、
また、
ありのままの自分を観察することを『ヴィパッサナー』と言います。
それは、「何かをする」ということではなく、心身を「今」「ここ」に集中させ「“今ここ”に戻っている状態」のことです。
何をしていても構いません。
座禅を例に取ると、座りながら自分を観察して「今ここ」に戻る。普段忘れている、息を「吸う・吐く」などの行為をきちんと意識する。座りっぱなしで足が痛くなっても、それを痛いと思うのではなく、痛い自分を観察する。余計なことが頭に浮かんできたら、それを否定するのでも、追いかけるのでもなく、「余計なことを考えている、余計なことを考えている…」とそれだけを観察する。
というお話をさせていただき、 次いで『大切なのは、「やり方」ではなく、「あり方」』です。
と書いた傍から
「質問なのですが、ヴィパッサナー・メタ認知はどうすればできるのですか?」
と聞かれて…
僕はなんと答えれば良いのでしょう?
いえ、このコメントを残してくれた、まことさんを責めているわけではないのです。
それは多分素直な気持ちでしょうし、まことさんと同じ事を思っている方も少なからずおられるんだと思います。
ただ…。僕自身、そんなに難しい事を書いたつもりもないし、どちらかというと、かなりわかりやすく説明できているつもりでいたものですから、その反応に困惑しているんです。
まさに、「思い通りにならないことばかり」ですね。w
と、言うわけで、今日はもう少しヴィパッサナーについて書いてみたいと思います。(とはいえ、どうしてもお話する内容は、同じ事の繰り返しになってしまうのですが…)
「ヴィパッサナー」はパーリ語です。
Vi(ヴィ)が「ありのままに・客観的に」と言う意味で、Passanaa(パッサナー)が「(心の目で)観る・観察する」と言う意味です。
つまり、『今という瞬間の自分を感じる(心の目で観察する)』というニュアンス。
ですから、「ヴィパッサナー」と「メタ認知」というこの2つ、言葉は違えど、言っていることは同じです。
その言葉の意味するところは、『自分を観察する』ということです。
なんてことはない、ホントにそれだけの事なんですよ。いたってシンプルでしょ?
(だから、「どうすればできるんですか?」と聞かれても、「どうするもこうするも、自分で自分を観察してください。」としか答えようがないんです。)
では次に…
「ありのままに観る」ということは、必然的に、イコール「今を観る」ということなるのですが、これはわかってもらえますか?
過去に起こった事が、今もそのままということはありません。
物事は絶えず変化するから、1分前に起こったことを観察することもできません。
何かに記録したものを観察するのでは、「ありのまま」を観察しているとはいえませんよね?
(仮に、ビデオに撮った自分の姿を、モニターを通して観察しても、それは「ありのままの自分」を観察してるんじゃなくて、「モニターに映った自分」を観察しているに過ぎないんです。まして、撮影時の自分と、観察時の自分とでは、すでに変化しています。)
未来に何が起こるかを予測するということも、その対象を観察しているとは言えません。
「こうであって欲しい」という希望的観測を交えることも、当然「ありのまま」とは言えません。
「ありのままを観察する」ということは、「今を見る」ことでしか実現出来ないわけですよ。めっさ当たり前の話だけど。
ですから、「ありのままを観察する」ということ自体が、「今に戻る」という状態に繋がるわけです。
でね、何かを観察していると、そこに「発見」が生まれるじゃないですか。
「お湯が沸騰している」という現象を観察していれば、「あ、水は熱すると蒸発するんだ。液体から気体へ変わっていくんだ。」ということに気付けるじゃないですか。
だから、それと同じことで、「自分」という現象を観察すれば、「あ、自分ってこうなんだ。」ってことに気付けるんです。
小学校の理科で習っていたことと同じわけですよ。やってることは。
ただ、小学校では「アリ」とか「葉っぱ」とかは散々観察してるわりには、「自分」ってものを観察してないんですよ。驚くことに。
そりゃ、「皮膚や毛の様子を顕微鏡で覗いてみよう」ってな事はしてましたけど、それはあくまで「皮膚」や「毛」を観察しただけであって、「自分」を観察したことになっていないですよね。
顕微鏡を覗いて「へー!毛ってこういう構造になってるんだー!」という気付きが起こるように、アリの巣を覗くことで、その生態を知ることが出来るように、自分を観察することで、必ず「へー!自分ってこういう仕組みになってるんだー!」という発見に出会えるんです。
だから、自分を知るために、自分を発見するために、「ありのままの自分を観察する」んです。
たんに、それをしましょう、というだけのことなんですよ。
「瞑想」っていうと、どこか神様に出会うための儀式とか、何かを念じたりとか思っちゃってるとこがあるかもしれないけど、全然そんな事じゃないんです。
精神論とか、思想とか、信仰とか、そういうことじゃないんですよ。むしろ、すっげー科学的です。
ただ、科学と違うのは、観察する対象が「物質ではない」ということぐらい。
顕微鏡で覗くことのできない、「心」や「心と体の繋がり」を観察するんです。
とにもかくにも、「偏見や思い込みに囚われることなく、注意深く観察する」というだけの話ですから、「テクニック」とか「コツ」とか、そういう事じゃないんです。
「ありのままに観る」というスタンス(あり方)があればいいだけ。
わかりますか?
「今の自分を観察する」=「今という瞬間を意識する」=「今、ここにいる自分に気付いていく」なんです。
自分の動作、行動、感情、それらに気付いているかどうか、それだけの話なんです。
それだけの話なのですが、実際にやってみればわかります。
不思議と、自分を観察するのは難しいです。
自分で自分を観察しようと思っている時に、「自我」が、自分を観察することを邪魔しに来るんです。
そこで初めて、「自分」と「自我」の違いが見えてくると思います。
ってとこでどうでしょう?
伝わってる?
 ←なんらかのレスポンスをいただけると嬉しいです。
←なんらかのレスポンスをいただけると嬉しいです。コメント ( 40 ) | Trackback ( )
あり方
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
ヴィパッサナー、メタ認知を繰り返していると、必然的に色々なことに気付き出します。
脳がひらめきや気付きを受け入れやすくなっている状態で自分自身を観察しているから、自ずと、自分や自分を取り巻く環境の構造が理解出来ていくんです。
その時、何を発見するのかは、実際にやってみればわかると思うので(それは、あくまで個人的な内的体験ですので)ここであまり深くは語りません。
しかしながら、今後話を続けるにあたり、是非ともこれには気付いて欲しいなぁという点を書いておきたいと思います。
それは、お釈迦様にしろ、イエス・キリストにしろ、彼らが語っていた内容は、人間の「あり方」であって、決して幸せになる「やり方」ではない、ということ。
現在紹介中の「八正道」や、各宗教の「戒律」等、一見「マニュアル」や「How to」とも見えてしまいそうな事ですら、「こうすれば幸せになれる」、「これをすれば苦しみから逃れられる」などと、『方法論』を語ったものではないんです。
そこで説いているのは、あくまで『存在論』なんです。
大切なのは、「人として、何をするか(Do)」ではなく、「人として、どうあるか(Be)」。
これまでの歴史で、色々な宗教が歪んできたのは、この「Do」と「Be」の取り違いが原因だと思います。
人は、目の前に苦悩や不満が現れたとき、ついつい「どうすればこの現状から逃れられるか」と、その「やり方」「方法」を模索してしまいがちです。
僕もかつてそうでした。「その苦悩とどう向き合うか」という、自分の「あり方」などは考えず、その苦悩から目を反らすことの出来る依存先や逃げ道を探すことに、必死で努力していました。
しかしながら、「苦悩」や「不満」といったこれらの事は、「状況・環境」の問題ではなく、その状況・環境を、「どう捉えているか」という心の問題が本質であるため、『方法論』や『物質・環境』では解決できないんです。
大切なのは、自分が「どうあれば」苦悩や不満を解消できるか、なんです。
『やり方を求める』という生き方は、宗教・精神世界だけに留まらず、人生全般において次々と問題を起こしてしまいます。
その典型が『マニュアル化』による弊害です。
「こういう時は、こうしましょう。」「そういう時は、そうしましょう。」そういった『How to』によって、人はどんどん『どうあるべきか』ということを忘れていきます。
そして、想定外の問題にぶつかった時、それをどう対処したらいいのか、自分で判断することが出来なくなってしまいます。
その結果、「Aの問題に当たった時は、こう対処する。Bの問題に当たった時は、こう対処する。Cの問題に当たった時は…」と、その『答え』ばかりを頭に詰め込む。
でも、残念なことに「人生は思い通りにならないことばかり(四苦八苦)」というのが真理です。
ですから、想定外の問題は、生きているかぎり、無限に現れるんです。
どんなに「やり方」を数多く詰め込んでも、追いつくことはできません。
ありとあらゆる方法を駆使しても苦から逃れられず、行き着く果ては絶望です。
しかし、『あり方』に気付いた人は違います。
つねに「自分がどうあるか」を持っているので、物事の判断を自分で行えるんです。
想定外の問題に当たっても、柔軟に対応できる。「今」を見て判断するから、事例もHow toもいらないんです。
育児につまずいた時、「育児書」(やり方)に依存している方は、その中に書かれていない問題の対処に困ってしまいます。
そして、「使い物にならない育児書だわ!」と、そこに怒りをぶつけてみたり。
でも、「母としてどうあるか」を持っている方は、育児書に向かわず、子供に向かいます。
問題は育児書にあるのではなく、目の前にあるのですから。
「どうあるか」があれば、「どうするか」は自ずと見えるんです。
「Be」があるから「Do」を行える。
何かをした(Do)から、自分のあり方(Be)が変わったのではないんです。
順序は必ず「Be→Do」なんです。「Do→Be」ではありません。
ヴィパッサナー、メタ認知を行ってみてください。この意味がハッキリわかると思います。
「何をするか」は問題ではありません。「どうあるか」が問題なんです。
このこと、とても大切なので、もう一つ別な視点からお話します。
「何をするか」は問題ではありません。
なぜなら、同じ事をしても、自分の「あり方」の違いで結果が異なってしまうからです。
身近な例を挙げてみましょう。
ある日買い物に出掛けました。その、お会計時。
いきいきと、楽しんで仕事をしている店員さんから商品を受け取ると、なんだかこちらも嬉しい気分になります。
嫌々仕事をしている店員さんから商品を受け取ると、なぜだかイラッとします。
店員さんは「レジを打つ」という同じ事をしているにも関わらず、その「あり方」によってお客様に与える結果が異なってしまいます。
ね。「やり方」ではなく、「あり方」の問題なんです。
…
お盆休み真っ只中。
お時間がある方は、是非「やり方」と「あり方」の違いを明確にしつつ、ヴィパッサナー、メタ認知をお試しいただければと思います。
 ←「あり方」を意識しつつポチッと。
←「あり方」を意識しつつポチッと。
********************************************
ヴィパッサナー、メタ認知を繰り返していると、必然的に色々なことに気付き出します。
脳がひらめきや気付きを受け入れやすくなっている状態で自分自身を観察しているから、自ずと、自分や自分を取り巻く環境の構造が理解出来ていくんです。
その時、何を発見するのかは、実際にやってみればわかると思うので(それは、あくまで個人的な内的体験ですので)ここであまり深くは語りません。
しかしながら、今後話を続けるにあたり、是非ともこれには気付いて欲しいなぁという点を書いておきたいと思います。
それは、お釈迦様にしろ、イエス・キリストにしろ、彼らが語っていた内容は、人間の「あり方」であって、決して幸せになる「やり方」ではない、ということ。
現在紹介中の「八正道」や、各宗教の「戒律」等、一見「マニュアル」や「How to」とも見えてしまいそうな事ですら、「こうすれば幸せになれる」、「これをすれば苦しみから逃れられる」などと、『方法論』を語ったものではないんです。
そこで説いているのは、あくまで『存在論』なんです。
大切なのは、「人として、何をするか(Do)」ではなく、「人として、どうあるか(Be)」。
これまでの歴史で、色々な宗教が歪んできたのは、この「Do」と「Be」の取り違いが原因だと思います。
人は、目の前に苦悩や不満が現れたとき、ついつい「どうすればこの現状から逃れられるか」と、その「やり方」「方法」を模索してしまいがちです。
僕もかつてそうでした。「その苦悩とどう向き合うか」という、自分の「あり方」などは考えず、その苦悩から目を反らすことの出来る依存先や逃げ道を探すことに、必死で努力していました。
しかしながら、「苦悩」や「不満」といったこれらの事は、「状況・環境」の問題ではなく、その状況・環境を、「どう捉えているか」という心の問題が本質であるため、『方法論』や『物質・環境』では解決できないんです。
大切なのは、自分が「どうあれば」苦悩や不満を解消できるか、なんです。
『やり方を求める』という生き方は、宗教・精神世界だけに留まらず、人生全般において次々と問題を起こしてしまいます。
その典型が『マニュアル化』による弊害です。
「こういう時は、こうしましょう。」「そういう時は、そうしましょう。」そういった『How to』によって、人はどんどん『どうあるべきか』ということを忘れていきます。
そして、想定外の問題にぶつかった時、それをどう対処したらいいのか、自分で判断することが出来なくなってしまいます。
その結果、「Aの問題に当たった時は、こう対処する。Bの問題に当たった時は、こう対処する。Cの問題に当たった時は…」と、その『答え』ばかりを頭に詰め込む。
でも、残念なことに「人生は思い通りにならないことばかり(四苦八苦)」というのが真理です。
ですから、想定外の問題は、生きているかぎり、無限に現れるんです。
どんなに「やり方」を数多く詰め込んでも、追いつくことはできません。
ありとあらゆる方法を駆使しても苦から逃れられず、行き着く果ては絶望です。
しかし、『あり方』に気付いた人は違います。
つねに「自分がどうあるか」を持っているので、物事の判断を自分で行えるんです。
想定外の問題に当たっても、柔軟に対応できる。「今」を見て判断するから、事例もHow toもいらないんです。
育児につまずいた時、「育児書」(やり方)に依存している方は、その中に書かれていない問題の対処に困ってしまいます。
そして、「使い物にならない育児書だわ!」と、そこに怒りをぶつけてみたり。
でも、「母としてどうあるか」を持っている方は、育児書に向かわず、子供に向かいます。
問題は育児書にあるのではなく、目の前にあるのですから。
「どうあるか」があれば、「どうするか」は自ずと見えるんです。
「Be」があるから「Do」を行える。
何かをした(Do)から、自分のあり方(Be)が変わったのではないんです。
順序は必ず「Be→Do」なんです。「Do→Be」ではありません。
ヴィパッサナー、メタ認知を行ってみてください。この意味がハッキリわかると思います。
「何をするか」は問題ではありません。「どうあるか」が問題なんです。
このこと、とても大切なので、もう一つ別な視点からお話します。
「何をするか」は問題ではありません。
なぜなら、同じ事をしても、自分の「あり方」の違いで結果が異なってしまうからです。
身近な例を挙げてみましょう。
ある日買い物に出掛けました。その、お会計時。
いきいきと、楽しんで仕事をしている店員さんから商品を受け取ると、なんだかこちらも嬉しい気分になります。
嫌々仕事をしている店員さんから商品を受け取ると、なぜだかイラッとします。
店員さんは「レジを打つ」という同じ事をしているにも関わらず、その「あり方」によってお客様に与える結果が異なってしまいます。
ね。「やり方」ではなく、「あり方」の問題なんです。
…
お盆休み真っ只中。
お時間がある方は、是非「やり方」と「あり方」の違いを明確にしつつ、ヴィパッサナー、メタ認知をお試しいただければと思います。
 ←「あり方」を意識しつつポチッと。
←「あり方」を意識しつつポチッと。コメント ( 16 ) | Trackback ( )
ノンストップ
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
さて。
それでは今度は、「正念」「正定」を行っている時、人間の脳がどのような活動状態になっているのかを、脳科学の見地から確認してみましょう。
人間の脳は、心臓と同様に、一生を通じてノンストップでフル活動しています。
「脳の90%は使われていない」という事を聞いたことがあるかとは思いますが、これ、まったくの嘘なんだそうです。
嘘というよりは勘違いと言った方が正確かな。脳科学の発展途上段階で、その働きを計測する術(すべ)を持っていなかっただけなんだそうです。
本当は活動しているにも関わらず、その活動内容が地味だったものだから、「測定出来ない=眠っている(使われていない)」という間違った解釈になっていたんですって。
そういうワケで、脳は常時100%フル活動しています。
つまり、どんな状況においても、何かしら活動し続けようとするのが、脳なんです。
ですから、瞑想しようとしているのにも関わらず、次々と余計な事が思い浮かんでしまうのも、当たり前と言えば当たり前の話なんですね。
でも、この脳の機能を逆手にとってやることで、ひらめきや気付きを促す事が出来るんだそうです。
結論からいうと、脳に「空白」を作ることが、ひらめきを生むために効果的となります。
もう少し表現を変えると、脳にひらめきや気付きを起こさせるための「余裕」を与えてあげる、ということ。
脳は常時いろいろな仕事・作業をしています。
その作業内容は、生命を維持するために必要な重大なものから、どうでもいい妄想など多岐にわたります。
逆にいうと、100%の容量を使い切るために、何かしらどうでもいい事を考えてしまっているんですね。
その、「どうでもいいことを考えている領域」の活動を意図的に停止させ、脳が自由に活動できる領域をつくってあげると、今度は脳が勝手にその領域を何かで埋めようとする。その「空白」に、ひらめきを意図的に誘導するんです。
では、その空白を作り出す為に必要なものは何か。
そのキーワードが、「リラックス」と「退屈」です。
瞑想はある意味で、脳に「リラックス」と「退屈」を与えてあげるための手段とも言えるかもしれません。
常時落ち着き無く活動し続ける、じゃじゃ馬状態の脳をなだめ、ゆったりとリラックスさせ、そこに単調な思考の繰り返し(メタ認知・呼吸への集中など)で、思考の暴走抑制を行い、ひらめき・気付きを受け入れるための「余裕」を作るんです。
脳に、どうでもいいことを考えることを止めさせて、その分のパワーを「アハ!体験」を促す方向へシフトする。
そう考えると、「正念」「正定」の目指しているモノがわかりやすくなると思うんだけど…
どう?
 ←どうでもいいことは考えずに、その分のパワーでポチッと。
←どうでもいいことは考えずに、その分のパワーでポチッと。
********************************************
さて。
それでは今度は、「正念」「正定」を行っている時、人間の脳がどのような活動状態になっているのかを、脳科学の見地から確認してみましょう。
人間の脳は、心臓と同様に、一生を通じてノンストップでフル活動しています。
「脳の90%は使われていない」という事を聞いたことがあるかとは思いますが、これ、まったくの嘘なんだそうです。
嘘というよりは勘違いと言った方が正確かな。脳科学の発展途上段階で、その働きを計測する術(すべ)を持っていなかっただけなんだそうです。
本当は活動しているにも関わらず、その活動内容が地味だったものだから、「測定出来ない=眠っている(使われていない)」という間違った解釈になっていたんですって。
そういうワケで、脳は常時100%フル活動しています。
つまり、どんな状況においても、何かしら活動し続けようとするのが、脳なんです。
ですから、瞑想しようとしているのにも関わらず、次々と余計な事が思い浮かんでしまうのも、当たり前と言えば当たり前の話なんですね。
でも、この脳の機能を逆手にとってやることで、ひらめきや気付きを促す事が出来るんだそうです。
結論からいうと、脳に「空白」を作ることが、ひらめきを生むために効果的となります。
もう少し表現を変えると、脳にひらめきや気付きを起こさせるための「余裕」を与えてあげる、ということ。
脳は常時いろいろな仕事・作業をしています。
その作業内容は、生命を維持するために必要な重大なものから、どうでもいい妄想など多岐にわたります。
逆にいうと、100%の容量を使い切るために、何かしらどうでもいい事を考えてしまっているんですね。
その、「どうでもいいことを考えている領域」の活動を意図的に停止させ、脳が自由に活動できる領域をつくってあげると、今度は脳が勝手にその領域を何かで埋めようとする。その「空白」に、ひらめきを意図的に誘導するんです。
では、その空白を作り出す為に必要なものは何か。
そのキーワードが、「リラックス」と「退屈」です。
瞑想はある意味で、脳に「リラックス」と「退屈」を与えてあげるための手段とも言えるかもしれません。
常時落ち着き無く活動し続ける、じゃじゃ馬状態の脳をなだめ、ゆったりとリラックスさせ、そこに単調な思考の繰り返し(メタ認知・呼吸への集中など)で、思考の暴走抑制を行い、ひらめき・気付きを受け入れるための「余裕」を作るんです。
脳に、どうでもいいことを考えることを止めさせて、その分のパワーを「アハ!体験」を促す方向へシフトする。
そう考えると、「正念」「正定」の目指しているモノがわかりやすくなると思うんだけど…
どう?
 ←どうでもいいことは考えずに、その分のパワーでポチッと。
←どうでもいいことは考えずに、その分のパワーでポチッと。コメント ( 10 ) | Trackback ( )
正定
※初めての方はこちら「プロローグ」、「このblogの趣旨」からお読みください。
********************************************
λλλλ........ 「右足を上げる、前に出す、下ろす、左足を上げる、前に出す、下ろす…」
(゜д ゜;) 「みんな、なにしてんの?」
( ゜ ー゜) 「あ、リーダー。」
( ゜ ゝ゜) 「今ね、さっきブッダから教わった瞑想をしてたんです。」
(゜д ゜;) 「瞑想?…っていうか、なんかブツブツ言いながら歩いてたよね。瞑想って、座ってやるもんなんじゃないの?」
( ゜ ∀゜) 「そういう事じゃないみたいですよ。」
( ゜ ω゜) 「これ、ヴィパッサナーって言うんですって。」
(゜д ゜;) 「ヴィパッサナー?なにそれ?」
( ̄д ̄ ) 『「ヴィパッサナー」は「観察」という意味です。ありのままの自分を観察する精神統一法です。』
Σ(゜д ゜≡;゜ д゜) 「あ!ブッダ。」
( ̄д ̄ ) 『瞑想ってのは、ただ黙って座ってりゃいいって事じゃないんですよ。「今ここ」に戻っている「状態」のことなんです。』
(;゜ д゜) 「状態…ですか?」
( ̄д ̄ ) 『先ほど皆さんに、「瞑想って、どうやればいいんですか?」って聞かれたものですから、「瞑想は“すること(Do)”じゃなくて、“あること(Be)”なんです。」とお話したんです。「状態」、つまり、自分の「ありよう」のことですから、本当は何をしていてもいいんです。「瞑想」という「状態」になっていれば、座ってようが歩いてようが、仕事をしてようが、家事をしてようが、何をしていても構いません。』
(;゜ д゜) 「“今ここ”に戻っている状態って、どういうことです?」
( ̄д ̄ ) 『どういうことって…そのままの意味ですよ。心身を「今」「ここ」に集中させるんです。実際にやってみるとわかります。人間は通常、意識していない状態では、「今」からも「ここ」からも離れてしまいます。』
(;゜ д゜) 「まさか~。」
( ̄д ̄ ) 『いえ、ホントですとも。じゃ、ちょっとそこに座って「今」「ここ」を感じてみてください。』
(;- д-) 「………。あれ?」
( ̄д ̄ ) 『どうしました?』
(;- д-) 「あれ? ホント…難しいもんですね…。意識が色んな所に飛んじゃいます。“今ここ”とは関係のない、余計な事が、次から次から頭に浮かんでしまいますね…。」
( ̄д ̄ ) 『でそ。』
(;- д-) 「考えるな・考えるな・考えるな・考えるな・考えるな…」
( ̄д ̄ ) 『何してるの?』
(;- д-) 「いえ、色々と余計なことが思い浮かぶので、考えないようにと…」
( ̄д ̄ ) 『そういう自分を否定して、無理に抑えこもうとしたら、もうそれだけで「今の自分」の認識じゃなくなっちゃうじゃない。』
Σ(;- д-) 「あ、そうか…。じゃ、どうすれば…」
( ̄д ̄ ) 『うん。だから「自己観察」で「認知を認知(メタ認知)」するんです。』
(;゜ д゜) 「さっきアッサジ達がしていたのは、それですか。」
( ̄д ̄ ) 『そうそう。歩いている自分を自分で観察するんです。座禅でも同じですよ。座りながら、自分を観察して「今ここ」に戻るんです。息を「吸う・吐く」という行為すら普段の自分は忘れています。それをきちんと意識する。座りっぱなしで足が痛くなっても、それを痛いと思うのではなく、痛い自分を観察するんです。余計なことが頭に浮かんできたら、それを否定するのでも、追いかけるのでもなく、「余計なことを考えている、余計なことを考えている…」とそれだけを観察するんです。その観察(メタ認知)が、自然と精神統一に繋がって、徐々に心に落ち着きが生まれてきます。』
( - д-) 「…」
( - д-) 「……」
( - д-) 「………」
( - д-)zzzZZZZ
( ̄д ̄ ) 『寝ちゃダメです。』
Σ(;゜ д゜)ハッ!
…
こうして、常に心を統一しておくことを「正定(しょうじょう)」と言います。
心が錯乱している状態ではなく、落ち着き、集中していて、統一されている状態のことです。
簡単にゆったりと座り、心を穏やかにするよう心掛けてみてください。
(きっと、自分の心の落ち着きのなさを、まざまざと思い知らされます。)
 ←「今」「ここ」を押してください。
←「今」「ここ」を押してください。
********************************************
λλλλ........ 「右足を上げる、前に出す、下ろす、左足を上げる、前に出す、下ろす…」
(゜д ゜;) 「みんな、なにしてんの?」
( ゜ ー゜) 「あ、リーダー。」
( ゜ ゝ゜) 「今ね、さっきブッダから教わった瞑想をしてたんです。」
(゜д ゜;) 「瞑想?…っていうか、なんかブツブツ言いながら歩いてたよね。瞑想って、座ってやるもんなんじゃないの?」
( ゜ ∀゜) 「そういう事じゃないみたいですよ。」
( ゜ ω゜) 「これ、ヴィパッサナーって言うんですって。」
(゜д ゜;) 「ヴィパッサナー?なにそれ?」
( ̄д ̄ ) 『「ヴィパッサナー」は「観察」という意味です。ありのままの自分を観察する精神統一法です。』
Σ(゜д ゜≡;゜ д゜) 「あ!ブッダ。」
( ̄д ̄ ) 『瞑想ってのは、ただ黙って座ってりゃいいって事じゃないんですよ。「今ここ」に戻っている「状態」のことなんです。』
(;゜ д゜) 「状態…ですか?」
( ̄д ̄ ) 『先ほど皆さんに、「瞑想って、どうやればいいんですか?」って聞かれたものですから、「瞑想は“すること(Do)”じゃなくて、“あること(Be)”なんです。」とお話したんです。「状態」、つまり、自分の「ありよう」のことですから、本当は何をしていてもいいんです。「瞑想」という「状態」になっていれば、座ってようが歩いてようが、仕事をしてようが、家事をしてようが、何をしていても構いません。』
(;゜ д゜) 「“今ここ”に戻っている状態って、どういうことです?」
( ̄д ̄ ) 『どういうことって…そのままの意味ですよ。心身を「今」「ここ」に集中させるんです。実際にやってみるとわかります。人間は通常、意識していない状態では、「今」からも「ここ」からも離れてしまいます。』
(;゜ д゜) 「まさか~。」
( ̄д ̄ ) 『いえ、ホントですとも。じゃ、ちょっとそこに座って「今」「ここ」を感じてみてください。』
(;- д-) 「………。あれ?」
( ̄д ̄ ) 『どうしました?』
(;- д-) 「あれ? ホント…難しいもんですね…。意識が色んな所に飛んじゃいます。“今ここ”とは関係のない、余計な事が、次から次から頭に浮かんでしまいますね…。」
( ̄д ̄ ) 『でそ。』
(;- д-) 「考えるな・考えるな・考えるな・考えるな・考えるな…」
( ̄д ̄ ) 『何してるの?』
(;- д-) 「いえ、色々と余計なことが思い浮かぶので、考えないようにと…」
( ̄д ̄ ) 『そういう自分を否定して、無理に抑えこもうとしたら、もうそれだけで「今の自分」の認識じゃなくなっちゃうじゃない。』
Σ(;- д-) 「あ、そうか…。じゃ、どうすれば…」
( ̄д ̄ ) 『うん。だから「自己観察」で「認知を認知(メタ認知)」するんです。』
(;゜ д゜) 「さっきアッサジ達がしていたのは、それですか。」
( ̄д ̄ ) 『そうそう。歩いている自分を自分で観察するんです。座禅でも同じですよ。座りながら、自分を観察して「今ここ」に戻るんです。息を「吸う・吐く」という行為すら普段の自分は忘れています。それをきちんと意識する。座りっぱなしで足が痛くなっても、それを痛いと思うのではなく、痛い自分を観察するんです。余計なことが頭に浮かんできたら、それを否定するのでも、追いかけるのでもなく、「余計なことを考えている、余計なことを考えている…」とそれだけを観察するんです。その観察(メタ認知)が、自然と精神統一に繋がって、徐々に心に落ち着きが生まれてきます。』
( - д-) 「…」
( - д-) 「……」
( - д-) 「………」
( - д-)zzzZZZZ
( ̄д ̄ ) 『寝ちゃダメです。』
Σ(;゜ д゜)ハッ!
…
こうして、常に心を統一しておくことを「正定(しょうじょう)」と言います。
心が錯乱している状態ではなく、落ち着き、集中していて、統一されている状態のことです。
簡単にゆったりと座り、心を穏やかにするよう心掛けてみてください。
(きっと、自分の心の落ち着きのなさを、まざまざと思い知らされます。)
 ←「今」「ここ」を押してください。
←「今」「ここ」を押してください。コメント ( 6 ) | Trackback ( )
| « 前ページ | 次ページ » |