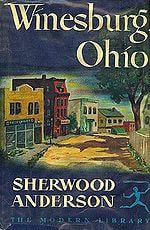SISTER CARRIE 


1900年 セオドア・ドライサー
おもしろかったですよ
田舎から都会へやってきた若い女性の、ありがちなサクセスストーリーともいえるし
浅はかなことをしでかした中年男性の転落という、よくある話ともいえます。
キャリーは憧れを胸に、大都会シカゴの姉夫婦の家に身を寄せた18歳の女性ですが
抱いていた理想と現実のギャップに戸惑い、とうとう田舎に帰されそうになります。
それで、上京する汽車で出会った羽振りのいいドルーエという男性と再会すると
誘われるままに同棲し、少し不満を覚えたところへドルーエの知人のハーストウッドという
40歳手前の高級酒場の支配人が現れると、みるみる間になびいてしまいました。
いきなり慎重さを欠いたハーストウッドの浮気は妻に知れて離婚訴訟をおこされます。
しかもキャリーにも家庭持ちだということがバレて別れを告げられふんだりけったり
ふとしたことから店の大金を持ち出したハーストウッドはキャリーを嘘で連れ出して
ニューヨークへ逃げ出すのですが、キャリーも結局承諾してしまいます。
ここから紆余曲折の末、キャリーは劇団の女優になって人生の坂を上り始めて
ハーストウッドはあれよあれよと転がり落ちていくのですけど…
キャリーはというと、帝政期に描かれた娼婦のようなタイプの女性ではなくて
流されるまま次々と男性と不適切な暮らしをしてしまって、生活のために女優になったら
人気が出て…という感じでして、サクセスストーリーの主人公にしては
ガッツが感じられないのよね。
じゃあ男を手玉にとった女が落ちぶれて散々な結末を迎えるのか、というとそうではなくて
なんだかキャリーはこの先堅実に生きて行きそうよ
ハーストウッドは、湯水のように女につぎ込んだ末の破滅ではなくて
失職して、事業失敗して、就職難で仕事無くて、というタイミングの不幸さが招いた
成れの果て、という感がありまして「ほ~ら、ごらんなさい」というのも可哀想かな、と…
そりゃキャリーに目がくらんだばっかりにバカな考えをおこしたからなんだけどね。
キャリーとハーストウッド、ふたりの行く末はあまりにもアンバランスなんじゃないかと
思ったりもしますが、その対比がおもしろいのかもしれませんね。
やはり貴族社会のないアメリカ、ロックフェラー家とかヴァンダービルト家みたいに
貴族より金持ちな家はあったでしょうが、同じような内容のフランス小説に比べたら
ゴージャスの焦点が定まっていないという嫌いはあるような気がします。
それともゴージャスのレベルが低いというのかしら?
“ 都会派小説のはしり ” と言われているということで、中流階級の増加にともなう
小市民的なゴージャスの蔓延を反映していると考えればよいのでしょうか?
まずは上巻から…



1900年 セオドア・ドライサー
おもしろかったですよ

田舎から都会へやってきた若い女性の、ありがちなサクセスストーリーともいえるし
浅はかなことをしでかした中年男性の転落という、よくある話ともいえます。
キャリーは憧れを胸に、大都会シカゴの姉夫婦の家に身を寄せた18歳の女性ですが
抱いていた理想と現実のギャップに戸惑い、とうとう田舎に帰されそうになります。
それで、上京する汽車で出会った羽振りのいいドルーエという男性と再会すると
誘われるままに同棲し、少し不満を覚えたところへドルーエの知人のハーストウッドという
40歳手前の高級酒場の支配人が現れると、みるみる間になびいてしまいました。
いきなり慎重さを欠いたハーストウッドの浮気は妻に知れて離婚訴訟をおこされます。
しかもキャリーにも家庭持ちだということがバレて別れを告げられふんだりけったり

ふとしたことから店の大金を持ち出したハーストウッドはキャリーを嘘で連れ出して
ニューヨークへ逃げ出すのですが、キャリーも結局承諾してしまいます。
ここから紆余曲折の末、キャリーは劇団の女優になって人生の坂を上り始めて
ハーストウッドはあれよあれよと転がり落ちていくのですけど…
キャリーはというと、帝政期に描かれた娼婦のようなタイプの女性ではなくて
流されるまま次々と男性と不適切な暮らしをしてしまって、生活のために女優になったら
人気が出て…という感じでして、サクセスストーリーの主人公にしては
ガッツが感じられないのよね。
じゃあ男を手玉にとった女が落ちぶれて散々な結末を迎えるのか、というとそうではなくて
なんだかキャリーはこの先堅実に生きて行きそうよ

ハーストウッドは、湯水のように女につぎ込んだ末の破滅ではなくて
失職して、事業失敗して、就職難で仕事無くて、というタイミングの不幸さが招いた
成れの果て、という感がありまして「ほ~ら、ごらんなさい」というのも可哀想かな、と…
そりゃキャリーに目がくらんだばっかりにバカな考えをおこしたからなんだけどね。
キャリーとハーストウッド、ふたりの行く末はあまりにもアンバランスなんじゃないかと
思ったりもしますが、その対比がおもしろいのかもしれませんね。
やはり貴族社会のないアメリカ、ロックフェラー家とかヴァンダービルト家みたいに
貴族より金持ちな家はあったでしょうが、同じような内容のフランス小説に比べたら
ゴージャスの焦点が定まっていないという嫌いはあるような気がします。
それともゴージャスのレベルが低いというのかしら?
“ 都会派小説のはしり ” と言われているということで、中流階級の増加にともなう
小市民的なゴージャスの蔓延を反映していると考えればよいのでしょうか?
 | シスター・キャリー〈上〉岩波書店 このアイテムの詳細を見る |
まずは上巻から…

















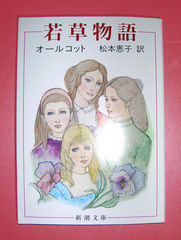












 余談2です
余談2です
 」とか言って出ていってもらいます、きっと。
」とか言って出ていってもらいます、きっと。

 そりゃそうだろうけど…
そりゃそうだろうけど…





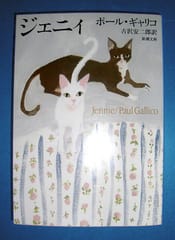
 愛あり、冒険あり、人情ありの素晴らしい物語なんですよ。
愛あり、冒険あり、人情ありの素晴らしい物語なんですよ。