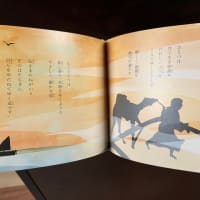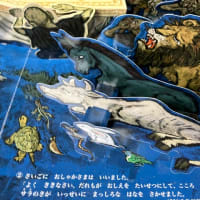寒蘭 紅娥
慶滋保胤(よししげのやすだね)と云う人について知っている人は一般的にはほとんど居ないかと思います。この人は平安期の承平(934頃)の頃、京都賀茂神社の賀茂忠行の次男として誕生しています。儒学の道を歩み御所の大学寮の文章生として菅原文時に師事して詩文の道を究め多くの佳文を残しました。仏教への志向は中国の白楽天や平安中期に市井に念仏を勧化した空也聖の影響を多分に受けたようです。
大学寮の同志を募って始めた「勧学会」(かんがくえ)と名付けられた仏教求道会は仏教史上特筆すべきことでしょう。
彼が収録し上梓した『日本往生極楽記』は次代、次々代へと編纂が受け継がれて行くのです。
伊予国越智郡と云う郷土の事から考えましても、この往生記に収録されている伊予国の住民「越智益躬」のことは愛媛県史上においても注目すべきことでしょう。何故ならばこの「越智益躬」の記述のある文献は保胤の往生記が初見だからです。
このように慶滋保胤とその関連する人達の活動が平安中期以降の仏教、文化に新たな興隆となっていることは看過できません。
そう云った意味からしても幸田露伴の絶筆となった『連環記』はすごさがあります。 多謝

秀麗

青花