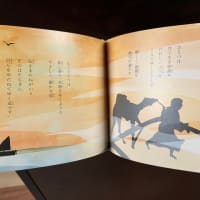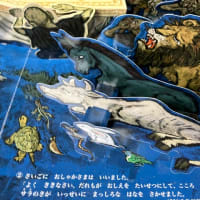御堂の左右の障子戸には蔀戸(しとみど)が設えてあり、平常時は廊下上に水平に
吊り上げられています。この蔀戸も修復されていましたが、黒漆塗りとなっていました。創建当時は黒漆仕上げだったのですネ、
大雨や大風、大変の時にはこれら唐戸、蔀戸でお御堂が守られて来たのです。お御堂の裏手3方は土蔵作りとなっていてお内陣を火災から守るように設えられていることも本願寺両堂の特徴であるとのことです。
中世以後ご本山本願寺が激動期に翻弄されて来た歴史を物語っているようです。
そしてまた、本願寺教団が常に大衆の側に在ったことをも意味していると思います。
吊り上げられています。この蔀戸も修復されていましたが、黒漆塗りとなっていました。創建当時は黒漆仕上げだったのですネ、
大雨や大風、大変の時にはこれら唐戸、蔀戸でお御堂が守られて来たのです。お御堂の裏手3方は土蔵作りとなっていてお内陣を火災から守るように設えられていることも本願寺両堂の特徴であるとのことです。
中世以後ご本山本願寺が激動期に翻弄されて来た歴史を物語っているようです。
そしてまた、本願寺教団が常に大衆の側に在ったことをも意味していると思います。