
総勢36名。
住職さんは、布教の勉強会で10年来のご縁です。

晴天に恵まれ、爽やかな日差しの中、御堂にて一緒に聴聞させていただきました。







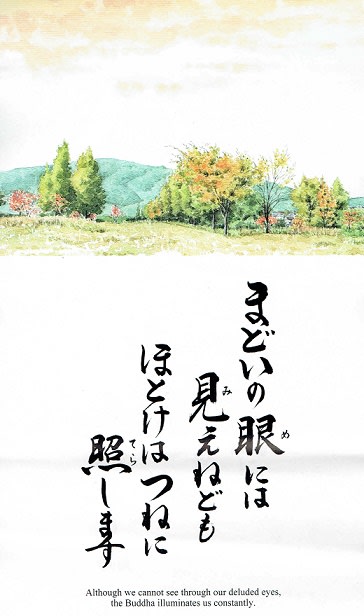
私の74年の人生で今年のように天候不順、大荒れの年はなかったように感じております。変な、変なと思っている内に10月も早3日、慌てて10月の法語アップを行っています。
まどいの眼には見えねども ほとけはつねんい照らします
正信偈の原文は 煩悩障眼雖不見 大悲無倦常照我(煩悩に眼倦を障えられて見ずといえども 大悲倦きこと無くして常に我を照らしたもう)
親鸞聖人が源信僧都の『往生要集』のご文を引用されているカ所ですが、如来さまの純粋で無蓋の大悲を的確に云い得ているご文であります。親鸞聖人このご文を和讃にも詠じておられます。
煩悩にまなこさえられて 摂取の光明みざれども
大悲ものうきことなくて つねにわが身をてらすなり
私の祖父慈朗は大正11年秋、37才で他界しておりますから孫の私は全く知りません。しかしこのような行実が伝わっております。慈朗がまだ万福寺に入寺する前の20代前半の頃のことでしょうが、人生の大きな問題にぶち当たり相当苦悶したことがあったようです。そうした中、朝のお参りの折、このご和讃「煩悩にまなこさえられて・・・・・・・・・」をお唱えした時、忽然として他力信心の深心に触れることが出来たのだと云います。
このようなご縁もあって、このお言葉には一入味わい深いものがあります。
数ヶ月前、末弟の徳正唯生(尊丸)から電話があり「一度、姉弟会を開いたらどうでしょうか、」と云う内容でありました。そう云えば、結婚式や法事で会うことはあっても、姉弟4人だけで話をしたことは、もう何十年もなかったことを思わされました。そうだ、今年は亡父の25年回の年でもあるから、京都のご本山へ一緒にお参りをしよう。と計画を立てました。
ご本山西本願寺にお参りして次に西大谷本廟で法要を営みました。そして栂尾(とがのお)高山寺を訪ねました。この寺には40年位前に両親がお参りしているからです。その折、父が数首の短歌を詠んでいます。
催邪輪(さいじゃりん)ついに読み竟(お)えその著者の住みしみ寺に今訪ね来ぬ
法然に強くあたりし論敵の人とも見えず我が心ひく
山気浸々一眸新緑映ゆる中古き聖に接するおもい
嵯峨野落柿舎 釈迦堂 大徳寺高桐院
5日夜は嵐山に宿を取り、深夜まで話し込んだことです。6日は嵯峨野を巡り、続いて茶道の寺、紫野大徳寺を散策いたしました。姉は今もお茶のお弟子が何人かいるようです。
徳正(末弟)より手紙が届き、俳句が数句添えてありました。
父母の納骨すまし初紅葉
論敵の遺徳偲びし紅木槿
語らひは深夜に及び冷酒かな
落柿舎や姉兄弟揃ひ萩の花
台風一過遺筆訪ねし二尊院

台風10号はまたも東北から北海道方面に向かい猛威を振るいました。今までに経験しない豪雨に多くの家屋、田畑が洪水に流され、多くの人命が失われました。衷心お悔やみとお見舞いを申しあげます。お体に十分気を付けられて復興に当たって下さいますように、
9月カレンダーをめくると、
一生悪を造るとも 弘誓(ぐぜい)に値(あ)いて救わるる とお正信偈の道綽禅師さまの『安楽集』のお味わいを引かれて「一生造悪値弘誓 至安養界証妙果」(一生悪を造れども弘誓に値いぬれば 安養界に至りて妙果を証せしむといえり)
「一生悪を造る」とは誰のことかと云えば、これはこれは私のことであります。何事もない時は、どうにか国法や世間の道徳に従っているようですが、内面と外面は大方相反していることが多く、縁によってはどのようなことを行ってしまうか分からないような「我」を抱えて生きております。そのような無知、無明な私に光明で照らし、「恐れるでない、必ず救う、お浄土へ一緒に帰ろう!」と呼んでいて下さるのです。
台風が過ぎて、少し秋めいて参りました。夏の疲れを癒やしつつお過ごしくださいませ、
本年も万福寺本堂で落語会を開催いたしました。隔年開催で今回で4回目になります。毎回出演しお世話になっております3代目桂春蝶師匠と1回目に来られた笑福亭由瓶師が元気溌剌高座に上がられました。
猛暑の中130名もの方々が来場され、大笑いされました。
pm2時開演、先ず尊前に勤行。若院が高座に上がって法話。そして小休。シュークリームとウーロン茶のおやつ。
そして落語寄席、最初に笑福亭由瓶師の高座。汗一杯の大熱演。
続いてお馴染みの桂春蝶師匠の高座、お客さんの中に子供が数人いたので急遽それ向きの演題に替えたとのこと「くらげの母子の話」
お手伝い頂いた仏婦役員の皆さんと両師匠。猛暑の一日でしたが大爆笑の内に今年の寄席を終えることができました。有難うございます。