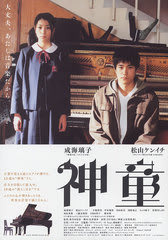裁判員制度が話題になっている。その参考になるのが三谷幸喜の舞台「12人の優しい日本人」と中原俊が監督したその映画化作品 (1991)だ。
三谷幸喜に素晴らしい先見性があったわけではなく、シドニー・ルメット監督作品「十二人の怒れる男 (1957) 」の骨格をもとにして、もし日本に陪審員制度があったら、という想定で書かれたコメディだ。
オリジナルの舞台脚本の面白さと、限定された空間を映画としてうまく処理した中原監督の緊密なショットの積み重ねで、舞台劇の映画化作品としては最もよく出来た作品の一つになっている。
豊川悦司が唯一謎めいたキャラクターで登場するが、公開当時はまだ「誰この人?」状態。今のようにメジャーになっては逆に出来ない役だ。
陪審員と裁判員、厳密には構成も評決方法も違うそうだが、こういうことをやらされるという参考にはなりそうだ。
三谷幸喜に素晴らしい先見性があったわけではなく、シドニー・ルメット監督作品「十二人の怒れる男 (1957) 」の骨格をもとにして、もし日本に陪審員制度があったら、という想定で書かれたコメディだ。
オリジナルの舞台脚本の面白さと、限定された空間を映画としてうまく処理した中原監督の緊密なショットの積み重ねで、舞台劇の映画化作品としては最もよく出来た作品の一つになっている。
豊川悦司が唯一謎めいたキャラクターで登場するが、公開当時はまだ「誰この人?」状態。今のようにメジャーになっては逆に出来ない役だ。
陪審員と裁判員、厳密には構成も評決方法も違うそうだが、こういうことをやらされるという参考にはなりそうだ。