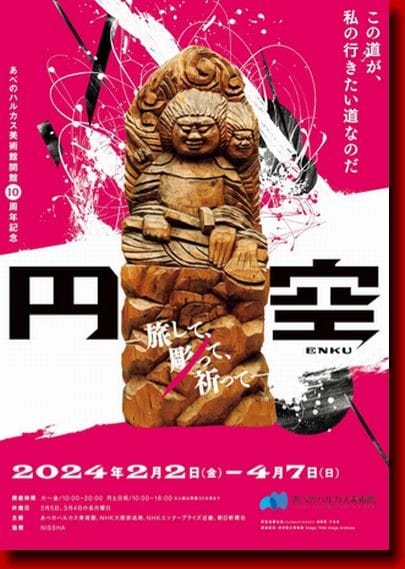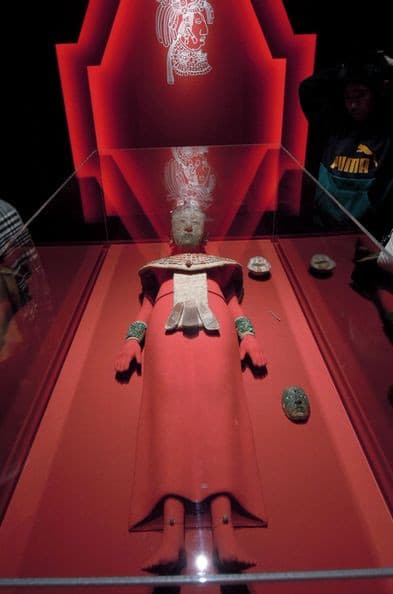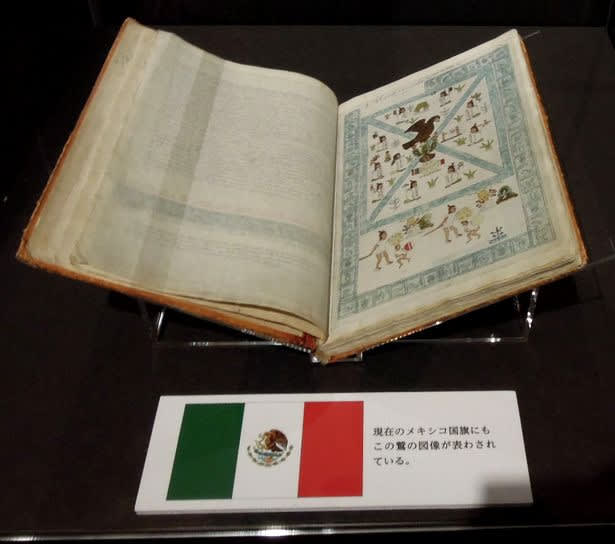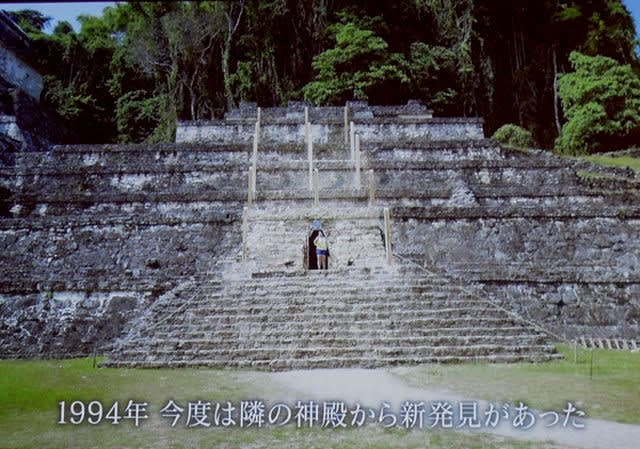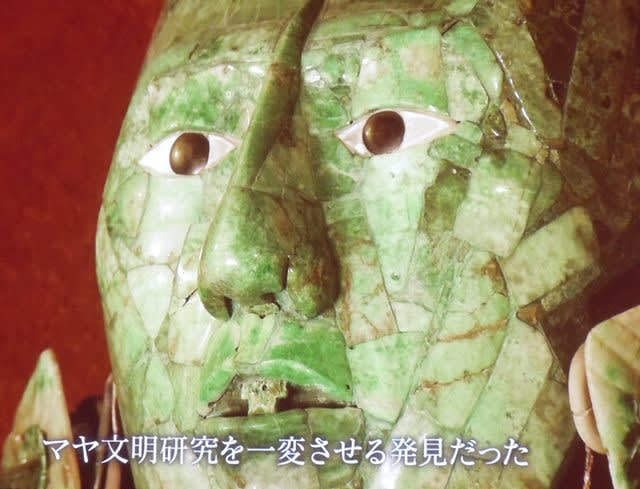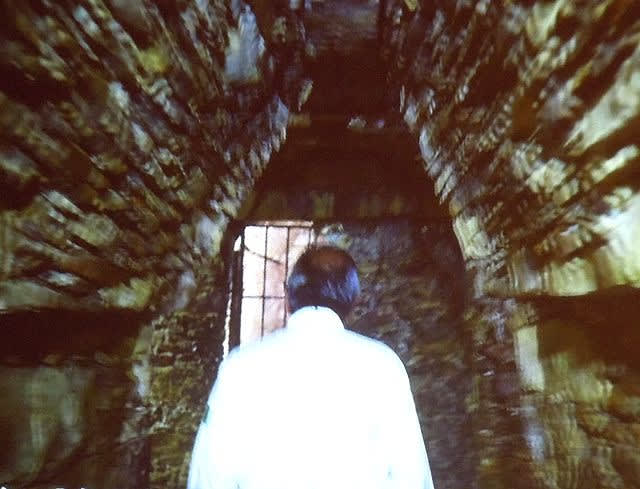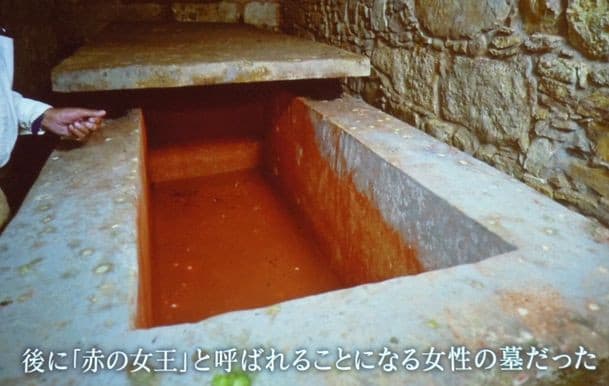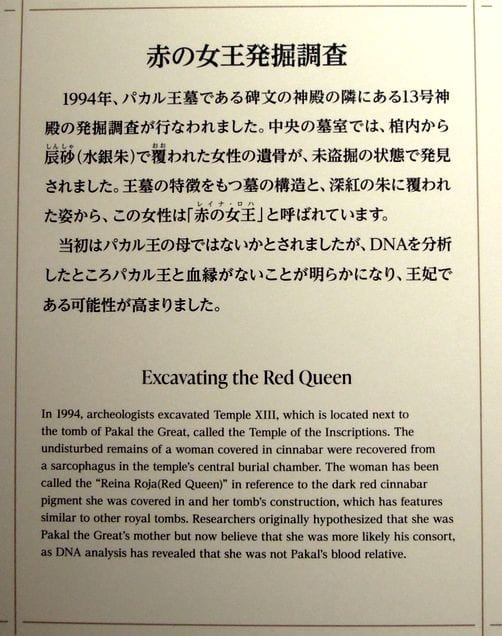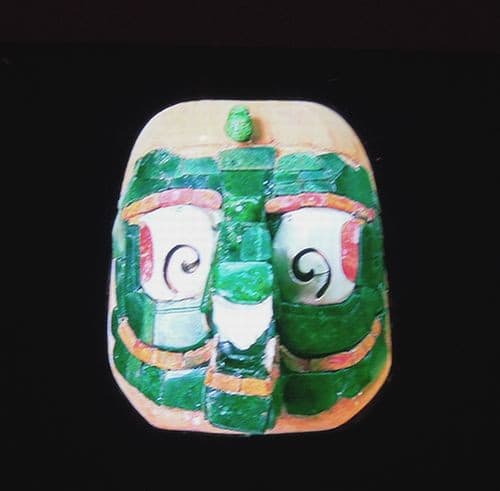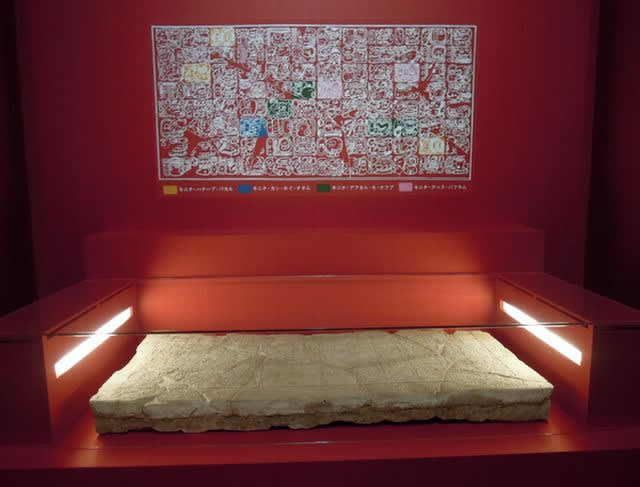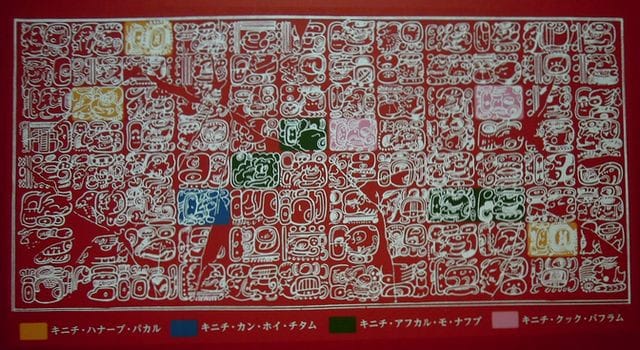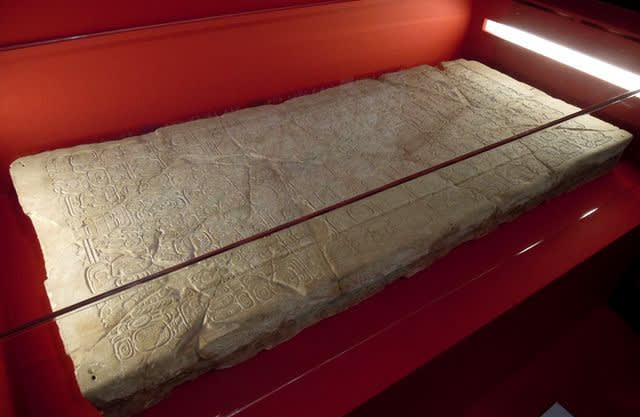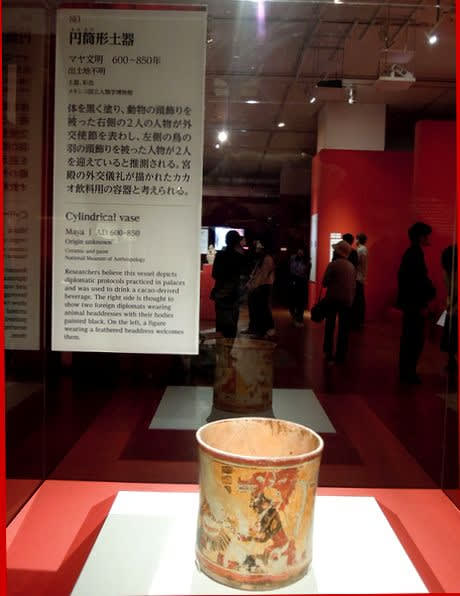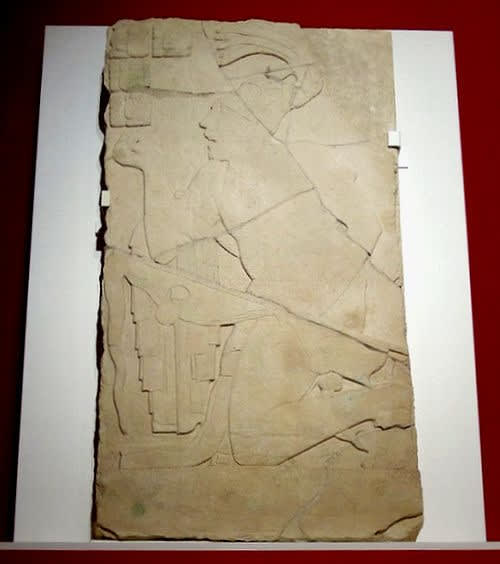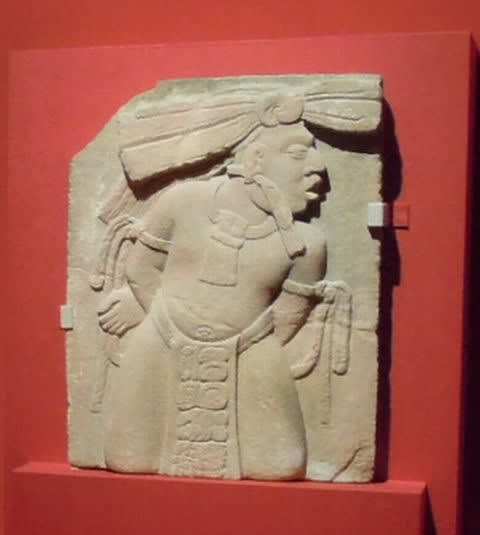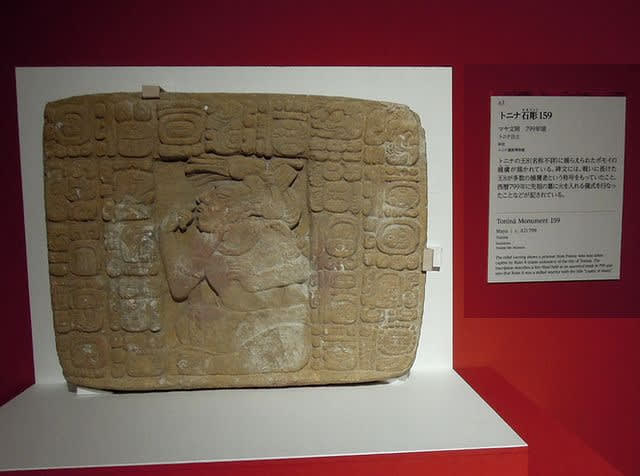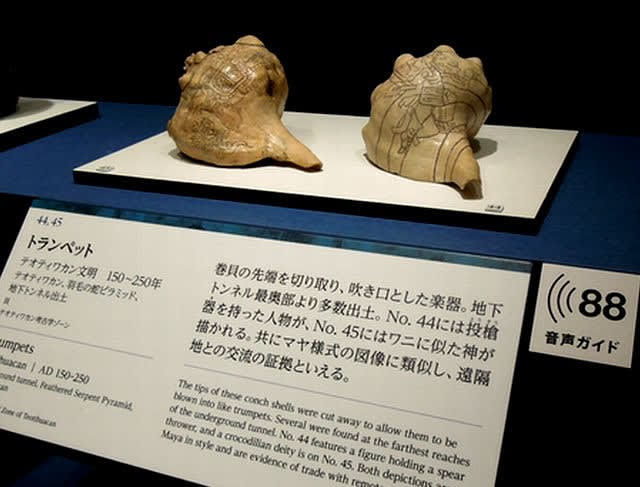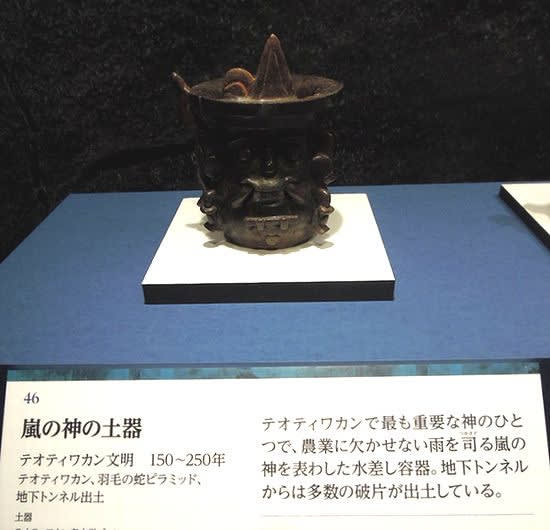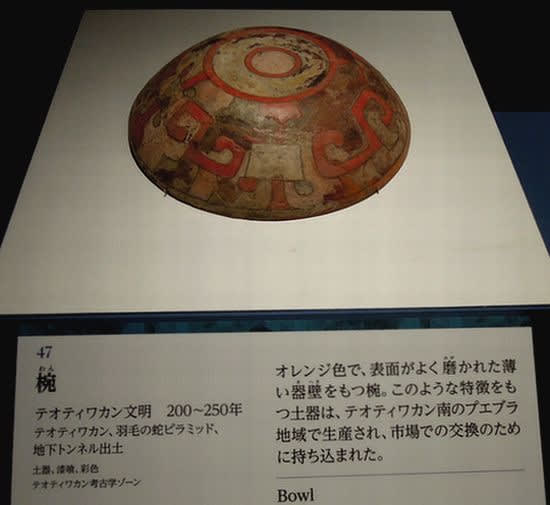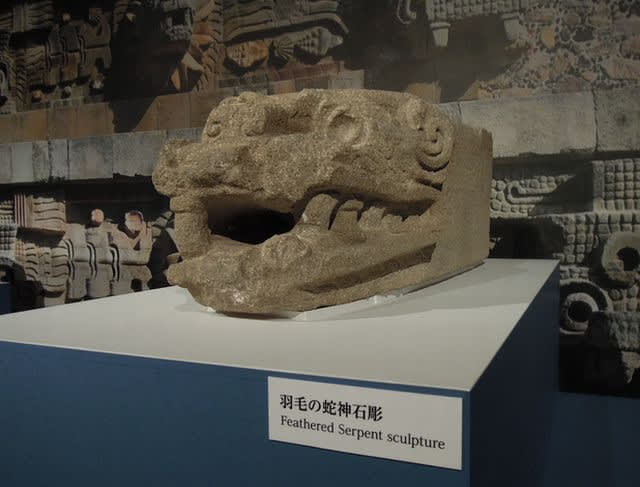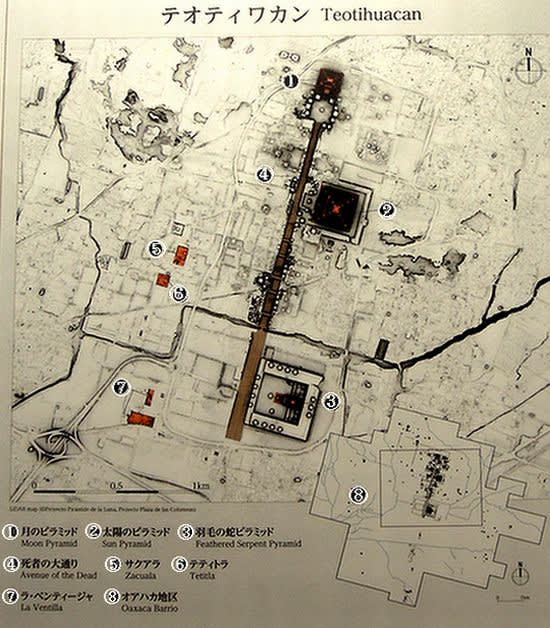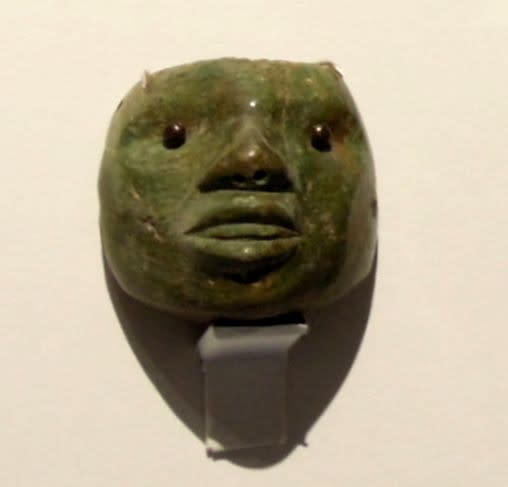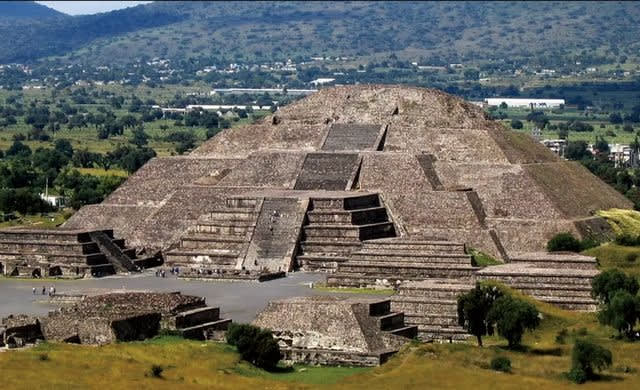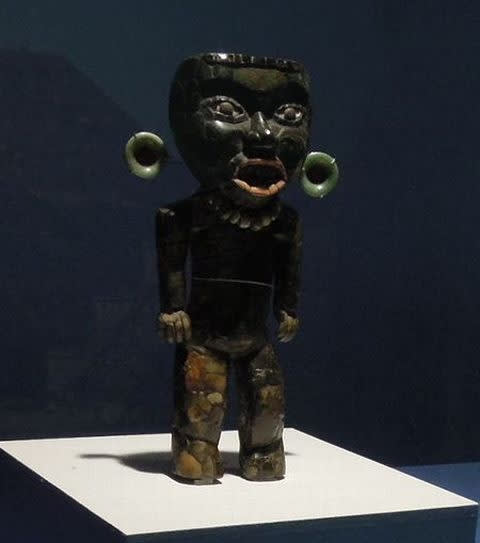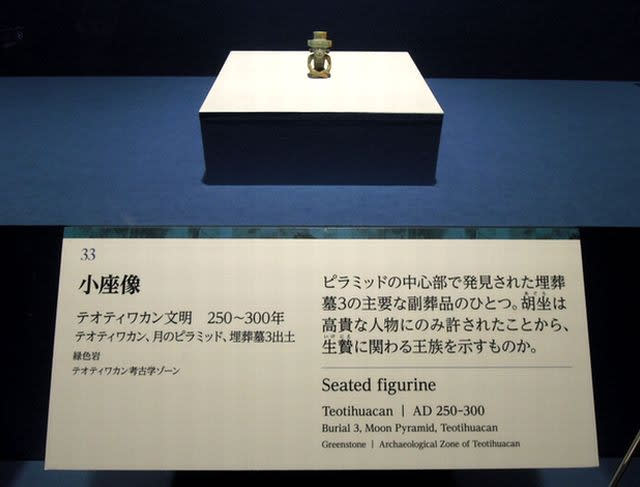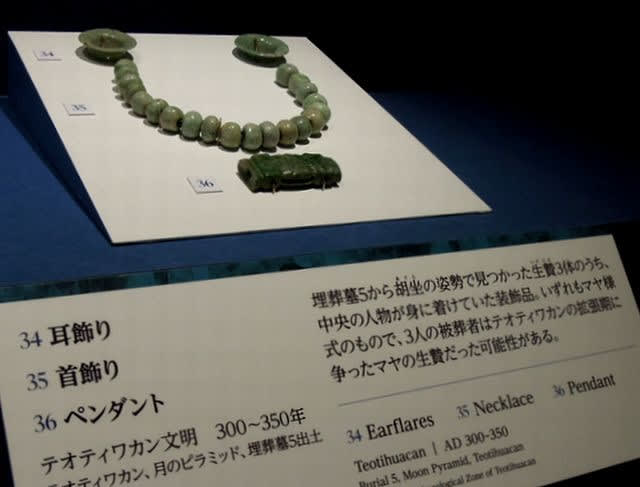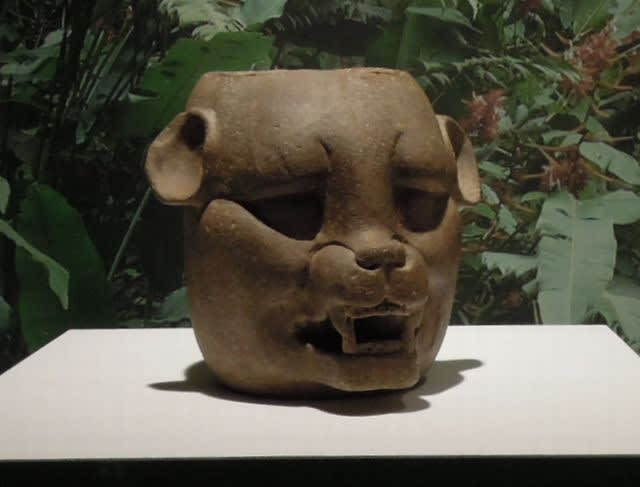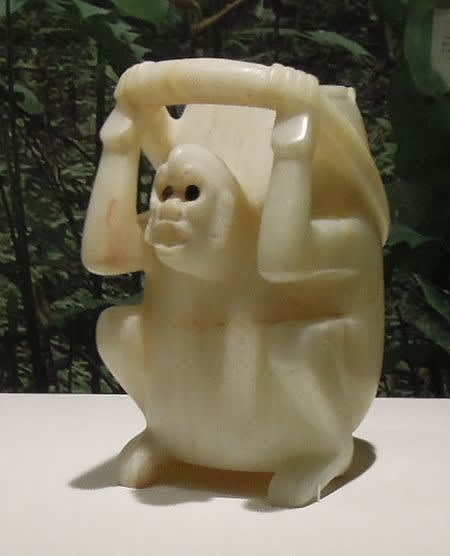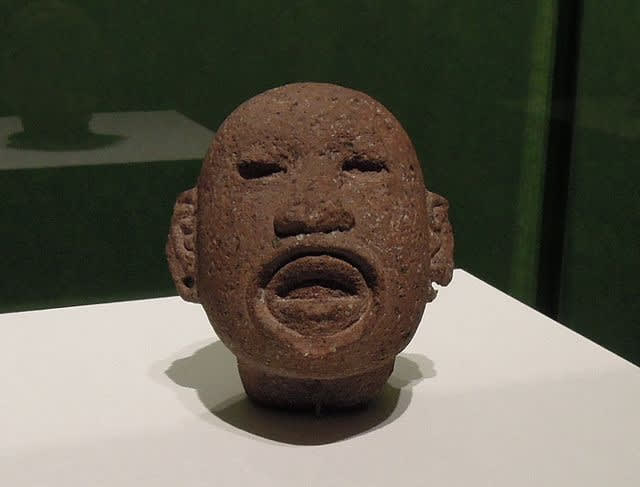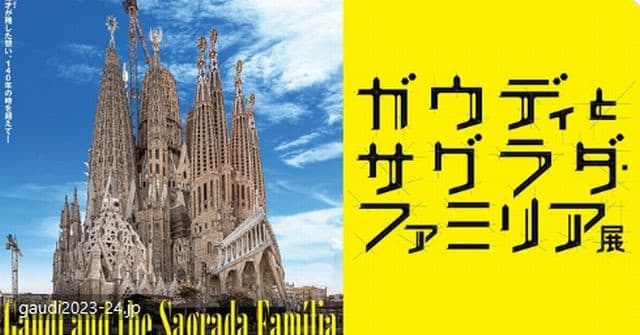「広重 摺の極」

あべのハルカス美術館開館・10周年記念開催
2024年7月6日(土)~9月1日(日) 休館日:8月5日(月)

あべのハルカス美術館だけの開催です。
歌川 広重(うたがわ ひろしげ)
寛政9年(1797年)ー 安政5年9月6日(1858年10月12日)
(安政5年9月6日は、西暦和暦変換で、1858年10月12日)
江戸時代の浮世絵師で、幼名を徳太郎 のちに安藤重右衛門。
NHK総合放送 広重ぶるう【原作】 梶よう子氏
第一回:6月23日(日)午前6時10分~6時52分
第二回:6月30日(日)午前6時10分~6時46分
最終回:7月07日(日)午前6時10分~6時46分
NHK総合放送から
江戸時代の浮世絵師「歌川広重(阿部サダヲ)」は、幼名を徳太郎、のちに重右衛門。家業である江戸の火事を消す火消し同心で、売れない絵を描いていました。
本当に描きたいものが見つからず苦しんでいた時に、広重を気丈に励ましつつ質屋通いの妻・加代(優香)、そして支えてくれた版元・保栄堂の竹内孫八(髙嶋政伸)の提案で「東海道五十三次」を描き始めます。
妻・加代が亡くなり、竹内孫八も去った後、広重の本当に描きたかったものが、安政の大地震(1855年11月)で失われた時に江戸を求めて「名所江戸百景」を描きます。

プルシアンブルーというドイツのベルリンで作られた化学染料は、ベルリン藍、ベロ藍とも言われ、吸い込まれるような美しい藍で広重を魅了し、後に「広重ブルー」といわれました。
※世界の絵画に大きな影響を与え、ゴッホが模写した
『 名所江戸百景 大はしあたけの夕立 』などがあります。
私が行ったのは7月の前期なので展示替えがあります。
前期:7月6日(土)~8月4日(日)
後期:8月6日(火)~9月1日(日)

あべのハルカス美術館開館・10周年記念開催
2024年7月6日(土)~9月1日(日) 休館日:8月5日(月)

あべのハルカス美術館だけの開催です。
歌川 広重(うたがわ ひろしげ)
寛政9年(1797年)ー 安政5年9月6日(1858年10月12日)
(安政5年9月6日は、西暦和暦変換で、1858年10月12日)
江戸時代の浮世絵師で、幼名を徳太郎 のちに安藤重右衛門。
NHK総合放送 広重ぶるう【原作】 梶よう子氏
第一回:6月23日(日)午前6時10分~6時52分
第二回:6月30日(日)午前6時10分~6時46分
最終回:7月07日(日)午前6時10分~6時46分
NHK総合放送から
江戸時代の浮世絵師「歌川広重(阿部サダヲ)」は、幼名を徳太郎、のちに重右衛門。家業である江戸の火事を消す火消し同心で、売れない絵を描いていました。
本当に描きたいものが見つからず苦しんでいた時に、広重を気丈に励ましつつ質屋通いの妻・加代(優香)、そして支えてくれた版元・保栄堂の竹内孫八(髙嶋政伸)の提案で「東海道五十三次」を描き始めます。
妻・加代が亡くなり、竹内孫八も去った後、広重の本当に描きたかったものが、安政の大地震(1855年11月)で失われた時に江戸を求めて「名所江戸百景」を描きます。

プルシアンブルーというドイツのベルリンで作られた化学染料は、ベルリン藍、ベロ藍とも言われ、吸い込まれるような美しい藍で広重を魅了し、後に「広重ブルー」といわれました。
※世界の絵画に大きな影響を与え、ゴッホが模写した
『 名所江戸百景 大はしあたけの夕立 』などがあります。
私が行ったのは7月の前期なので展示替えがあります。
前期:7月6日(土)~8月4日(日)
後期:8月6日(火)~9月1日(日)