日本マレーシア学会(JAMS)関東地区研究会2016年度第5回研究会
日時:2016年7月9日(土)14時~17時
場所:立教大学池袋キャンパス5号館5203教室
テーマ:エコクリティシズムとマレーシア研究
コメント:野田研一(立教大学名誉教授、立教大学ESD研究所運営委員)
タイトル:ネイチャーライティングとしてのマレーシア華人文学
発表者:舛谷 鋭(立教大学観光学部)
概要:マレーシア華人文学(馬華文学)は20世紀初頭の五四運動の影響による中国語口語文学である。コモンウェルス文学などの英語文学がAnglophone Literatureと呼ばれるのを参照例に、Sinophone(華語語系) Literature(華語話者の文学)という定義が今世紀以降使われているが、マラヤのSinophoneは1920年代の「南洋色彩提唱」、30年代の「マラヤ地方性」以来、戦直後の「僑民文芸論争」に至るまで、独立前から送出国との相対化によって独自性を主張してきた。現代文学では、熱帯雨林やゴム林、ボルネオライティングにおける熱帯自然や動植物などをモチーフに、ネイチャーライティングを展開している。こうした要素は台湾文学の先住民、東南アジア移民、香港文学の国際都市、雑種性などと同様、古典文学を共有する中国大陸との差異化を図るものと捉えることもできよう。本発表では、現代マレーシアのSinophone作品をエコクリティシズムの視点から再検討することを試みる。
タイトル:熱帯マレーシアの語り方—文学と民族誌から考える—
発表者:奥野 克巳(立教大学異文化コミュニケーション学部)
概要:季節性の乏しい熱帯マレーシア。そこでは、あるとき一斉に花が咲き、実が一斉に成る。そのとき蜂が蜜を吸い、鳥や猿が実を啄み落下させ、地上の動物たちがそれを食べる。森は食べ物に溢れ、ひとときのと化す。地上や樹上の種子は芽吹き、やがて陽光と養分が行きわたれば生長するだろう。被子植物や昆虫や脊椎動物のとの間で、過去一億年くり返されてきたそのような熱帯雨林の生命活動のほんの一隅に人間がいるにすぎない。人類が自然環境を大きく変えてしまうと呼ばれる時代になったと雖も、人間のみが言語のうちに特遇され、記述され過ぎてきたのだとは言えまいか。
そうした点を踏まえ、今日、人間を含む熱帯の自然は、いったいいかに記述されるべきなのか。本発表では、マレー半島を舞台として、巨大樹である主人公によって時空を超えて語られる文学作品(谷崎由依「天蓋歩行」『すばる』2016年5月号)を読み、サラワクの混交双葉柿林の中で、動植物が紡ぎだす生命活動に深く参与する狩猟民プナンを民族誌の中に描きながら、熱帯がいかに記述されるべきなのかを考えたい。
https://www.facebook.com/events/1212625515434344/











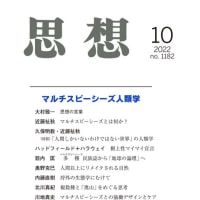

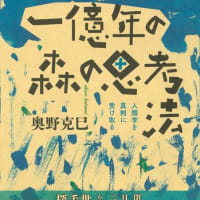
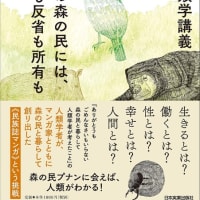



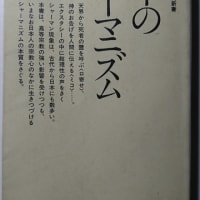


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます