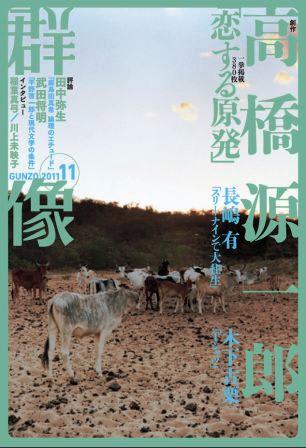
高橋源一郎「恋する原発」『群像』2011.11.pp.6-131.(11-45)★★★★★★
雑誌掲載にストップがかかったというような情報が伝わってきて、そのことによって逆に、読書欲をそそられていたのであるが、日々、被災地の復興・復旧の遅れ、被曝と放射線量の影響、政治家たちの正義ぶったり、な~んも考えてなかたりするような言葉言葉言葉、自治体の原発承認をめぐるメールやらせ問題、さらには、脱原発・原発推進などをめぐる「知識人」たちの「知識人」ぶった批評など、震災後の意見表明や珍見提出にうんざりして、やや食傷気味のところに、「恋する原発」は、一見、「不謹慎」な内容ながら、ほ~、なるほどね、すごい!、と思わされるようなスパーキングな読後感を与えてくれる。
ストーリーは、AV監督という職業を恥ずかしく思っている男のチャリティーAV作成をめぐる奮闘の日々の物語。最初に、AVの作品が、たんなるAVではなく、どんどんとヘンテコになって来ている現実が描き出される。そのうちに、主人公たちは、2011.3.11.の地震の揺れにみまわれる。前半部分でまず驚かされるのは、放送禁止用語のお構いなしの連呼・連発である。慣れてきて、読者(である私)は、そのうちに、何も感じなくなって、やがて作者の術中にはまっていくのだ。
『恋するために生まれてきたの・大正生まれだけどいいですか?』という「AV業界を震撼させたシリーズ」の第一弾、『稲元ヨネさん七十二歳・夫が戦死してから五十年ぶりのセックスです、冥途の土産にしたかった』 では、ヨネさんと二十二歳童貞カネダとのセックスが記録されている。それを見た視聴者の反応は、おおむね、4つある。「(1)目を瞑る。(2)ヴィデオのスイッチをOFFにする。(3)他のヴィデオに替える。(4)試練だと思って、見つづける。」私なら、(4)かなと思ったけど、「多くの視聴者たちが(1)を選んだ」らしい。そして、そのヴィデオの反響はすごかったらしい。三人が出家し、全財産をアメリカ動物虐待防止協会に寄付したやつもいた。「女の裸を見てもなにも感じなくなった」・・・「男に生まれてきてすいません」というような反響も。ロケバスでは、怒涛の叫びが巻き起こったという。「戦争に反対する!あらゆる抑圧に反対する!・・・」。「あの72歳のヨネさんの裸体とセックスシーンを世界のテレビのゴールデン番組で放映したら、この世から戦争なんかなくなるんじゃないだろうか。」そのAVには現実への強い喚起力があるのだ。
ところで、何で、このヨネさんのAVヴィデオが震災に関わるのかというと、そのAVを撮影した15年前に、小学校の先生にレイプされてから30年間セックスしていなかった、ヨネさんの姪のヨシコさん(40歳)が、その作品のおまけのコーナーのなかでセックスをしていたのだが、当のヨシコさんは、いま福島のハズレにある、小学校に設けられた避難所で避難生活をしているからである。AV製作のスタッフは、『大正生まれですけどいいですか?』のシリーズに出演後に亡くなったおばあさんの法要に出かけて行って、自分たちが元気であることを知らせるためにセックスして、それを撮影する。ある人は、それを冒瀆だという。そりゃそうだろうなと思う。「それって冒瀆なのかな。おれは麻痺しているから、わからんけど。ちゃんと、お布施も持ってゆくし・・・最後には脱いじゃうわけだが。」う~ん、やっぱり狂ってんじゃないかと、私は思うけど。
そのあたりの問題を、作家・高橋源一郎はこの作品でターゲットにしているのではないだろうか。震災後の復興復旧、原発や被爆問題、それらをめぐる行政のごたごた、議員たちの正義を振りかざした言葉、知識人の批評などによってつくられてゆく現代日本社会の浮ついた現実に切り込むために、高橋は、映画やニュースからは捨象される一方で、現代日本人の現実であるAV産業のなかの「チャリティーAV」というヘンテコな、キワモノ的な慈善事業を描き出すことで、日本社会の狂気へと迫ろうとしたのではないだろうか。高橋は、「チャリティーAV作って、その収益性を寄付するより、ふつうにAVをサクサク作って、その収益を寄付したほうが手っとり早いんじゃないですか?」と、主人公の口からまともなことをしゃべらせている。
最後には、フクシマ第一原発前広場での、「ウィー・アー・ザ・ワールド」をバックミュージックとして、一万組・二万人同時集団セックスというチャリティーAVが行われる。最後の最後になって、「っていうのはどう?そんな案却下。なんで!そんなのAVじゃないからだよ!」という言葉で締めくくられ、それが「案」であったことが明かされる。
さらに、この作品には、そのクライマックスに行く手前に、骨太の「震災文学論」が差し挟まれている。「ぼくはこの日をずっと待っていたんだ」という、インタヴューを受けたある著名人の「不謹慎な」言葉によって、高橋は、震災後の「がんばれ東北、がんばれニッポン!」という現代日本社会の風潮に安住することなく、そういう見方に挑んでいるように思える。そのなかで、川上弘美『神様2011』、宮崎駿『風の谷のナウシカ』、石牟礼道子『苦海浄土』が取り上げられている。「わたしたちは、『死』や『老い』を『汚れ』とみなすようになった。おそらく、『病』や『障害』や『貧困』も。『汚れ』は浄化されなければならない。つまり、私たちの視線から遠ざけられなければならない。」震災や死や貧困や障害は、それほど、酷ったらしいことなのだろうか。それらはこれまでつねに人を苛んできたし、それゆえに、人はそれらとうまくやって来たのではないだろうか。「おそらく、『震災』はいたるところで起こっていたのだ。わたしたちは、そのことにずっと気づいていなかっただけなのである」。










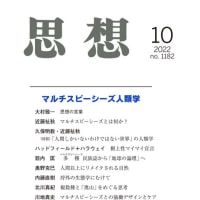

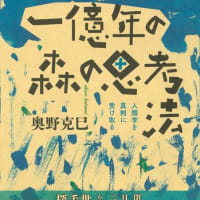
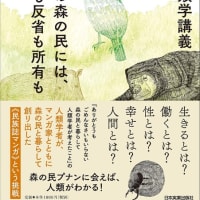



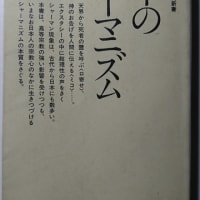


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます