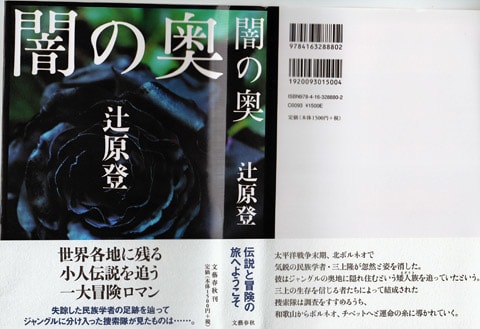昨年末、いつものBookOffでこの本に出会いました。

10年近くも前の2002年1月の発行で、しかもよく読みこまれているのに(あとで見ると
赤ボールペンのアンダーラインまでありました)、まだ定価の半額の棚にありました。
いつもなら手を出さないのですが、ちょうど関心のある国だったので買って帰りました。
著者の篠沢教授(近影ではあのふくよかな面影は見る由もなく、お気の毒)によると、
この本は「フランス文明の真相」、「ふざけていえば『深層』」を探るのがテーマです。
内容は1.フランスとは何だろう 2.フランス語とは何だろう 3.文明としての
フランス からなり、難しい問題も随所に篠沢節がバクハツして面白く読めます。
フランス史にはそれほど関心はないのですが、大昔に「世界史」で習った百年戦争、
アンシャン・レジーム、フランス大革命はじめ、懐かしい言葉が次々と現れます。
「三銃士」や「ジャンヌ・ダルク」などにも触れています。また、これまで気づか
なかった「イギリスとフランスの関係」たとえば、ブルターニュとグランド・ブル
ターニュ(グレート・ブリテン)の関係や、現在の英語(イングランド語)の成立した
のは実は14世紀、日本では足利時代だったことなど、「目から鱗」の話もたくさんあり
ます。
「フランスは日本に似ている」という結論らしいのですが、まだ半分ほどしか読んでい
ない今は<時間がかかるのは、やはり固い本?>「ああ、このことだな」と気付く程度
です。
で…真相確認のために明日から8日間、フランスへ行ってきます。土産話をお楽しみに。

10年近くも前の2002年1月の発行で、しかもよく読みこまれているのに(あとで見ると
赤ボールペンのアンダーラインまでありました)、まだ定価の半額の棚にありました。
いつもなら手を出さないのですが、ちょうど関心のある国だったので買って帰りました。
著者の篠沢教授(近影ではあのふくよかな面影は見る由もなく、お気の毒)によると、
この本は「フランス文明の真相」、「ふざけていえば『深層』」を探るのがテーマです。
内容は1.フランスとは何だろう 2.フランス語とは何だろう 3.文明としての
フランス からなり、難しい問題も随所に篠沢節がバクハツして面白く読めます。
フランス史にはそれほど関心はないのですが、大昔に「世界史」で習った百年戦争、
アンシャン・レジーム、フランス大革命はじめ、懐かしい言葉が次々と現れます。
「三銃士」や「ジャンヌ・ダルク」などにも触れています。また、これまで気づか
なかった「イギリスとフランスの関係」たとえば、ブルターニュとグランド・ブル
ターニュ(グレート・ブリテン)の関係や、現在の英語(イングランド語)の成立した
のは実は14世紀、日本では足利時代だったことなど、「目から鱗」の話もたくさんあり
ます。
「フランスは日本に似ている」という結論らしいのですが、まだ半分ほどしか読んでい
ない今は<時間がかかるのは、やはり固い本?>「ああ、このことだな」と気付く程度
です。
で…真相確認のために明日から8日間、フランスへ行ってきます。土産話をお楽しみに。










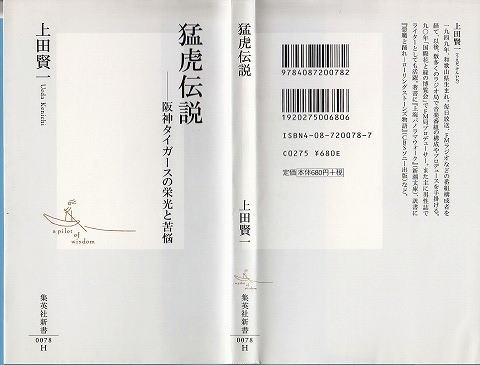
 ちょと興奮しすぎました。
ちょと興奮しすぎました。