河口慧海の「チベット旅行記」に始まり、「チャンタンの蒼い空」まで、長い間
とびとびに拾い読みしてきたチベット関連本ですが、このあたりでお終いにしたい
と思います。
「チベット」と聞くと誰しも思い浮かべるのは「ポタラ宮のあるラサ」、あるいは
「カイラス山」の光景でしょう。行政区域上は「中華人民共和国チベット自治区」。
しかしチベットは、かって広範な範囲に版図を広げ栄えていたので、その文化圏は
かなり遠くにまで及んでいます。

上のガイドブック「旅行人ノート チベット」は、副題に「全チベット文化圏完全
ガイド」とあるように、前回の「ドルボ」、前々回の「ラダック」地方はもちろん、
中国だけでなくインド、ネパール、ブータンまでを含めた詳細なガイドブックに
なっています。
各地方のガイドに先立つ総説にあたるチベットの自然、歴史、また「チベット世界
をもっと知るために」の副題の付いた「解説」は、何度も読み返しています。
「チベットの歴史」では、いわゆる吐蕃時代から現代まで、中国側から見た歴史と
チベット側から見た歴史を二段組で対比させているのがとても興味深いです。
例えば、ダライ・ラマの亡命のいきさつについて
中国側
しかし、チベットが平和のうちに解放され、祖国の懐に抱かれるのに我慢出来ない
者たちがいた。それは外国の反中国勢力と一部の元貴族・農奴主だった。彼らは
たびたび妨害・破壊工作を続け、ついに1959年に武力反乱を起こした。
14世ダライ自らの希望でチベット軍区講堂での観劇が決まった際、反乱分子たち
は「漢人がダライを拉致しょうとしている」とか「毒殺しょうとしている」とかの
デマを飛ばして市民を扇動し、当日2000人余りの市民を脅迫してダライの住むノル
ブリンカに生かせた。彼らはダライを脅迫してラサから連れ出し、…
チベット側
1959年、ラサにいた中国軍の将軍がダライ・ラマ14世に、中国軍駐屯地に劇を見に
来るようにと命令した。チベット人たちは、法王が誘拐されるのを心配し、法王の
離宮ノルブリンカを取り囲んで法王を守ろうとした。これを抑えようとした中国軍
がチベット人たちと衝突し、数千のチベット人が殺された。これ以上の悲劇を避け
るため、ダライ・ラマ14世はひそかにインドに逃れ、北インドのダラムサラに亡命
政府を立てた。
現在、チベットの子供たちが学校で学んでいる歴史が「中国側」の主張する歴史で
あることは間違いありません。
図版や地図の詳しさは群を抜いていて(もちろん私の知る限りですが…)ネパール
への旅では随分重宝しました。

これはカトマンドゥ市内タメル地区の地図ですが、しばらく在住していた息子に
聞いた情報を書き加えています。チベット文化に関する地図などは更に詳細です。
(例えばスワヤンブナートやボダナート周辺のチベット寺院の地図など)
私の持っているのは1998年発行の改訂版ですが、現在絶版になっています。
最新の第4版の目次を見ると、ラサの項に「ついに鉄道がやって来た!~青蔵鉄道
が開通~」とあり、また改訂版では「ネパールのチベット圏」だったものが
「ネパールヒマラヤ」になり詳しい項目も増えています。
この新しい本を持って「カイラス周辺」は無理としても、せめて「ラサからカトマンドゥ」
への旅をしてみたいというのが、今の変愚院の夢となっています。
どうも長い間、「チベット関連本」にお付き合い頂きありがとうございました。
とびとびに拾い読みしてきたチベット関連本ですが、このあたりでお終いにしたい
と思います。
「チベット」と聞くと誰しも思い浮かべるのは「ポタラ宮のあるラサ」、あるいは
「カイラス山」の光景でしょう。行政区域上は「中華人民共和国チベット自治区」。
しかしチベットは、かって広範な範囲に版図を広げ栄えていたので、その文化圏は
かなり遠くにまで及んでいます。

上のガイドブック「旅行人ノート チベット」は、副題に「全チベット文化圏完全
ガイド」とあるように、前回の「ドルボ」、前々回の「ラダック」地方はもちろん、
中国だけでなくインド、ネパール、ブータンまでを含めた詳細なガイドブックに
なっています。
各地方のガイドに先立つ総説にあたるチベットの自然、歴史、また「チベット世界
をもっと知るために」の副題の付いた「解説」は、何度も読み返しています。
「チベットの歴史」では、いわゆる吐蕃時代から現代まで、中国側から見た歴史と
チベット側から見た歴史を二段組で対比させているのがとても興味深いです。
例えば、ダライ・ラマの亡命のいきさつについて
中国側
しかし、チベットが平和のうちに解放され、祖国の懐に抱かれるのに我慢出来ない
者たちがいた。それは外国の反中国勢力と一部の元貴族・農奴主だった。彼らは
たびたび妨害・破壊工作を続け、ついに1959年に武力反乱を起こした。
14世ダライ自らの希望でチベット軍区講堂での観劇が決まった際、反乱分子たち
は「漢人がダライを拉致しょうとしている」とか「毒殺しょうとしている」とかの
デマを飛ばして市民を扇動し、当日2000人余りの市民を脅迫してダライの住むノル
ブリンカに生かせた。彼らはダライを脅迫してラサから連れ出し、…
チベット側
1959年、ラサにいた中国軍の将軍がダライ・ラマ14世に、中国軍駐屯地に劇を見に
来るようにと命令した。チベット人たちは、法王が誘拐されるのを心配し、法王の
離宮ノルブリンカを取り囲んで法王を守ろうとした。これを抑えようとした中国軍
がチベット人たちと衝突し、数千のチベット人が殺された。これ以上の悲劇を避け
るため、ダライ・ラマ14世はひそかにインドに逃れ、北インドのダラムサラに亡命
政府を立てた。
現在、チベットの子供たちが学校で学んでいる歴史が「中国側」の主張する歴史で
あることは間違いありません。
図版や地図の詳しさは群を抜いていて(もちろん私の知る限りですが…)ネパール
への旅では随分重宝しました。

これはカトマンドゥ市内タメル地区の地図ですが、しばらく在住していた息子に
聞いた情報を書き加えています。チベット文化に関する地図などは更に詳細です。
(例えばスワヤンブナートやボダナート周辺のチベット寺院の地図など)
私の持っているのは1998年発行の改訂版ですが、現在絶版になっています。
最新の第4版の目次を見ると、ラサの項に「ついに鉄道がやって来た!~青蔵鉄道
が開通~」とあり、また改訂版では「ネパールのチベット圏」だったものが
「ネパールヒマラヤ」になり詳しい項目も増えています。
この新しい本を持って「カイラス周辺」は無理としても、せめて「ラサからカトマンドゥ」
への旅をしてみたいというのが、今の変愚院の夢となっています。
どうも長い間、「チベット関連本」にお付き合い頂きありがとうございました。















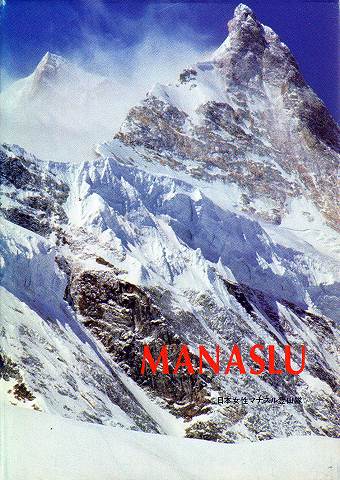
























 2005.08.05撮影
2005.08.05撮影

