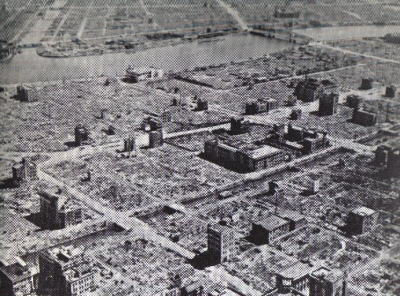今度、NHKは司馬遼太郎の『坂の上の雲』をドラマ化し放映するようだ。
司馬遼太郎は、太平洋戦争に従軍し辛酸をなめた経験もあって、日露戦争以後の日本は「あかん」、明治の日露戦争までの日本は「凛としていた」というベースで『坂の上の雲』を書いているらしい。
『坂の上の雲』という題も「理想を求めて坂の上に見える雲を追って駆け登る青年達は素晴らしかった」というメッセージであろう。
ところが、今日、恵送されてきた中塚 明著『司馬遼太郎と歴史観ーその「朝鮮観」と「明治栄光論」を問うー』(高文研刊)を読むと、「歴史は、司馬遼太郎が言うような、一時前は良かったが最近は駄目」みたいな単純なものではない。
歴史は司馬の言うような「不連続」なものではなく連綿と「連続」しているものだ、というメッセージが伝わってくる。
世の俗論に、「朝鮮は放っておくと、ロシアの植民地になる恐れがあり、そうなれば日本は窮屈になる。もし、そうなら日本が先手を打って朝鮮を封建制から解放してあげた方が良い・・・」というのがある。
これは、事実に照らして見ると、全く違っていて、明治の日清戦争の前から、日本は朝鮮を「併合」しようと虎視眈眈狙っていたことが明らかとなる。
日清戦争をする場合も日露戦争の場合も、まず最初に朝鮮政府を抑えてから乗り出していることが歴史的事実としてある、とこの著書は事実を上げ論証している。
司馬は、『坂の上の雲』では、日清戦争に際しても日露戦争に際しても日本が朝鮮に対し何をしたか、それに対する朝鮮の政府や国民の動きはどうかには殆どふれていないと言う。
これは、戦後のことだが、日韓条約の締結に15年も要したのは、日本の朝鮮併合の意味について日韓で認識が大きく違っていたことがある、という。
朝鮮民族の日本に対する抵抗として「東学党の乱」(東学農民革命)があるが、日本人は、殆ど良く理解していない、『坂の上の雲』でも詳しく触れられていないともいう。
朝鮮半島を身近なものにするためにも歴史を連続するものとして深く理解しなければ・・・、とこの著書を読んで思った。ドラマ『坂の上の雲』にも注視していきたい。
中塚 明さんは、私の近所に住んでおられる。一回り「先輩」、京大史学科卒(日本近代史専攻)、奈良女子大学名誉教授、元学術会議会員。定年退官されてから毎年のように研究成果を著書で出しておられる。見習いたいものだ。
司馬遼太郎は、太平洋戦争に従軍し辛酸をなめた経験もあって、日露戦争以後の日本は「あかん」、明治の日露戦争までの日本は「凛としていた」というベースで『坂の上の雲』を書いているらしい。
『坂の上の雲』という題も「理想を求めて坂の上に見える雲を追って駆け登る青年達は素晴らしかった」というメッセージであろう。
ところが、今日、恵送されてきた中塚 明著『司馬遼太郎と歴史観ーその「朝鮮観」と「明治栄光論」を問うー』(高文研刊)を読むと、「歴史は、司馬遼太郎が言うような、一時前は良かったが最近は駄目」みたいな単純なものではない。
歴史は司馬の言うような「不連続」なものではなく連綿と「連続」しているものだ、というメッセージが伝わってくる。
世の俗論に、「朝鮮は放っておくと、ロシアの植民地になる恐れがあり、そうなれば日本は窮屈になる。もし、そうなら日本が先手を打って朝鮮を封建制から解放してあげた方が良い・・・」というのがある。
これは、事実に照らして見ると、全く違っていて、明治の日清戦争の前から、日本は朝鮮を「併合」しようと虎視眈眈狙っていたことが明らかとなる。
日清戦争をする場合も日露戦争の場合も、まず最初に朝鮮政府を抑えてから乗り出していることが歴史的事実としてある、とこの著書は事実を上げ論証している。
司馬は、『坂の上の雲』では、日清戦争に際しても日露戦争に際しても日本が朝鮮に対し何をしたか、それに対する朝鮮の政府や国民の動きはどうかには殆どふれていないと言う。
これは、戦後のことだが、日韓条約の締結に15年も要したのは、日本の朝鮮併合の意味について日韓で認識が大きく違っていたことがある、という。
朝鮮民族の日本に対する抵抗として「東学党の乱」(東学農民革命)があるが、日本人は、殆ど良く理解していない、『坂の上の雲』でも詳しく触れられていないともいう。
朝鮮半島を身近なものにするためにも歴史を連続するものとして深く理解しなければ・・・、とこの著書を読んで思った。ドラマ『坂の上の雲』にも注視していきたい。
中塚 明さんは、私の近所に住んでおられる。一回り「先輩」、京大史学科卒(日本近代史専攻)、奈良女子大学名誉教授、元学術会議会員。定年退官されてから毎年のように研究成果を著書で出しておられる。見習いたいものだ。