二枚目役では売れなかった勝新太郎が、「不知火検校」の、ちょいと、というかものすごく悪いキャラで人気爆発。延長線上にある座頭市でスターの座は確たるものになった。
ちなみに、長唄の三味線方だった父親といっしょに、戦時中は若山富三郎と勝新の兄弟は酒田に疎開していて、港座の建物のなかで遊んでいたんですって。
1962年(昭和37年)製作の映画だからさすがにリアルタイムでは見ていないけれど、観客が熱狂したのがよくわかる。盲目だから日常の所作はどこかユーモラス、というよりはっきりと不格好。そのあたりを勝新は愛敬たっぷりに演じていて、だからこそ凄腕にしてトリッキーな居合い斬りを見せつけるシーンとの落差が効く。
ストーリーは天保水滸伝がベースになっている。“異物”として市があの争いに投げ込まれた形。
座頭市のモデルとなった人物は、原作の子母沢寛によれば確かに飯岡助五郎の客人だったらしい。対する笹川繁蔵の用心棒が、かの有名な平手造酒(天知茂)。労咳病みの剣豪と盲目の按摩が池のほとりで釣りに興ずる場面は味があったなあ。
脚本の犬塚稔は、やくざたちを文字どおりケチな野郎どもに描いていてすばらしい。侠客だの渡世人だのと格好をつけても、内実はこすい方法で敵を陥れることしか考えていないことを強調している。
座頭市にしても、自分の剣法は見せ物小屋の座興にすぎないと卑下していて、しかしそのことで逆に『剣の道』にこだわる平手造酒を……
障子、ふすま、板塀など、日本家屋は白黒映画のためにあるのではないかと思うぐらいに画面が美しい。陰影豊かな画面のなかで、ヒロインの万里昌代と市のからみは泣ける。大映製作陣の底力を思い知らされる傑作。決闘の場面にシジミとりの籠が揺れているなんてテクニック、いまどこの映画会社がやってくれます?















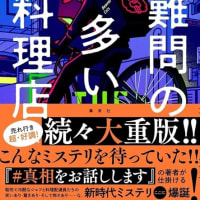













画面の隅々にまで演出が行き届いているってのは
黄金時代だなあ。
「必殺仕置人」は見るぞっ。ちゃんとレビューするぞっ!
お楽しみに。