『升田山を歩く』ができました
加古川市観光協会が升田山のハイキングコースを完成させました。
これに勝手に協賛して、フェイスブックとブログで連載した「升田山を歩く」(29ページ)を暇に任せて、冊子にまとめてみました。
ご希望の方にお分けします。もちろん、無料です。
良い配布方法が見つかりません。ご提案ください。

(内容)
はじめに
1 升田山ハイキングコース完成
2 素晴らしい景色
3 升田山『播磨風土記』に登場(1)
4 升田山『播磨風土記』に登場(2)・八十の岩橋
5 八十橋の伝承と『風土記』
6 3つの古墳群
7 古墳説明板(柱)の修理を!
8 平荘湖古墳群
9 升田山15号墳
10 こけ地蔵
11 稚児窟古墳(池尻16号墳)の石棺の蓋
12 (民話)又平新田村の弁天さん
13 金のイヤリング(カンス塚古墳出土)
14 慰霊碑
15 「加古の入江」:古代升田山からの風景
16 砂部弥生遺跡と東神吉弥生遺跡
17 含芸里(かむきの里)
18 古代山陽道は升田をはしる
19 蝦夷がいた
20 佐伯寺、西念寺そして妙願寺へ
21 慈眼寺(三木市)の鐘・元は佐伯寺の鐘
22 升田堤
23 上部用水(うえべようすい)
24 益気神社での一件
25 平荘湖
26 平荘湖は、池それとも湖?
おわりに
*写真:加古川市観光協会会長の大庫さん











 散歩の途中で「平荘湖」の第3堰堤で、必ず休憩します。
散歩の途中で「平荘湖」の第3堰堤で、必ず休憩します。 加古川市は、工業誘致に積極的に取り組み、工業都市としての発展をめざしました。
加古川市は、工業誘致に積極的に取り組み、工業都市としての発展をめざしました。 升田に益気神社(ますきじんじゃ)があります。
升田に益気神社(ますきじんじゃ)があります。 図をご覧ください。加古川右岸(西側)の平野部の主な灌漑用水は、加古川から取水する土部井用水(うえべようすい)です。
図をご覧ください。加古川右岸(西側)の平野部の主な灌漑用水は、加古川から取水する土部井用水(うえべようすい)です。 写真は、升田山の山頂からの南の平野部の写真です。
写真は、升田山の山頂からの南の平野部の写真です。 図は、「正保播磨国絵図(解読図)」です。
図は、「正保播磨国絵図(解読図)」です。 今日の話題は、加古川市から離れ、三木市久留美(くるみ)の慈眼寺の鐘の話です。
今日の話題は、加古川市から離れ、三木市久留美(くるみ)の慈眼寺の鐘の話です。  升田にある妙願寺に関する話題を2題続けます。そのため、先に妙願寺を紹介しておきます。
升田にある妙願寺に関する話題を2題続けます。そのため、先に妙願寺を紹介しておきます。  東神吉町升田集落の中ほどで、集落を東西に走る古代山陽道沿いに佐伯廃寺跡があります。
東神吉町升田集落の中ほどで、集落を東西に走る古代山陽道沿いに佐伯廃寺跡があります。 『日本書紀』は、大化二年(646)正月の条の「改新の詔」に、「初めて・・・駅馬・伝馬を置く」とあります。
『日本書紀』は、大化二年(646)正月の条の「改新の詔」に、「初めて・・・駅馬・伝馬を置く」とあります。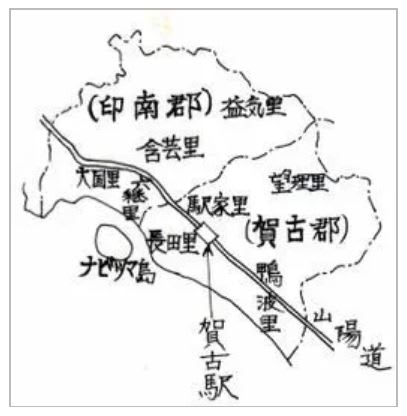 「神吉(かんき)」について考えてみます。
「神吉(かんき)」について考えてみます。
 升田山の頂上へ上り南の景色をご覧ください。広い平野が広がっています。
升田山の頂上へ上り南の景色をご覧ください。広い平野が広がっています。 弁天社のすぐ横に慰霊碑があります。
弁天社のすぐ横に慰霊碑があります。




