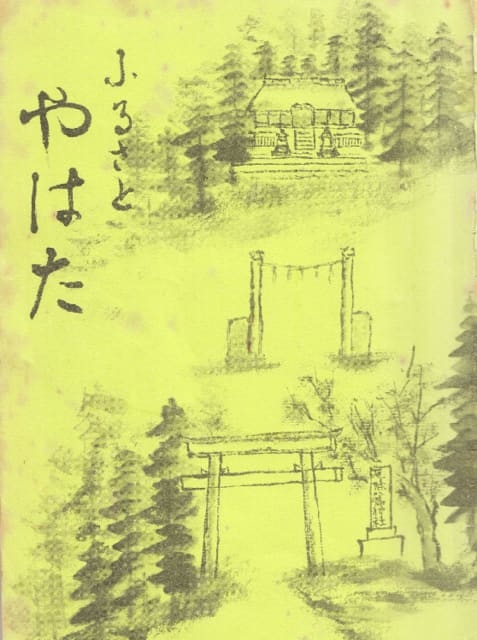志方町をゆく (余話)樋抜きの儀(原の大池 の水抜き)
きょうの神戸新聞に風物詩「樋抜きの儀(原の大池 水抜き)」がありました。その一部をお借りします。
志方町原の大池は、横大路、原、成井、永室、西牧の集落にとって、まさに命の水甕です。
これらの集落は、農業に十分な川がありません。
それに、急峻な山からの水は、そのままでは平野部へ流れ、法華谷川に流れ込んでしまいます。
そのため、山に降った水を、いったん溜めておくため池がどうしても必要になります。
原の大池の水は百姓にとって、まさに命でした。
「ため池の大切さを記憶に残してもらえたら」
池は安土桃山時代に築造されたといいます。
・この日は、近くの志方西小学校の4年生16人も参加。神事の後、取水バルブが開けられると、「円筒分水工」から勢いよく水が流れ出し、児童から歓声が上がりました。・・・
大池五ケ村ため池協議会の米田茂朗会長(63)=同町原=は「地元の伝統行事を体験した子どもたちが、ため池の大切さを記憶に残してもらえたら」と話した。(増井哲夫)