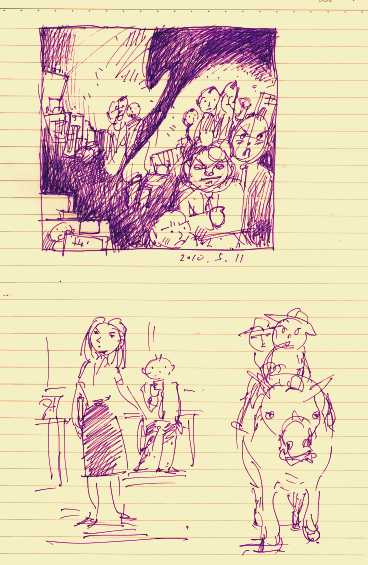
ディラックは散歩の大変な愛好者でした。ある日曜日、仁科と私は非常に古い有名なカシの木を見るために、ディラックをコペンハーゲンの郊外にある森へさそい出しました。ぶらぶらしながら、われわれはいろいろなことについて語り合いました。ディラックは当時、生物を特徴づける性質についてある考えをもっていましたが、それについて話してくれたのです。それは、生物はみな分子構造において左右どちらか一方の側にいるらしいという事実にもとづいていました。ディラックの考えによれば、完全な鏡像をもった生物は存在しないということでした。仁科も私も同様にディラックの考えに対して懐疑的でしたが、彼はそれを面白いと思ったようです。
(オスカー・クラインが仁科芳雄追悼のために寄稿した文章から)
このオスカー・クライン(スウェーデンの物理学者)の回想は1928年デンマーク・コペンハーゲン(ボーア研究所)での出来事。 この散歩のすぐ後に、仁科芳雄とクラインは二人で、ディラック方程式を基に「クライン-仁科の公式」と呼ばれる電子の散乱についての新しい公式をつくりあげるのである。
仁科芳雄は、この年日本に帰る。イギリス(ケンブリッジ・キャベンディッシュ研究所)に1年、ドイツ(ゲッチンゲン)に半年、そしてコペンハーゲンで5年半という長い留学生活であった。仁科は、日本の物理学界に「コペンハーゲン精神」をもたらした、とされている。 「コペンハーゲン精神」とは、ニールス・ボーアが…( 略 )。
上の、ポール・ディラック(イギリスの物理学者、1929年には訪日)の生物の非対称性の意見はおもしろい。ディラックは、自分の編み出した方程式から「電子の負のエネルギー」が出てくるのに首をひねった。「これはなんだろう…?」 考えた末、「プラスの電荷を持った電子」が存在するのではないか、と思った。つまりディラックは、この場合、人間の「眼」や「常識」よりも、「方程式」の対称性を信じたのである。 (一方で生物の非対称性を信じていたというのに。)
彼は無口な男だったという。ディラックはその自分の意見に自信をもっていたわけではないが、自然は彼に味方をした。 「プラスの電荷を持った電子」、陽電子(ポジトロン)は1932年、宇宙線の中から発見されたのである。
発見者はアメリカのアンダーソンだったが、「なぜ自分たちが発見しなかったのか!?」とみんなくやしがった。
一度発見されてみれば、それは地上でも見つかるありふれたものだったのだ。 現在では医療などにも使われている。(PET検査の「P」はポジトロンのことである。)
アイザック・アシモフが陽電子(ポジトロン)脳ロボット・シリーズを書き始めるのは1940年である。「自然」の不思議さは、小説よりも、どうやら先を歩いているようだ。
(オスカー・クラインが仁科芳雄追悼のために寄稿した文章から)
このオスカー・クライン(スウェーデンの物理学者)の回想は1928年デンマーク・コペンハーゲン(ボーア研究所)での出来事。 この散歩のすぐ後に、仁科芳雄とクラインは二人で、ディラック方程式を基に「クライン-仁科の公式」と呼ばれる電子の散乱についての新しい公式をつくりあげるのである。
仁科芳雄は、この年日本に帰る。イギリス(ケンブリッジ・キャベンディッシュ研究所)に1年、ドイツ(ゲッチンゲン)に半年、そしてコペンハーゲンで5年半という長い留学生活であった。仁科は、日本の物理学界に「コペンハーゲン精神」をもたらした、とされている。 「コペンハーゲン精神」とは、ニールス・ボーアが…( 略 )。
上の、ポール・ディラック(イギリスの物理学者、1929年には訪日)の生物の非対称性の意見はおもしろい。ディラックは、自分の編み出した方程式から「電子の負のエネルギー」が出てくるのに首をひねった。「これはなんだろう…?」 考えた末、「プラスの電荷を持った電子」が存在するのではないか、と思った。つまりディラックは、この場合、人間の「眼」や「常識」よりも、「方程式」の対称性を信じたのである。 (一方で生物の非対称性を信じていたというのに。)
彼は無口な男だったという。ディラックはその自分の意見に自信をもっていたわけではないが、自然は彼に味方をした。 「プラスの電荷を持った電子」、陽電子(ポジトロン)は1932年、宇宙線の中から発見されたのである。
発見者はアメリカのアンダーソンだったが、「なぜ自分たちが発見しなかったのか!?」とみんなくやしがった。
一度発見されてみれば、それは地上でも見つかるありふれたものだったのだ。 現在では医療などにも使われている。(PET検査の「P」はポジトロンのことである。)
アイザック・アシモフが陽電子(ポジトロン)脳ロボット・シリーズを書き始めるのは1940年である。「自然」の不思議さは、小説よりも、どうやら先を歩いているようだ。










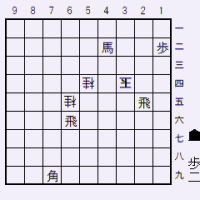
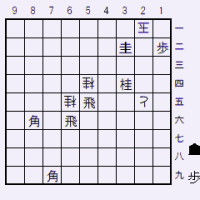
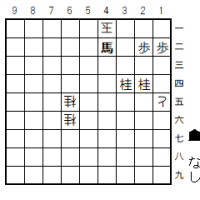
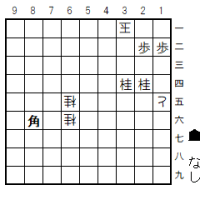
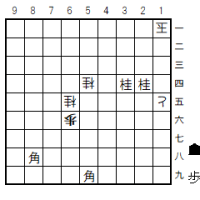
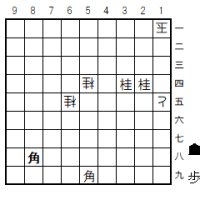
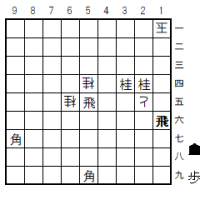
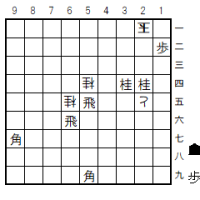
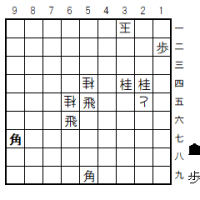
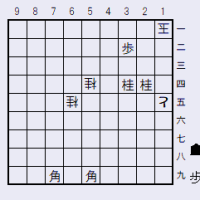






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます