2011年12月14日(水) 日本語での数表現―基数詞 b ③漢式と和式の併用 現在の日本では、実生活上では、桁の概念が不要な1~10迄については、漢式の数え方だけでなく、和式の数え方が、以下の様に、併用されている。 4 よん と、7 なな は、立派に、現役なのだが、他の数詞は、特別な場合しか使われない。 数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 漢発音 いち に さん し ご ろく しち はち く・きゅう じゅう 和発音 (ひい ふう みい よ)・よん ( い む) なな (や ここ とお) 一方、11以上の数についても、4と7の所で、漢式と和式が併用されているのだ。 数字 11 12 13 14 15 16 漢発音 じゅういち じゅうに じゅうさん じゅうし じゅうご じゅうろく 和発音 じゅうよん 数字 17 18 19 20 漢発音 じゅうしち じゅうはち じゅうく にじゅう 和発音 じゅうなな 以下、21以降についても、4と7の所で、漢式と和式が併用されている、のは同様だが、問題となる、40台、70台を見ると、以下の様に、双方が使われるものの、漢式よりも、むしろ、和式の数詞が使われることが多いように思われる。 和式(漢式) 漢式(和式) 44 よんじゅうよん(し) しじゅうし(よん) 47 よんじゅうなな(しち) しじゅうしち(なな) 74 ななじゅうよん(し) しちじゅうし(よん) 77 ななじゅうなな(しち) しちじゅうしち(なな) 100を越えた数字についても、4,7の関連は、以下の様に、殆ど、和式になる。 中には、和式しか使われない場合もあるなど、ややこしい事になっている。 100台 ひゃく○○ 147 ひゃくよんじゅうなな ひゃくしじゅうしち(なな)とは言わない 177 ひゃくななじゅうなな ひゃくしちじゅうしち(なな)とは言わない 400台 よんひゃく○○ しひゃく とは言わない 444 よんひゃくよんじゅうよん 447 よんひゃくよんじゅうなな 700台 ななひゃく○○ しちひゃく とは言わない 777 ななひゃくななじゅうなな 1000を越えた数字についても、4,7の関連では、和式だけである。 4000台 よんせん しせん とは言わない 7000台 ななせん しちせん とは言わない 万、億、兆についても、4,7の関連では、和式だけである。 4万 4億 4兆 よん○○ し○○ とは言わない 7万 7億 7兆 なな○○ しち○○ とは言わない ④ 4,7での和式併用の理由は何? 見て来たように、基数詞では、漢数詞による漢式が基本なのだが、4,7に関しては、和式も併用されている訳だ。でも、4は、(し)ではなく、殆ど(よん)で、7も、(しち)より(なな)が多くなっている。 これは、どのような理由からだろうか。以下は、自分勝手な推測である。 先ず、考えられることは、発音の難易だ。各基数詞の発音時の先頭は、漢式では、以下のように発音される 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 漢式 i ni sa si go ro si ha ku jyu 和式 yo na 漢式では、4(si)と、7(si)は、発音(si)が一緒で、区別が紛らわしいことがあるように思う。この部分を和式にすると、前記のように、4(yo)と、7(na)になり、全体として、先頭に同じ発音が無くなるのだ。 このことが、漢式を基本としながらも、4、7に関しては、和式が根強く残る、大きな理由のように思われる。 もう一つ考えられる理由は、4(し)は、死(し)に繋がるので、4(し)を忌み嫌うという、日本人独特の感覚だ。このことから、特に、4は、(し)ではなく、(よん)と発音されることが多いように思う。 ⑤ まとめ 以上、見て来たように、現在の日本語での基数詞は、漢式を基本としながらも、4、7の所で、和式が併用される形になっていて、場合によっては、和式しか使われない時もある、と言う、複雑なシステムになっている、と言える。 今回の整理をベースに、次回は、いよいよ、厄介な助数詞についても触れることで、この春入学した小学校での、孫の苦戦ぶりに、思いを致すこととしたい。 (記事一覧) 漢字の世界―漢字遊び (2011/2/28) 漢字の世界 その6 デザイン遊び (2011/1/8) 漢字の世界―年賀状の中の名前 (2011/1/3) 漢字の世界 その4 柊の花 (2010/12/20) 広州アジア大会 (2010/12/4) 漢字の世界 その2 国名など (2010/11/19) 漢字の世界 その1 塒という字 (2010/10/30) 日本語の表記 その4 ローマ字入力 (2010/8/27) 日本語の表記 その3 人名のローマ字表記 (2010/8/18) 日本語の表記 その2 たちつてと (2010/8/8) 日本語の表記 その1 駅名は分りやすい? (2010/8/1)











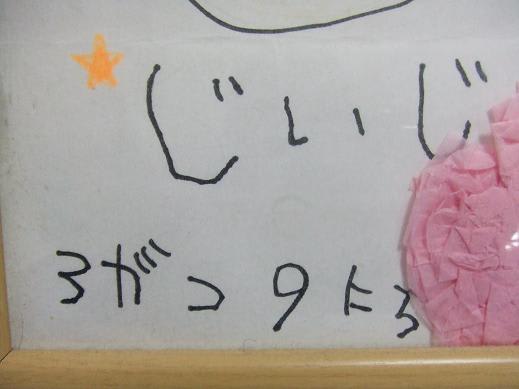
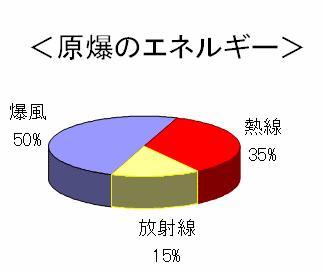



 おいしそう!
おいしそう! あちこちに伸びたランナー
あちこちに伸びたランナー (伝達式 ネットより借用)
(伝達式 ネットより借用)



