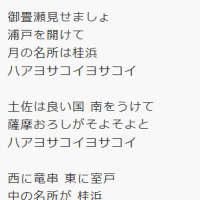2011年12月14日(水) 日本語での数表現―基数詞 a
国際的にも、日本語は、複雑で難しい言語の一つ、と言われる。当ブログでは、これまで、主に、日本語の表記や、漢字の世界について、いくつかの記事で触れて来た。
(末尾の記事一覧 参照)
今回は、日本語での数表現について、述べて見たい。 この話題を取り上げた、一寸した理由は、以下である。
当ブログのプロフィールとして、孫が、小学校就学前に、書いてくれた似顔絵を使用しているが、この絵は、誕生日祝いに貰ったものだ。そこには、筆者の誕生日として
3がつ 9にち
と書き込んであった。この、9にち とあるのを見て、“ここのか と言うのは、子供には難しいんだ” と思った。

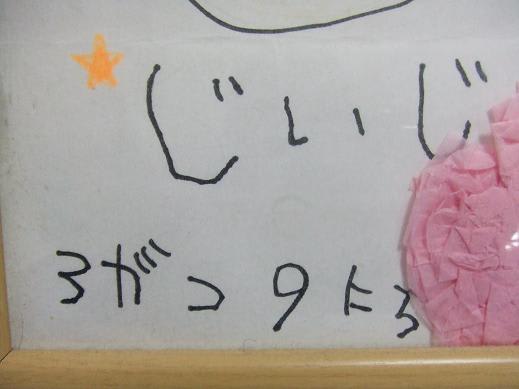
プロフィールの元絵 部分拡大
因みに、孫自身の誕生日は、
7がつ 21にち
なので、こちらは、なんら難しくは無い。
このことが、長い間、気になっていたのだが、今回漸くにして、当ブログで、日本語での、数に関する話題を、取り上げることとなったものである。
物の本や、ネット情報によれば、言語の中で、数に関する言葉は、「数詞」と言われるようだ。 数詞は、以下の様に、分類される。
基数詞 数え方の基本となる数詞 日本語の例 英語等の例
1 2 3 one two three
序数詞 順序を表す数詞 2等 第3位 first second third fourth
第25回 twenty-fifth
反復数詞 回数を表す数詞 3度 17回 once twice thrice
three-times
集合数詞 複数のものからなる 3人組 duo trio quintet
組を表す数詞
倍数詞 何倍であるかを表す数詞 2倍 五重 single double triple
soro duet
mono- di- bi- tri-
助数詞 数える時の単位となる言葉 家1軒 木5本 one house five trees
今回は、これらの中の、基数詞について、本稿で、触れることとしたい。
なお、序数詞、反復数詞、集合数詞、倍数詞については、例示の様に、日本語では、基数詞の1、2,3の前後に、
位、回、組、倍
等の助数詞を付けて言うので、専用の言葉はない。然るに、英語等では、
first , twice, trio, duet
など、全く別の専用の言葉が存在するのだが、これらについては、これ以上は触れない。
又、日本語の場合は、物を数える時に付ける、物の名前とは別の、専用の助数詞/接尾語があるので、厄介なのだが、英語等では、物の名前そのものを使うので簡単である。
この、助数詞/接尾語については、いずれ改めて、詳しく触れる予定である。
①数え方の基本ー基数詞
まず、数える時の基本となる基数詞について、述べて見たい。小学校1年の時、算数の時間に、
文字としての数字 例 4
言葉としての数詞(発音) 例 し
数の映像イメージ 例 ●●●●
の3つが、明確に区別できるように、子供たちに、教えるという。
現在の日本語では、1~10までは、以下の様になり、
数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
発音 イチ ニ サン シ ゴ ロク シチ ハチ ク・キュウ ジュウ
11以降については
数字 11 12 13 14 ------------
発音 ジュウイチ ジュウニ ジュウサン ジュウシ ------------
数字 21 ---- 41 ------- 71
発音 ニジュウイチ シジュウイチ シチジュウイチ
等となる。
このような数え方は、中国での、 漢数詞を基本とした数え方(以下漢式)に基づいてい
る。
表記する数字も、以前は、漢数字
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 --------
だったのだが、現在は、アラビア数字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 --------
が、基本となっている。
②日本古来の数え方
日本には、古来からある、やまとことば(原日本語)での、以下の様な数え方(和語の
数詞 以下和式)がある。
数字 1 2 3 4 5 6 7
発音1 ひい ふう みい よ い む なな
発音2 ひとつ ふたつ みっつ よっつ いつつ むっつ ななつ
みつ よつ いつ むつ
数字 8 9 10
発音1 や ここ とお
発音2 やっつ ここのつ とお
やつ
発音1と発音2の、語幹は同じで、発音2は、発音1に、数を表す、○○つ を付け
たもの、と言える。
11以上については、調査不十分だが、昔は、以下の様に数えたという。
17個=10(とお)とあまり7(ななつ)/10(とお)と7(ななつ)
13日=10日(とおか)あまり3日(みっか)
37年=30年(みそとせ)あまり7年(ななとせ)
このように、古来の和式では、桁ごとに助数詞を繰り返し、あまり をいれる等、かなり冗長である。
これに対し、漢式では、
17個=10(じゅう) 7(しち)個
13日=10(じゅう) 3(さん)日
37年=30(さんじゅう)7(しち)年
と、数字を桁ごとに、基数詞で読み、最後にまとめて、助数詞/接尾語を付ければいいので、合理的で、極めて簡潔である。このようなことから、桁の概念が入る、11以上についての、和式の数え方は使われなくなっている、のであろう。
先進文化圏であった中国から、後進国の日本に、漢語、漢字が伝わる以前の、日本の言葉(やまと言葉)がどのようなものであったかは、色んな研究や説があるようだ。
一説では、体系的な言葉は無かったとも言われ、仮名文字の発明等に見られるように、漢語、漢字の翻訳から、日本文化は始まった、という説もある位だ。当時の日本では、日常的に使う数詞としては、1~20位までしか無かった、とも言われている。