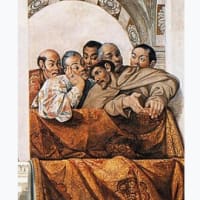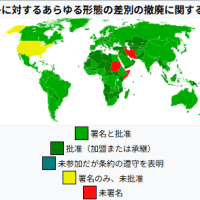2012年4月26日(木) 再びの桜花―おまけ 花より団子
先日から、当ブログに、下記記事を掲載してきたが
再びの桜花―その1 (2012/4/16)
再びの桜花―その2 (2012/4/23)
今回は、おまけ編の、花より団子 である。
□花より団子
江戸いろはかるた にある、「花より団子」は、7語で言いやすく、人心の機微を突いて、ズバリ、本音を表した、好きな言葉である。
衣食足りて、礼節を知る、と言われるように、人間誰しも、食い気が最も基本になるのは自然で、その後に、花を愛でる気持ち(花気?)や、色気も出て来るというものだろう。
 花見団子
花見団子
花見と言えば、一般には、団子や酒は付き物だが、
花も、団子も
という、欲張った AND形は、江戸時代頃からのスタイルだろうか。
靖国神社や上野公園で、桜の下に茣蓙を敷いて楽しんだ花見が、懐かしく思い出される。 職場の花見の場所取り担当になり、苦労した事もある。
花か、団子か、
と言う、OR形もある。 遠い昔は、風流に、花だけを見て、帰宅後、ゆっくりと、酒食を味わったのかもしれない。
最近の花見でも、場所によっては、スペースの関係から、桜の木の下の席取りはご法度で、立ち停まれず、止むを得ず、花だけとなることもある。都内では、皇居の堀に面した、千鳥ヶ淵公園がそうだし、八重桜が見事な、大阪造幣局の通り抜けもそうだ。
逆に、団子だけ、と言うのもある。以前、地域の仲間で、近くの道路脇の桜並木で花見をやった時は、初めは、桜の木の下にシートを敷いてやったのだが、狭いし、寒いので、2回目は、近くの住区センターの部屋の中になった。当然、花が無いので、桜の花のカレンダーを壁に下げてやったりしたが、それ以降は、結局、飲み会だけの花見になってしまった。 仲間には、年配の女性も多かったことから、姥桜の花見、などと冷やかしたりしたものだ。
最近の花見は、花の方は簡単に切り上げ、席を改めて、盛大に団子を楽しむことも、多いのではないか。
色んな行事にしても、次第に本来の意味が薄れて、花より団子で、以下のように、食い気だけが、しっかり残ることも多いようだ。
バレンタインデーのチョコ
クリスマスケーキ
節分の恵方巻
冬至のあずき南瓜
(月見の団子)
□江戸いろはかるた
花より団子 は、良く知られた、江戸いろはかるた の一枚だが、いろはかるた について、少しく調べて見た。
いろはかるたには、地域によって色々あるようだが、大きく
・江戸いろはかるた
・上方いろはかるた
になるようだ。
いろはかるたは、いろは 47文字に、京を加えて、48枚になっている。
子供の頃に親しんだ、江戸いろはかるた だが、現在で、どの位記憶しているものだろうかと、先日、48枚を、必死に思い出そうとして、2~3時間に亘って、記録してみた。これと、ネットで調べた正解(かるた - Wikipedia)と対比して見たら、以下のような結果になった。
記憶が合致していたもの 黒字
記憶が違っていたもの 青字
何も思い出せなかったもの 赤字
い ろ は に ほ へ と ち り ぬ る を
わ か よ た れ そ つ ね な ら む
う ゐ の お く や ま け ふ こ え て
あ さ き ゆ め み し ゑ ひ も せ す 京
記憶が違っていたもの(青字) は以下の2件である
1件は、
ア 屁をひって尻すぼめ
イ 下手の長談義
で、これは、アの、以前に覚えた表現が下品なことから、イに、差し替えられたようだ。
もう一つは
ア 月夜に釜を抜く
イ 月とすっぽん
だが、以前遊んだ かるたでは、アに、なっていたと思うが、これは、意味が難解なことから、イに、差し替えられたようだ。
どうしても、思い出せなかった赤字の9件は、以下の様になる。その中の、3件は、やや難しかった。
1件は、旧仮名遣いに関連する
良薬(れうやく)は口に苦し
で、もう2件は、濁点が付く
芸(げい)は身を助く
貧乏(びんぼう)暇なし
だったのである。
残る6件は、分って見れば、以下の様な、良く聞く言葉であった。
嘘から出たまこと
臭いものに蓋をする
亭主の好きな赤い烏帽子
頭隠して尻隠さず
急いては事を仕損じる
粋は身を食う
江戸いろはかるた を見ると、現在では、意味の良く分からない、以下の様な言葉もある。
かったいの瘡うらみ かったいとは?
総領の甚六 甚六さんとは?
芋の煮えたもご存じない 芋に特別な意味?
三遍回って煙草にしよ 何を三遍回る?
又、旧仮名遣いの関係で、現在は使われないものに、上述のものを含め、以下がある。
老(を)いては子に従え
良薬(れうやく)は口に苦し
芋(ゐも)のに煮えたもご存じない
縁(ゑん)は異なもの味なもの
又、江戸かるたを、上方かるた と比較すると、 共通なものは
下手の長談義
1件だけ、と言うのは面白い。長い歴史があり、文化の中心である上方の、向こうを張るように、敢えて、異なる言葉を採用した、江戸人の、心意気のようなものが感じられる。
上方かるた には、歴史の中で人口に膾炙したのだろうか、江戸かるた とは異なるものの、意味のわかる、良く聞く言葉が多い。よく聞く言葉と、あまり聞かない言葉とに分けてみると、以下の様になる。(区分は自分の主観)
良く聞く言葉 31
あまり聞かない言葉 17 (自分は、意味も良く知らない)
最近は、遊びとしての いろはかるた はどうなっているのだろうか。子供達は、今も楽しんでいるだろうか。
いろはかるた は、自分が子供の頃は、そのまま、調子で覚えたものだが、大人になって改めて見て見ると、人生の中での、処世上の知恵(悪知恵も)が一杯に詰まった、名言集・箴言集と言えよう。 でも、余りに教訓的過ぎて、遊びが無く、大いに疲れる!
今後は、「花より団子」は、桜と花見がある限り、無くならないと思われるものの、多くの言葉・諺が、徐々に、死語になってしまうのかも知れない。 でも、「老いては子に従え」で、時代と共に生きて行く、こととなるだろうか。