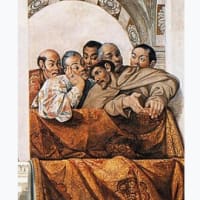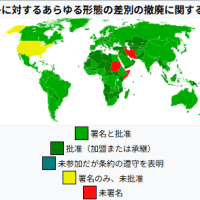2010年8月01日(日) 日本語の表記 その1 駅名はわかりやすい?
日本語の発音や表記については、長年、関心を持ってきたところだが、最近、現代仮名遣いや、ローマ字表記等に関して、いくつか気になることもあり、自分もやや混乱している。このため、自分なりに整理する手掛かりを得るため、まず、交通機関の駅名の表記について、取り上げることとした。
手始めに、日頃、身近に利用している地下鉄千代田線の各駅と、千代田線に相互に乗り入れしている、小田急線、JR常磐線の近郊の各駅を中心に、漢字名、ひらがな名、ローマ字名について、改めて調べてみた。
地下鉄千代田線の各駅の駅名は、以下のようになっている。
漢字名 ひらがな名 ローマ字名
代々木上原 よよぎうえはら Yoyogi―uehara
代々木公園 よよぎこうえん Yoyogi―koen
明治神宮前 めいじじんぐうまえ Meiji―jingumae
表参道 おもてさんどう Omote―sando
乃木坂 のぎざか Nogizaka
赤坂 あかさか Akasaka
国会議事堂前 こっかいぎじどうまえ Kokkai―gijidomae
霞が関 かすみがせき Kasumigaseki
日比谷 ひびや Hibiya
二重橋前 にじゅうばしまえ Nijubashimae
大手町 おおてまち Otemachi

新お茶の水 しんおちゃのみず Shin―ochanomizu
湯島 ゆしま Yushima
根津 ねづ Nezu

千駄木 せんだぎ Sendagi
西日暮里 にしにっぽり Nishi―nippori
町屋 まちや Machiya
北千住 きたせんじゅ Kita―senju
綾瀬 あやせ Ayase
北綾瀬 きたあやせ Kita―ayase
おもな特徴としては、ひらがな名では、長音は、こう、ぐう、じゅう、おお、などと、なっている。また、根津は、ねず、でなく、ねづ、になっていることだ。
一方、ローマ字名では、長音の符号(マクロン:macron と呼ぶ)は使用しておらず、しはshi、ちはchi、と表記している。
長音が入る駅は6つあるが、マクロン不使用ということで、この駅名を、短音的に読むと
Yoyogi―koen 小苑?
Meiji―jingumae 神具?
Omote―sando 酸度、三度?
Kokkai―gijidomae 疑似度?
Nijubashimae 二儒?
Otemachi お手町?
などと、やや変に聞こえるが、決定的な紛らわしさはない。逆に、oをすべて長音的に読んで
Yoyogi―koen ヨーヨーギ コーエン
Omote―sando オーモーテ サンドー
などとなっても、意味は通じるようだ。
千代田線と相互乗り入れしている、小田急線について、乗り入れ駅の代々木上原から本厚木までの近郊区間について調べてみると、主なものは、以下のようになる。
東北沢 ひがしきたざわ Higashi―Kitazawa
豪徳寺 ごうとくじ Gotokuji
経堂 きょうどう Kyodo
成城学園前 せいじょうがくえんまえ Seijogakuem-mae
向丘遊園 むこうがおかゆうえん Mukogaokayuen
新百合丘 しんゆりがおか Shin―Yurigaoka
相模大野 さがみおおの Sagami-Ono

小田急相模原 おだきゅうさがみはら Odakyu―Sagamihara
相武台前 そうぶだいまえ Sobudaimae
厚木 あつぎ Atsugi
本厚木 ほんあつぎ Hon―Atsugi
おもな特徴は、ひらがな名では、長音の表記は、ごう、ゆう、おおなど、千代田線と同じである。
ローマ字名では、長音は、 マクロンを使っておらず、千代田線と同じである。一方、しはshi、で、撥音の、ん、は、gakuem―maeと、mになっている。
又、千代田線が、もう一方で相互乗り入れしている、JR常磐線の、綾瀬から先の取手までの近郊の駅名では、主なものは以下である。
金町 かなまち Kanamachi
松戸 まつど Matsudo
馬橋 まばし Mabashi
新松戸 しんまつど Shim―Matsudo
柏 かしわ Kashiwa
天王台 てんのうだい Tennōdai
おもな特徴は、ひらがな名では、長音の表記などは、千代田線、小田急線と同じである。ローマ字名では、長音はマクロン(ōなどの、文字上の横棒)を使用しているのが、大きな特徴だ。一方、しはshi、つは、tsuになっており、撥音は、shim-matsudoと、mになるなど、千代田線、小田急線と同じである。
これらの駅名の根拠となっている、規則類について調べた。ひらがな名については、現代仮名遣い(昭和61年(1986年)7月 内閣告示第一号)に準拠している。すなわち、根津駅のひらがな名は、根の後の津は、元字のつに、濁点のづ、という、二語が連合した場合の、現代仮名遣いのルールに則っている。
長音については、通常は、公園:こうえんのこう、神宮:じんぐうのぐう、などと、うを添えている。例外的な、大手町、相模大野などの場合は(旧仮名遣いでは、おほ、で、は行転呼音と言うようだ)、おお、と、おを添えていて、これも、例外のルール通りだ。
一方、ローマ字名については、出来るだけ、発音に近付けることが基本となっている、ヘボン式によることとしている、旧国鉄の鉄道掲示規程を、私鉄なども準用しているようだが、最大のポイントは、長音の表示だ。ヘボン式では、マクロンを使用することとなっており、JRや多くの私鉄もこれに従っている。
マクロンがあると、発音はしやすいのだが、文字入力が面倒である。本文書の作成でも、マクロン付きの文字は、IMEパッドで、沢山の文字の中から、選んで入力することとなり、又、フォント種別も任意ではないので、厄介である。
マクロンを使わないへボン式を採用しているのは、地下鉄と小田急である。
更に、千代田線と繋がっていて、比較的に乗る機会の多い
JR 山手線、京浜東北線、中央線、総武線
地下鉄 日比谷線 銀座線 半蔵門線
東武 伊勢崎線
の各駅についても、近郊について、ネット上で、概略、調査した。
これらの調査結果も含めて整理すると、以下のようになる。
ひらがな名 地下鉄、JR、小田急、東武とも同じで、現代仮名遣いに準拠
お列長音の表示 うを付加 よよぎこうえん おうじ
じんぐうまえ
おを付加 おおてまち おおつか
二語の連合 ねづ つきじ(連結前からの濁音で、じ)
ローマ字名 ヘボン式が基本である。
長音の表示では、マクロンを使用する方式と、マクロンを使用しない方式 に分かれる
マクロン使用 JR、東武
Tōkyō
Tōbu―dōbutsukōen
マクロン不使用 地下鉄 小田急
Otemachi Ningyocyo
Sagami―Ono
さ行、た行 他 JR、小田急、東武、地下鉄とも同じで、
shi chi tsu cyo 等と表記
撥音は、nだが、m、b、pの前ではm
長音に関しては、以前は、地下鉄もマクロンを使っていたが、民営化後に、マクロンを使わない方向に、変えたようである。又、マクロンを使わないヘボン式は、外務省のパスポート用などにも、採用されている。
日本語の固有名詞のローマ字表記は、英語表現と見ることができる。これは、日本人向けというより(難解な地名などは、ローマ字で読み方がわかって助かる時もあるが)、外国人向けと考えると、長音と短音の区別が明確になっている、マクロン付きの方がいい、ように思われる。
ただ、今後は、ネット利用などで、駅名の入力など、キーボード入力が多くなることを考えると、マクロン付きは、かなり厄介な問題である。日本語ワープロ用として、マクロン付きの母音を入力する方法が必要かも知れない。手持ちのキーボードには、そのようなキーは見当たらず、前述のように、面倒を覚悟で、ソフトキーボードのIMEパッドで入力することとなる。
地下鉄や小田急線の例にあるように、マクロンを使わない表示だと、発音も不自然になり、Onoでは、大野も小野も、同じになってしまうのは、問題があり、特に、人名になると、本人にしてみれば重大である。
長音を含む、大野を、マクロンを使わないで表示する方法としては、何もしないOnoの他に、
Oを重ねる:Oono
Hを入れる:Ohno
Uを入れる:Ouno
などが考えられ、使用例も見受けられるが、これらについては、次回以降で触れる予定である。
日本語の発音や表記については、長年、関心を持ってきたところだが、最近、現代仮名遣いや、ローマ字表記等に関して、いくつか気になることもあり、自分もやや混乱している。このため、自分なりに整理する手掛かりを得るため、まず、交通機関の駅名の表記について、取り上げることとした。
手始めに、日頃、身近に利用している地下鉄千代田線の各駅と、千代田線に相互に乗り入れしている、小田急線、JR常磐線の近郊の各駅を中心に、漢字名、ひらがな名、ローマ字名について、改めて調べてみた。
地下鉄千代田線の各駅の駅名は、以下のようになっている。
漢字名 ひらがな名 ローマ字名
代々木上原 よよぎうえはら Yoyogi―uehara
代々木公園 よよぎこうえん Yoyogi―koen
明治神宮前 めいじじんぐうまえ Meiji―jingumae
表参道 おもてさんどう Omote―sando
乃木坂 のぎざか Nogizaka
赤坂 あかさか Akasaka
国会議事堂前 こっかいぎじどうまえ Kokkai―gijidomae
霞が関 かすみがせき Kasumigaseki
日比谷 ひびや Hibiya
二重橋前 にじゅうばしまえ Nijubashimae
大手町 おおてまち Otemachi

新お茶の水 しんおちゃのみず Shin―ochanomizu
湯島 ゆしま Yushima
根津 ねづ Nezu

千駄木 せんだぎ Sendagi
西日暮里 にしにっぽり Nishi―nippori
町屋 まちや Machiya
北千住 きたせんじゅ Kita―senju
綾瀬 あやせ Ayase
北綾瀬 きたあやせ Kita―ayase
おもな特徴としては、ひらがな名では、長音は、こう、ぐう、じゅう、おお、などと、なっている。また、根津は、ねず、でなく、ねづ、になっていることだ。
一方、ローマ字名では、長音の符号(マクロン:macron と呼ぶ)は使用しておらず、しはshi、ちはchi、と表記している。
長音が入る駅は6つあるが、マクロン不使用ということで、この駅名を、短音的に読むと
Yoyogi―koen 小苑?
Meiji―jingumae 神具?
Omote―sando 酸度、三度?
Kokkai―gijidomae 疑似度?
Nijubashimae 二儒?
Otemachi お手町?
などと、やや変に聞こえるが、決定的な紛らわしさはない。逆に、oをすべて長音的に読んで
Yoyogi―koen ヨーヨーギ コーエン
Omote―sando オーモーテ サンドー
などとなっても、意味は通じるようだ。
千代田線と相互乗り入れしている、小田急線について、乗り入れ駅の代々木上原から本厚木までの近郊区間について調べてみると、主なものは、以下のようになる。
東北沢 ひがしきたざわ Higashi―Kitazawa
豪徳寺 ごうとくじ Gotokuji
経堂 きょうどう Kyodo
成城学園前 せいじょうがくえんまえ Seijogakuem-mae
向丘遊園 むこうがおかゆうえん Mukogaokayuen
新百合丘 しんゆりがおか Shin―Yurigaoka
相模大野 さがみおおの Sagami-Ono

小田急相模原 おだきゅうさがみはら Odakyu―Sagamihara
相武台前 そうぶだいまえ Sobudaimae
厚木 あつぎ Atsugi
本厚木 ほんあつぎ Hon―Atsugi
おもな特徴は、ひらがな名では、長音の表記は、ごう、ゆう、おおなど、千代田線と同じである。
ローマ字名では、長音は、 マクロンを使っておらず、千代田線と同じである。一方、しはshi、で、撥音の、ん、は、gakuem―maeと、mになっている。
又、千代田線が、もう一方で相互乗り入れしている、JR常磐線の、綾瀬から先の取手までの近郊の駅名では、主なものは以下である。
金町 かなまち Kanamachi
松戸 まつど Matsudo
馬橋 まばし Mabashi
新松戸 しんまつど Shim―Matsudo
柏 かしわ Kashiwa
天王台 てんのうだい Tennōdai
おもな特徴は、ひらがな名では、長音の表記などは、千代田線、小田急線と同じである。ローマ字名では、長音はマクロン(ōなどの、文字上の横棒)を使用しているのが、大きな特徴だ。一方、しはshi、つは、tsuになっており、撥音は、shim-matsudoと、mになるなど、千代田線、小田急線と同じである。
これらの駅名の根拠となっている、規則類について調べた。ひらがな名については、現代仮名遣い(昭和61年(1986年)7月 内閣告示第一号)に準拠している。すなわち、根津駅のひらがな名は、根の後の津は、元字のつに、濁点のづ、という、二語が連合した場合の、現代仮名遣いのルールに則っている。
長音については、通常は、公園:こうえんのこう、神宮:じんぐうのぐう、などと、うを添えている。例外的な、大手町、相模大野などの場合は(旧仮名遣いでは、おほ、で、は行転呼音と言うようだ)、おお、と、おを添えていて、これも、例外のルール通りだ。
一方、ローマ字名については、出来るだけ、発音に近付けることが基本となっている、ヘボン式によることとしている、旧国鉄の鉄道掲示規程を、私鉄なども準用しているようだが、最大のポイントは、長音の表示だ。ヘボン式では、マクロンを使用することとなっており、JRや多くの私鉄もこれに従っている。
マクロンがあると、発音はしやすいのだが、文字入力が面倒である。本文書の作成でも、マクロン付きの文字は、IMEパッドで、沢山の文字の中から、選んで入力することとなり、又、フォント種別も任意ではないので、厄介である。
マクロンを使わないへボン式を採用しているのは、地下鉄と小田急である。
更に、千代田線と繋がっていて、比較的に乗る機会の多い
JR 山手線、京浜東北線、中央線、総武線
地下鉄 日比谷線 銀座線 半蔵門線
東武 伊勢崎線
の各駅についても、近郊について、ネット上で、概略、調査した。
これらの調査結果も含めて整理すると、以下のようになる。
ひらがな名 地下鉄、JR、小田急、東武とも同じで、現代仮名遣いに準拠
お列長音の表示 うを付加 よよぎこうえん おうじ
じんぐうまえ
おを付加 おおてまち おおつか
二語の連合 ねづ つきじ(連結前からの濁音で、じ)
ローマ字名 ヘボン式が基本である。
長音の表示では、マクロンを使用する方式と、マクロンを使用しない方式 に分かれる
マクロン使用 JR、東武
Tōkyō
Tōbu―dōbutsukōen
マクロン不使用 地下鉄 小田急
Otemachi Ningyocyo
Sagami―Ono
さ行、た行 他 JR、小田急、東武、地下鉄とも同じで、
shi chi tsu cyo 等と表記
撥音は、nだが、m、b、pの前ではm
長音に関しては、以前は、地下鉄もマクロンを使っていたが、民営化後に、マクロンを使わない方向に、変えたようである。又、マクロンを使わないヘボン式は、外務省のパスポート用などにも、採用されている。
日本語の固有名詞のローマ字表記は、英語表現と見ることができる。これは、日本人向けというより(難解な地名などは、ローマ字で読み方がわかって助かる時もあるが)、外国人向けと考えると、長音と短音の区別が明確になっている、マクロン付きの方がいい、ように思われる。
ただ、今後は、ネット利用などで、駅名の入力など、キーボード入力が多くなることを考えると、マクロン付きは、かなり厄介な問題である。日本語ワープロ用として、マクロン付きの母音を入力する方法が必要かも知れない。手持ちのキーボードには、そのようなキーは見当たらず、前述のように、面倒を覚悟で、ソフトキーボードのIMEパッドで入力することとなる。
地下鉄や小田急線の例にあるように、マクロンを使わない表示だと、発音も不自然になり、Onoでは、大野も小野も、同じになってしまうのは、問題があり、特に、人名になると、本人にしてみれば重大である。
長音を含む、大野を、マクロンを使わないで表示する方法としては、何もしないOnoの他に、
Oを重ねる:Oono
Hを入れる:Ohno
Uを入れる:Ouno
などが考えられ、使用例も見受けられるが、これらについては、次回以降で触れる予定である。