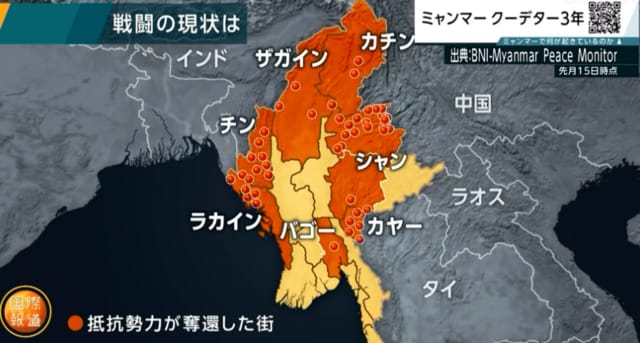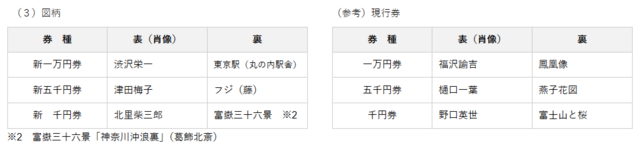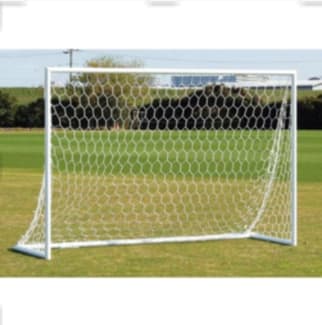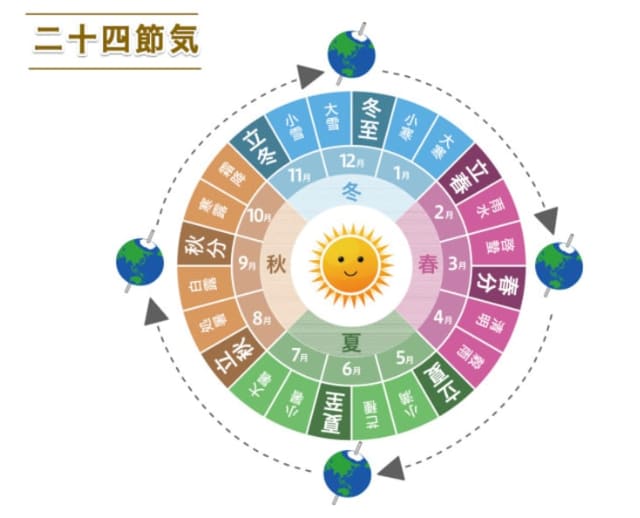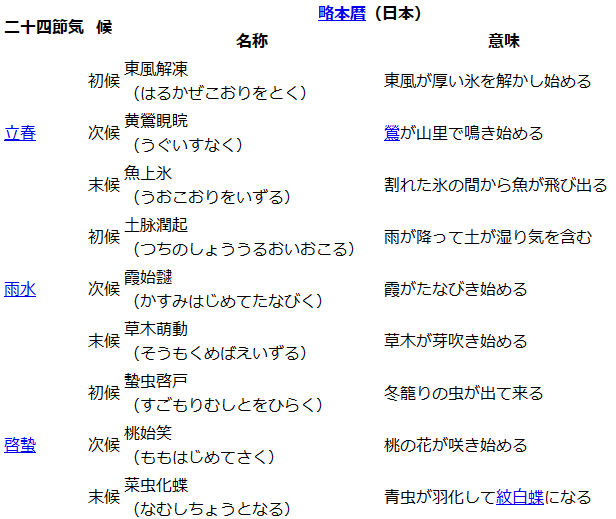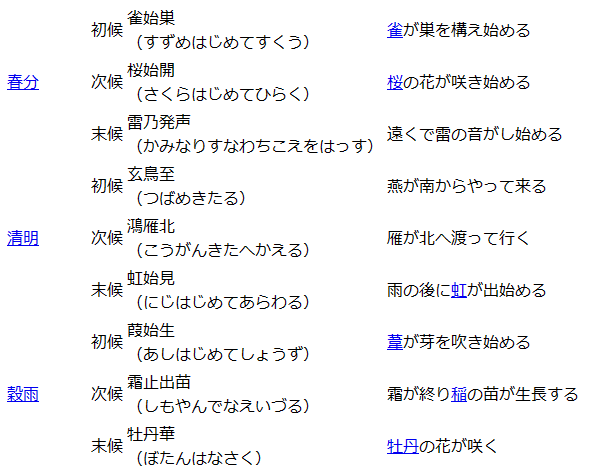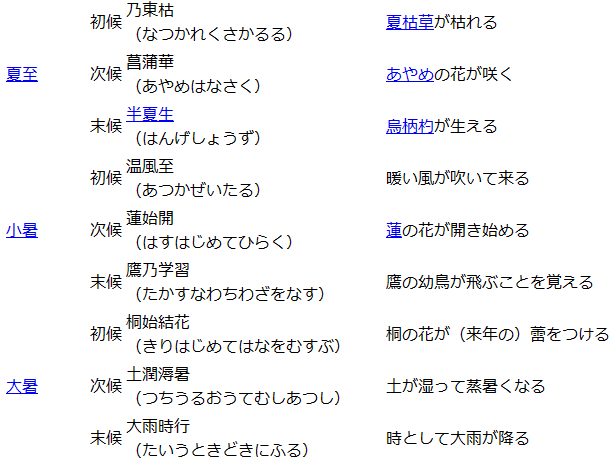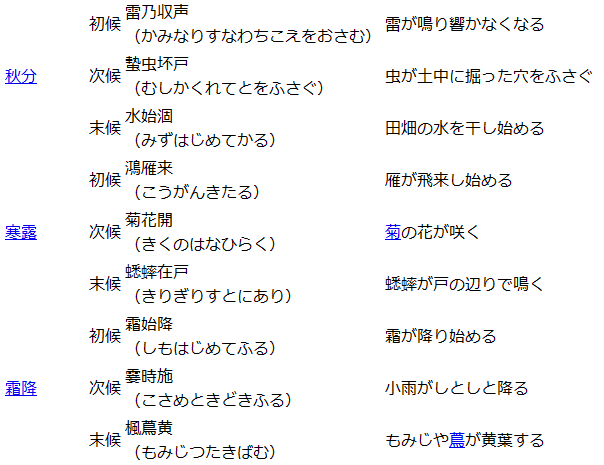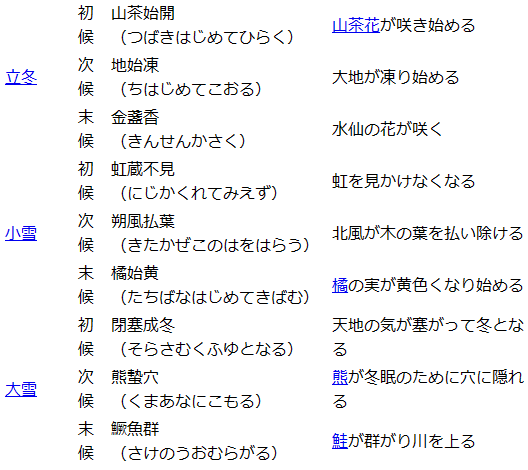2024年4月13日(土) ハンセン病のこと
先日、TVを観ていたら、ハンセン病についての意識調査結果が報道された。
本稿は、この病について、記してみたい。
◉意識調査
厚労省が、ハンセン病について、初めての意識調査を行い、この4月に結果を公表した。
・調査方法: 対象者 インターネット利用者で、約21000人から回答
期間 2023年11月から2024年3月まで
・調査結果 :西日本新聞のサイトに、調査結果が、下図のように、グラフにして示されているので、引用させて貰
う。
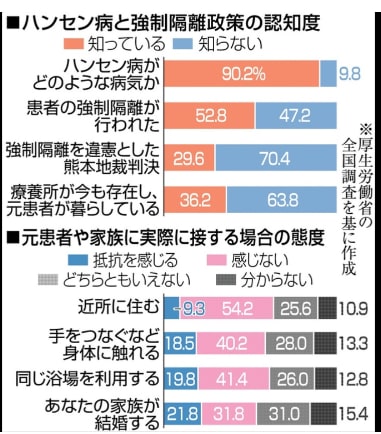
*図の、上段には、ハンセン病について、90%の人が知っているとある。
また、後述する政府の隔離政策や現在の療養所について知っているか、を問うたものである。
*図の下段では、どのような意識を持っているか問うている。
患者と体が触れること、同じ浴場を利用すること、でかなりの抵抗を感じるとある。
家族の結婚相手となると、感じない人が多いものの、どちらとも言えないや、分からないなど、更に、抵抗感が増す
ようだ。
◉病の原因と治療
・癩(らい)菌という病原菌による、弱い感染症とされる。この菌を発見したのが、スエーデンの医学者A,ハンセン
で、1873年のことという。
発見者の名を冠して、ハンセン病という病名になっている。
・病名: 日本では、癩病という呼称は、差別的用語として忌避され、ハンセン病という病名にしている。外国では、レ
プラ(lepra leprosy)と呼ぶ。
・5段階にわけられる、身体的変形が有るようだ。
(参照:ハンセン病 - Wikipedia.html)
我が国では、古来、患者は、かったい(癩)等と呼ばれたようだ。
諺に 「かったいのかさうらみ」 と言うのがあるが、ここでの「かさ」(瘡)とは、梅毒により顔面が変形した人のことで、諺の意味は、些細な違いをみて羨むことという。
・最近の感染者数
世界では、まだ各地感染者数はいるようだが。日本国内では、1桁ほどという。
・病気の治療の進歩で、最近は治る病気と言われている。
◉社会的な位置づけの変遷
・癩予防法の成立と廃止
1931(S31)成立 理由:国の隔離政策で、終戦後の結核と同じ
1996(H8) 廃止 理由:国が政策の誤りを認める
患者の隔離が主で、患者への配慮が不十分だった。
・患者の救済制度
2019年11月、救済金と名誉の回復のための法律が公布された。
◉筆者が生れた地域での様子
終戦前の山形の田舎のとだが、病気がうつると恐れられ、周囲が、敬遠・忌避していた。
◉施設訪問
・場所:東京の西の方角という記憶しかないが、現在、東村山市にある施設:国立全生園(下図)と思われる。
・時期 かなり以前
・メンバーは、琴の先生と当方夫婦の3人が訪問
筆者が運転するマイカーで琴を運搬(3人が同乗)
・お琴の先生と筆者の尺八とで合奏
曲目は覚えていない
・施設訪問のきっかけ 今となっては、はっきりしない。
この訪問前に、筆者がそちらの施設に行ったことがあるかも知れない?