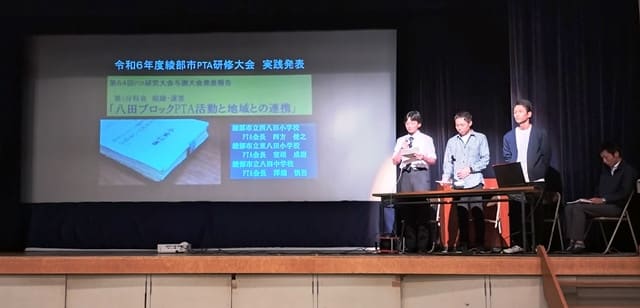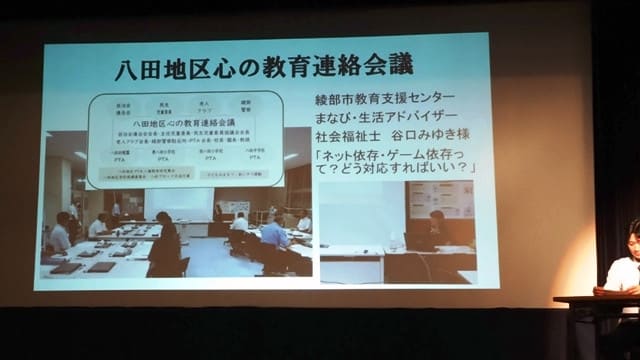9日㈬、9時半から京都府立綾部高等学校(一井育校長)の入学式に出席。次男・温二郎も綾部高校・普通科に入学した。

綾部高校の体育館には、温二郎は入学生として、涼子は吹奏楽部員として、妻は保護者として、私は来賓として、それぞれ立場は違えど家族4人が集合していた。
「せっかくだから、小源太も帰らせたら良かったな」と言うと、「小源太はもう学校始まっとる」とのことだった。

一井校長は式辞で「人間の味(あじ)」という例えを使って、綾部高校の校訓である「探真究理」を新入生に説明された。
AI時代になって、計算したり、文章を書いたり、絵を描くのは、人間よりもコンピュータが優れているように思うかもしれないが、文章や絵を見てどう感じるか、その人間としての共感が「人間の味」となる。
マルチタスクよりも、綾部高校で好きなことに熱中して深い学びを得てほしい。自分の身体で得て、自分の頭で考え、自分の言葉で話せる人になってほしい、と。
■綾部高校の校訓「探真究理」
「探真究理」という言葉は、明治26年に開校した綾部高校(当時は京都府蚕糸業組合立高等養蚕伝習所)の初代所長(校長)である波多野鶴吉(グンゼ創業者)の造語だろうか。東京農大附属第三中学・高校に「究理探新」という似た言葉があるが、他には見当たらない。
「探真究理」は「真理」と「探究」を組み合わせた言葉だろう。「真理」を「探究」し、読み書きするだけでなく、自ら体得することの重要性を言わんとしているのではないだろうか?
それは綾部高校が創立以来、大切にしている「実学」(現実に役立つ学び)に通じるように思う。偏差値の高い大学を目指すのはもちろん良いことだが、多様な人と交わり、「実学」を身につけることも良いことだ。
「探真究理」を目標とする綾部高校では、柔軟で強靭な人格、人脈を形成し、社会での対応力が高い人材を育てていただきたい。
式の後で一井校長が「綾部高校は志願者数が多いことに甘んじていてはいけない。上位層の学力を伸ばすことがまだまだできていない。この現実を直視し、学校本来の使命である学力向上にもっと真剣に取り組もう!」と「熱量」をテーマに教職員を鼓舞しているとおっしゃっていた。
私も全く同感であり、その危機意識を校長先生が持っていただいていることに、逆に安心した。
■「福知山高校、定員割れなぜ?」京都新聞の記事
先日の京都新聞に「福知山高校、定員割れなぜ?」という記事が掲載されていた。
福知山高校は直近10年で8年定員割れしており、記事は「2025年度は2割超の定員割れ」との見出しで、その原因としては「少子化」と「私学との競合」を挙げているが、それは見方が甘い。
福知山高校の進学実績は中丹で群を抜いているが、難関大学に進学できる生徒は全体の1割もいないだろうし、そういう生徒の絶対数が年々減っていると感じる。
難関大学を目指す生徒の数に対して、福知山高校の定員が多いことが定員割れしている主因であり、福知山高校を中高一貫校にした時に文理科学科の改廃や普通科定員の見直しをしなかった結果、というだけのこと。
その頃は綾部高校の志願者数がもっと減るとの想定があったのだろう。想定に反して綾部高校の志願者数が多くなっているのは誤算だったかもしれない。
少子化や私学との競合だけに「福知山高校の定員割れ」の結論を持っていくのは、京都新聞記者の貧弱な取材、考察不足だと言わざるを得ないだろう。
私学と競合しているのは福知山高校に限ったことではなく、綾部高校や西舞鶴高校はじめ、府内の公立高校全体が影響を受けている。
勉強も、部活も、遊びも、バイトも、バランスよくやりたい子が全体の7~8割ほどいて、その「ボリュームゾーン」の生徒を綾部高校と私学が共にターゲットにして引っ張り合いをしているのが現状だと思う。

校長挨拶の後は、今年度の田中雄作PTA会長の挨拶。
10年ほど前、私が綾部小学校PTA会長だった時に、次の年のPTA役員をお願いし、それ以降、綾部小学校、綾部中学校でPTA会長や役員を歴任してもらってきた。
■府立農大の入学式にも
12時半からは京都府立農業大学校(稲田佳奈校長)の入学式に出席。16名の新入生が入学された。京丹後市、舞鶴市という北部からの入学生は3名、京都市、長岡京市、京田辺市、宇治市、城陽市、精華町など南部から12名、大阪府からも1名入学された。

河村能夫名誉校長の挨拶では「実習」「実学」の大切さを説いておられた。
続いて、知事代理の小瀬康行農林水産部長、府議会議長代理の林正樹副議長、山崎善也綾部市長が来賓挨拶をされ、「農業の未来は明るい」と京都府農業を担う若き農業者を激励された。
農商工労働常任委員会(森口亨委員長)からも多くの委員に出席していただいており、ありがとうございました。
新入生の皆さんには綾部を「第二のふるさと」として、ここで将来の夢に向けた良い学び、経験、出会いがあることを願っています。