(承前)
前回述べたとおり、日本共産党の六全協(第6回全国協議会)の決議は、「極左冒険主義」を「戦術上の」誤りとし、「はっきり手をきる」としたが、武装闘争路線を導いた51年綱領については、否定するどころか「すべての規定が、完全に正しい」とし、この綱領を実現することが党の任務だとするものだった。
ところで、先日の、共産党は破防法の調査対象であると述べた政府の答弁書を批判したしんぶん赤旗の記事「「議会の多数を得ての革命」の路線は明瞭/政府の「暴力革命」答弁書は悪質なデマ 」にはこうあった(太字は引用者による。以下同じ)。
では、六全協から3年後の1958年に開かれた第7回党大会では、武装闘争路線は「明確に批判され、きっぱり否定された」のだろうか。
第7回党大会に関する文書を確認してみた。
「日本共産党第7回大会にたいする中央委員会の政治報告」という文書がある。報告者は野坂参三第一書記であるが、「中央委員会の政治報告」とあるから中央委員会で承認されたものだし、この報告は党大会で採択されたので、「党が統一を回復したさい」の党の正式な見解である。
この報告は、いわゆる50年分裂後の情勢について、次のように説明している(〔 〕内は引用者による註。以下同じ)。
五全協を、分裂状態が実質的に解決していないとしながらも、「ともかくも一本化された党の会議であった」と評価している。
私はこれまで、前回の記事で引用した不破哲三氏の発言のように、四全協も五全協も共に「分裂した一方の側の会議」だと思っていたが、どうも違うようだ。
調べてみると、この1951年には、四全協後に「国際派」の志賀義雄が自己批判して主流派に復帰したり、「所感派」である北京の徳田球一や臨中議長の椎野悦朗が自己批判したり、「国際派」が分裂したり、徳田(所感派)と袴田里見(国際派)がモスクワに赴き、スターリンが徳田を支持して袴田は自己批判し主流派入りするといったさまざまな出来事があり、単純な分裂ではなく、複雑な状態であったらしい。
特に、政治報告も触れているモスクワ放送でソ連の徳田支持が明確になってからは、「国際派」は腰砕けとなり、主流派への復帰への動きが進んだらしい。
だから、五全協を「ともかくも一本化された党の会議であった」と表現しているのだろう。
ならば、五全協で決定された51年綱領に基づく武装闘争路線については、「分裂した時期の一方の側の行動」として切り捨ててはいられないはずだが……。
前回の記事でも述べたように、平成元年2月18日の衆議院予算委員会での石山陽・公安調査庁長官の答弁には、
とあり、不破氏に否定されているのだが、この「全体としては、これは当時の主流派、反主流派によって十分意見の統一によって行われたもの」というのは、もしかすると、この第7回党大会の政治報告と六全協の決議を混同していたのかもしれない。
さて、中央委員会の政治報告はこう続く。
続いて、誤りの原因を多々並べ立て、中でも徳田球一による家父長的個人指導を強調し、伊藤律、志田重男、椎野悦朗といった指導者を名指しで批判している。
しかし、その誤りの具体的な内容には触れていない。軍事方針や武装闘争、山村工作隊や中核自衛隊、火炎びん闘争といった言葉は全く出てこない。
そして、51年綱領については、
と、六全協とはうってかわって誤りがあったことを認め、これに変わる「党章」草案を呈示するとしている。
この「党章」とは、綱領と規約を合わせたもので、この第7回党大会後に書記長に選出される宮本顕治の主導により草案が作成され、既に前年に公表されていた。
宮本らは、この党大会での採択を図ったが、中央に春日庄次郎ら少数の反対派がおり、大会でも代議員の3分の2以上の賛成が得られなかったため、規約のみを決定し、綱領については持ち越しとなった。
では、この大会で 宮本は 51年綱領についてどう述べていたのだろうか。
先の文書の引用元である『日本共産党事典(資料編)』には、この大会での宮本による綱領問題についての報告も収録されているのだが、一部しか収録されていない。
ネットで検索してみると、「日本共産党資料館」なるサイト(党内異論派のサイト「さざ波通信」と関係があるようだ)に、この宮本による報告の大部分が掲載されていた。
「綱領問題についての中央委員会の報告(1)」というページから引用する。
51年綱領は「一つの重要な歴史的な役割を果した」と評価しながらも「誤りと欠陥をもっていた」から「再検討が必要であ」り、「新しい綱領の方向を提示」するとしている。
ここでも「誤りと欠陥」によって何がもたらされたかには触れていない。
軍事方針とか武装闘争路線といった言葉も出てこない。
では、言葉にしないまでも、失敗に終わった武装闘争路線はもう採らず、議会で多数派を得て平和革命を目指すのか。
宮本はそうは言わない。
この報告の中に、次のような記述がある。
暴力革命不可避論も正しくないが、平和革命必然論もまた正しくないとしている。
これが、今回の政府答弁書でも問題となった、いわゆる「敵の出方論」のルーツである。
「敵の出方論」とは元々このようなものであり、暴力のみを否定し、平和的手段のみをも否定する折衷的な見解であって、以前引用した国会質問で不破氏が述べていたような、反共クーデターといった事態のみを想定したものではない。
「反動勢力が弾圧機関を武器として人民闘争の非流血的な前進を不可能にする措置に出た場合」
「米日反動勢力が非道な挑発、暴力的な手段をもって抵抗する可能性」
「民主勢力がまだ強大にならないうちに、暴圧を加える可能性」
というが、「措置」「挑発」「暴力的な手段」「暴圧」とは具体的に何を意味するのか、明確でない。
例えば、共産党が非合法活動を行っていて、それに対して警察が動いたり、管轄する行政当局が指導を行ったりすることも、「措置」「挑発」「暴圧」に当たると判断されたりはしないだろうか。
今回問題になった、公安調査庁が共産党を調査対象としていることはどうか。
「敵の出方」は共産党側の「出方」によっても左右されるはずだが、共産党側がまずは常に合法的活動の枠内にとどまると宣言していないのは何故だろうか。
そして、しんぶん赤旗の記事が述べていたように、これで武装闘争路線を「第7回党大会で党が統一を回復したさいに明確に批判され、きっぱり否定された問題」だと言えるのだろうか。
軍事方針とか武装闘争路線といった言葉を用いていないのに、何を明確に批判しきっぱり否定したというのだろうか。
51年綱領自体についても、意義を認めているではないか。
51年綱領を「分裂した時期の一方の側の行動」だとして全否定するのは、宮本体制が確立したもっと後のことではないか。
なのに、しんぶん赤旗の記事は、第7回党大会から一貫して全否定しているかのように語っている。
以前にも述べたが、「歴史の事実を歪曲」しているのは誰なのだろうか。
なお、綱領論争はこの第7回党大会後も続き、結局春日庄次郎ら綱領反対派は排除され、1961年の第8回党大会では綱領草案は満場一致で決定された。
この時の綱領が、基本的には現在まで続いている。
(続く)
前回述べたとおり、日本共産党の六全協(第6回全国協議会)の決議は、「極左冒険主義」を「戦術上の」誤りとし、「はっきり手をきる」としたが、武装闘争路線を導いた51年綱領については、否定するどころか「すべての規定が、完全に正しい」とし、この綱領を実現することが党の任務だとするものだった。
ところで、先日の、共産党は破防法の調査対象であると述べた政府の答弁書を批判したしんぶん赤旗の記事「「議会の多数を得ての革命」の路線は明瞭/政府の「暴力革命」答弁書は悪質なデマ 」にはこうあった(太字は引用者による。以下同じ)。
1950年から55年にかけて、徳田球一、野坂参三らによって日本共産党中央委員会が解体され党が分裂した時代に、中国に亡命した徳田・野坂派が、旧ソ連や中国の言いなりになって外国仕込みの武装闘争路線を日本に持ち込んだことがあります。
しかし、それは党が分裂した時期の一方の側の行動であって、1958年の第7回党大会で党が統一を回復したさいに明確に批判され、きっぱり否定された問題です。
では、六全協から3年後の1958年に開かれた第7回党大会では、武装闘争路線は「明確に批判され、きっぱり否定された」のだろうか。
第7回党大会に関する文書を確認してみた。
「日本共産党第7回大会にたいする中央委員会の政治報告」という文書がある。報告者は野坂参三第一書記であるが、「中央委員会の政治報告」とあるから中央委員会で承認されたものだし、この報告は党大会で採択されたので、「党が統一を回復したさい」の党の正式な見解である。
この報告は、いわゆる50年分裂後の情勢について、次のように説明している(〔 〕内は引用者による註。以下同じ)。
一九五〇年一月初めに、「恒久平和のために、人民民主主義のために」紙〔コミンフォルム――ソ連とヨーロッパの共産党の国際組織――の機関紙〕上に「日本の情勢について」という論評が発表された。それはこれまでのわが党の指導方針のなかにあった右翼日和見主義的傾向にたいする適切な批評であり、助言であった〔共産党幹部野坂参三の、米軍を解放軍とし、占領下における平和革命を可能とする見方を批判した〕。「論評」を契機として、党は、全党の意志の統一と固い団結のもとに、党の戦略方針を正しく確立する重大な任務に直面した。
このもっとも重要な期間に、党内の意見の対立が表面化し党の団結を保証することに失敗した。
一月十二日政治局は『日本の情勢について』にかんする「所感」を発表した。その内容は、国際批判の提起している問題点を戦略上の問題として正しく理解せず、誤りを犯す結果になった〔野坂の主張に誤りはあったが実践で克服済みだと反論した〕。その際、二名の政治局員〔志賀義雄と宮本顕治〕が「所感」に反対し、ついで三名の書記局員〔亀山幸三、春日庄次郎、袴田里見〕が反対した。「論評」をめぐる論争のなかで「所感」に反対するものが増加した〔人民日報も「論評」に同調したため、まだソ連や中共の影響下にあった党は動揺した〕。
〔中略〕
「所感」は撤回される結果となったが、「所感」の処理についての明確な決定と率直な自己批判がなされなかったために、「論評」と「所感」にたいする基本的態度の問題をめぐって党内の対立が拡大した。〔中略〕
四月末にひらかれた第十九回中央委員会総会は、〔中略〕アメリカ帝国主義が党を非合法化する意図が明らかになった事態に対処して、全政治局員をはじめ全党員が一致団結してこれとたたかうことを決意した。
ところがその直後、政治局の多数は十九中総の決定と党の規約を無視して、「所感」に反対する同志たちを除外して、非合法体制の準備をすすめた。〔中略〕
六月六日、わが党の中央委員にたいするマッカーサーの公職追放令がだされた。翌七日にはアカハタ編集部員十七名が追放された。この弾圧にたいして政治局の多数は、この命令の執行には二十日の猶余があったにもかかわらず、その間に政治局や中央委員会を開き意志の統一によって、これと断固としてたたかう処置をとらずに、意見を異にする七人の中央委員を排除して、一方的に非合法体制に移行した。六月七日に臨時中央指導部が任命され、「中央委員の追放にともない、中央委員会の機能は実質上停止のやむなきにいたった」との声明がだされた。これによって第六回大会で選出された中央委員会は統一的機能を失い、事実上解体されてしまった。このことは重大な誤りである。
〔中略〕七名の中央委員は、このような事態にあたって、中央委員としての責任において、中央委員会および全党の原則的統一のためにたたかうという基本的な立場から事態を収集〔原文ママ〕するために協議した。その結果、〔中略〕十余の府県組織といくつかの大衆団体グループをその指導下に結集し、公然機関として全国統一委員会をつくった。
九月三日、中国共産党機関紙「人民日報」は、「今こそ団結して敵に当るべきときである」という社説を発表した。九月十一日、全国統一委員会は、臨中〔臨時中央指導部〕に統一を申し入れた。十月三十日には、統一委員会は、中央委員会を統一するという原則に立って統一の実現を促進するという配慮のもとに、みずからその組織を解消する措置をとった。そして、中央委員会、政治局の機能の回復をかさねて提案したが、臨中側は、中央委員会の解体その他の既成事実の承認という建前からこれを拒否した。
〔中略〕分裂状態のもとで、一九五一年二月、第四回全国協議会がひらかれた。四全協は〔中略〕極左冒険主義的政策をうちだすとともに「スパイ分派の粉砕」、「中道派との闘争」として、統一を主張していた同志たちへの闘争を強調した。四全協は、党が組織的に分裂している状態のもとで一方的にひらかれたもので、正常なものではなかった。それは〔中略〕党の分裂状態を決定的に固定化した。統一を主張していた中央委員たちは〔中略〕公然機関を再建して全国統一会議を組織する方向にすすんだ。こうして〔中略〕両者のあいだにはげしい批判と攻撃がつづけられた。
〔中略〕二つの組織が公然と対立抗争する党の分裂状態は、大衆の不信と批判をうけ、党勢力は急速に減退した。
このような事態のもとで、四全協指導部の間に従来からの戦略や指導上の誤りが自己批判されはじめた。これらのことが分裂した双方のなかに統一への機運をつくりだし、両者の統一のための話し合いもすすんでいった。八月十四日のモスクワ放送〔コミンフォルムが徳田書記長ら主流派を支持〕を契機として、全国統一会議の結成を準備していた中央委員たちは下部組織を解体して、臨中のもとに統一する方向にすすんだ。
だが、四全協指導部は、これらの組織に属していた人びとに、分派としての自己批判を要求し、そのため復帰も順調に進まなかった。このような態度は基本的には六全協にいたるまで克服されず、党内問題の解決をおくらせる主要な原因となった。
一九五一年十月にひらかれた第五回全国協議会も、党の分裂状態を実質的に解決していない状態のなかでひらかれたもので不正常なものであることをまぬがれなかったが、ともかくも一本化された党の会議であった。(思想運動研究所編『日本共産党事典(資料編)』全貌社、1978、p.449-452)
五全協を、分裂状態が実質的に解決していないとしながらも、「ともかくも一本化された党の会議であった」と評価している。
私はこれまで、前回の記事で引用した不破哲三氏の発言のように、四全協も五全協も共に「分裂した一方の側の会議」だと思っていたが、どうも違うようだ。
調べてみると、この1951年には、四全協後に「国際派」の志賀義雄が自己批判して主流派に復帰したり、「所感派」である北京の徳田球一や臨中議長の椎野悦朗が自己批判したり、「国際派」が分裂したり、徳田(所感派)と袴田里見(国際派)がモスクワに赴き、スターリンが徳田を支持して袴田は自己批判し主流派入りするといったさまざまな出来事があり、単純な分裂ではなく、複雑な状態であったらしい。
特に、政治報告も触れているモスクワ放送でソ連の徳田支持が明確になってからは、「国際派」は腰砕けとなり、主流派への復帰への動きが進んだらしい。
だから、五全協を「ともかくも一本化された党の会議であった」と表現しているのだろう。
ならば、五全協で決定された51年綱領に基づく武装闘争路線については、「分裂した時期の一方の側の行動」として切り捨ててはいられないはずだが……。
前回の記事でも述べたように、平成元年2月18日の衆議院予算委員会での石山陽・公安調査庁長官の答弁には、
昭和二十六年に四全協、五全協という当時の党大会にかわるべき執行部機関による会合が行われて、有名な軍事方針が決定され、それが五全協、六全協へと引き継がれてまいりましたが、六全協でいわゆる極左冒険主義の反省が行われたわけであります。その際に、当時の決定によりますれば、五全協の軍事方針の決定については、一応、極左冒険主義はいかぬけれども、全体としては、これは当時の主流派、反主流派によって十分意見の統一によって行われたものだ、簡単に申し上げますれば、そのような趣旨が行われておりますので、単純な分派活動による一部のはね上がりだけがやったというふうな認定を実は私どもはしておらないわけでございます。
とあり、不破氏に否定されているのだが、この「全体としては、これは当時の主流派、反主流派によって十分意見の統一によって行われたもの」というのは、もしかすると、この第7回党大会の政治報告と六全協の決議を混同していたのかもしれない。
さて、中央委員会の政治報告はこう続く。
五全協で「日本共産党の当面の要求――新綱領」〔51年綱領〕が採択され発表された。〔中略〕この綱領には若干の重要な問題についてあやまりをふくんでいたが、しかし、多くの人びとに深い感銘をあたえ、かれらのたたかいを鼓舞し、激励した。
この方針にもとづいて、党は、アメリカ帝国主義と日本の反動勢力にたいするたたかいを積極的にすすめた。〔中略〕
以上にのべたような党活動における積極的な面はあるが、しかし、六全協にいたるこの期間に、党は、極左日和見主義とセクト主義の方針と戦術をとるという重大なあやまりをおかした。(前掲『日本共産党事典(資料編)』、p.452)
続いて、誤りの原因を多々並べ立て、中でも徳田球一による家父長的個人指導を強調し、伊藤律、志田重男、椎野悦朗といった指導者を名指しで批判している。
しかし、その誤りの具体的な内容には触れていない。軍事方針や武装闘争、山村工作隊や中核自衛隊、火炎びん闘争といった言葉は全く出てこない。
そして、51年綱領については、
六全協の決議は、全体として党の前進に積極的な役割を果たしたにもかかわらず、五一年綱領が完全に正しいと規定した。しかし、その後の党活動によって、五一年綱領にあやまりのあることが明らかになった。中央委員会はすでにその主要点を発表したが、そのあやまりから生まれた党の政治方針の不正確さは、党活動にいろいろな矛盾や動揺、停滞を生んだ。したがって、党中央委員会は、この綱領の改訂を提案する。これが本大会の主要議題の一つである。
〔中略〕
過去十年の間、党は曲折のある道を歩んできた。とくに、六全協前の数年間には、党の分裂、極左冒険主義等々の重大な誤りをおかした。六全協によって党は、これらの誤りの根本原因を明らかにし、党内の家父長的個人中心主義をのぞきさり、党の団結の基礎をつくり、大衆との結びつきの強化に一歩前進した。しかし、〔中略〕その成果はまだ十分ではない。
この政治報告では、新しい情勢にもとづく党活動の方針を確立するという任務とともに、党内にある主要な弱点や欠陥を明らかにし、その克服のための具体的方策を提起した。〔中略〕
第一に、不正確と誤りをもっていた「五一綱領」をあらためて、全党員の積極的な参加のもとに、日本の現実に適応した正しい戦略と戦術の基準を規定した「党章」草案を、われわれはつくりあげている。この草案をめぐる討論の成果を生かして全党の意志を統一し、全党が確信をもって前進することのできるような綱領をつくりあげよう。(前掲『日本共産党事典(資料編)』、p.458及びp.472)
と、六全協とはうってかわって誤りがあったことを認め、これに変わる「党章」草案を呈示するとしている。
この「党章」とは、綱領と規約を合わせたもので、この第7回党大会後に書記長に選出される宮本顕治の主導により草案が作成され、既に前年に公表されていた。
宮本らは、この党大会での採択を図ったが、中央に春日庄次郎ら少数の反対派がおり、大会でも代議員の3分の2以上の賛成が得られなかったため、規約のみを決定し、綱領については持ち越しとなった。
では、この大会で 宮本は 51年綱領についてどう述べていたのだろうか。
先の文書の引用元である『日本共産党事典(資料編)』には、この大会での宮本による綱領問題についての報告も収録されているのだが、一部しか収録されていない。
ネットで検索してみると、「日本共産党資料館」なるサイト(党内異論派のサイト「さざ波通信」と関係があるようだ)に、この宮本による報告の大部分が掲載されていた。
「綱領問題についての中央委員会の報告(1)」というページから引用する。
1947年にひらかれた第6回党大会で、わが党は新しい行動綱領を採択した。同時に大会の決議で次期大会に提出する綱領の起草委員会を任命した。1950年の第18回中央委員会総会は、わが党内にあったアメリカ帝国主義への正しくない見解を克服するうえで重要な意義をもった。その後第19回中央委員会総会は綱領問題についての下案(政治局の多数案として提出されたもので、正式原案以前のもの)を検討して、それについての全党的な討議が開始されることとなった。討議の問題点は戦後の情勢、階級関係の変化とそれにもとづく革命の展望にあった。しかるに、この討議は正しく発展されなかった。当時、党を支配していた家父長的個人中心指導は、討議を正しく民主的に発展させなかったばかりか、下案について、ことなった意見をもつものを、組織的に圧迫し排除する方向を強めた。第19回中央委員会総会は、政治局をふくむ全中央委員が一致団結して、党の統一を確保して闘争に進むことを声明した。しかるに6・6弾圧をきっかけに党中央委員会の解体、党の分裂という事態が表面化、そのような事態によって綱領問題の全党的な正しい検討の討議は妨げられた(これらの事情についてのより詳細な分析と評価は、中央委員会の1950年問題についての報告によってあつかわれる予定である)
「いわゆる1951年綱領」(「綱領―日本共産党の当面の要求」)は、このような党の分裂状態が正しく解決されない時期につくられた。
〔中略〕
51年綱領は、アメリカ帝国主義の日本にたいする占領支配への闘争とそれからの解放を革命の課題として強調した。
またアメリカのたくらんだ単独講和の道が、ソ連邦、中国との戦争準備の道であること、「アメリカ帝国主義は、アジアにおけるかれらの支配を日本人の手と血で獲得するために、日本を新らしい侵略戦争にひき入れようとしている」ことを指摘して平和愛好諸国との平和と協力の道を呼びかけた。
こうして、アメリカ帝国主義との闘争を強調したことは、第6回大会後、党内外で提起されつつあったアメリカ帝国主義との闘争課題に一つの重要な定式化を与えたものであった。
51年綱領は「民主日本の自由と繁栄のために闘っているいっさいの進歩的な勢力の民族解放民主統一戦線」の組織を革命の力として決定的に重視した。
1948年3月、わが党中央委員会は「光栄ある民主日本を建設するために、民主主義の徹底、働く人民の生活の安定と向上、日本の完全な独立」を基本目標とする民主民族戦線の結成を提起したが、この統一戦線の課題を革命闘争前進の中心任務として規定したことは、重要な積極的意義をもっていた。
しかし当時は、独立のための闘争課題の過小評価とともにこの統一戦線の意義を理論的にも実践的にも軽視する傾向が党の指導にも根強かった。
この数年間、わが国人民の闘争は独立と平和のための闘争において大きな前進を示したが、それには戦後――とくに第6回大会後わが党の陣列のなかでアメリカ帝国主義の日本支配と新らしい戦争準備への闘争課題が討議され、強調されてきたことも、少なからぬ役割を果たしてきた。51年綱領はこの方向に一つの重要な歴史的な役割を果した。この綱領はアメリカ帝国主義が日本を「目したの同盟者」として戦争にひきいれようとしていること、「吉田政府はアメリカ占領当局のツイタテと支柱になることに賛成している」というような米日反動の利害の一致等について正しく問題を提起した。
それにもかかわらず、この綱領はつぎのような誤りと欠陥をもっていた。戦後の内外情勢の変化、日本資本主義の現段階および農村の生産関係の変化およびそれと関連した日本の反動勢力の実体――とくに絶対主義的天皇制と寄生地主的土地所有制の変化から生まれたものを正しくとらえることができなかった。そのため綱領は誤った規定と一面化を内包するものとなった。
この綱領は、以上のような弱点のほか、それがつくられた1951年8月いらい内外惰勢がすでに変化したため、今日では個々の命題や記述だけでなく、全体の叙述も、不適当なものになっている。
6全協決議が「新しい綱領が採用されてからのちに起ったいろいろのできごとと、党の経験は、綱領に示されているすべての規定が、完全に正しいことを実際に証明している」と書いているのは正しくなかった。
これらの問題点の若干については、すでに6全協後、7中総、8中総の決議がその検討を呼びかけてきた。われわれはこれにもとづいて51年綱領を全体として検討した結果、新しい綱領の方向を提示するとともに、つぎの諸点を明らかにする必要があると考える。
51年綱領は、アメリカ帝国主義の日本支配という戦後日本の重大な特質を分析するにさいして、アメリカ帝国主義の対日支配が、民族的主権への抑圧と日本を新しい侵略戦争へひきこむことにあると強調しているが、その中には、「かれらは日本工業にとどめをさそうとしている」というような単純すぎる叙述がある。
〔中略〕
「土地を買う金のない大部分の農民にとっては、この『農地改革』がなにも与えなかったことは明らかである」「現在日本農民に土地が少いのは最良の土地が寄生地主その他大きな土地を所有しているものに占められているからである」という土地問題、農地改革についての評価は、再検討の結果にてらせば、事実を正しく反映していない。
51年綱領は、日本の「反民族的反動勢力」として「天皇、旧反動軍閥、特権官僚、寄生地主、独占資本、つまり日本国民を搾取し、あるいはこの搾取を激励するいっさいのもの」であると規定している。これは戦後の階級関係の変化の結果を当時においても正しく反映していない。
51年綱領は「新らしい民族解放民主政府が、妨害なしに平和的な方法で自然に生まれると考えたり、あるいは反動的な吉田政府が、新らしい民主政府に自分の地位をゆずるために、抵抗しないでみずから進んで政権をなげだすと考えるのは重大な誤りである」「日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがいである」とのべている。
たしかに、反民族的反人民的政府がやすやすとその政権をなげだすと考えることは、今日でも正しくない。しかし根本的に変化した国際情勢とサンフランシスコ条約以後の日本の情勢において、われわれが革命を平和の手段によって達成する可能性はあり得ないと断定し、自らの手をしばりつけることは、再検討を必要としている。
51年綱領はさきにあげた歴史的成果にもかかわらず、これらの点で再検討が必要である。それは第7回および第8回中央委員会総会で提起された51年綱領の二つの問題点の再検討だけにとどまることはできない。今日の革命運動のむかうべき基本的進路を定めるために必要な問題――戦後の内外情勢と階級関係の変化、および解放闘争の主体的条件の基本点についての新らしい探究によってこそ、包括的な解明に近づくことができる。
51年綱領は「一つの重要な歴史的な役割を果した」と評価しながらも「誤りと欠陥をもっていた」から「再検討が必要であ」り、「新しい綱領の方向を提示」するとしている。
ここでも「誤りと欠陥」によって何がもたらされたかには触れていない。
軍事方針とか武装闘争路線といった言葉も出てこない。
では、言葉にしないまでも、失敗に終わった武装闘争路線はもう採らず、議会で多数派を得て平和革命を目指すのか。
宮本はそうは言わない。
この報告の中に、次のような記述がある。
革命への道すじに関していくつかの重要な問題がある。
(1)その一つは、過渡期のよりましな政府と、統一戦線の政府と革命の政府の問題である。
わが党は、強大な統一戦線を結集し、その基礎のうえに統一戦線の政府をつくるために奮闘する。これは、アメリカ帝国主義と日本の反動勢力のあらゆる妨害に抗しての闘争である。この統一戦線政府の樹立が革命の政府となるかどうかは、それを支える統一戦線の力の成長の程度にかかっている。統一戦線が一応人民の支持をうることに成功しても、敵の力にたいしてまだ十分強くないときには不安定な過渡期状態で民主的政府が成立することもありうる。
また統一戦線における指導権がまだ労働者階級に確保されない場合には、それは革命の課題を確実に遂行する保証をもちえない。しかし、統一戦線が人民の絶対的多数の土台に成立し、また、この統一戦線のうえにおける労働者階級と前衛党の比重がたしかなものになったような条件で、新しい政府が樹立されるならば、それは革命の課題を遂行しうる政府となるだろう。
統一戦線政府が樹立されるまでの過程で、よりましな政府の可能性の問題について無関心であってはならない。階級諸勢力の相互矛盾の関係に変化が生じた場合、統一戦線の政府ではないが、米日反動の支配を部分的にも一時的に妨げうるような政府ができる場合には、一定の条件のもとで、それを支持することを避けるべきではない。
そのさい、統一戦線とその政府の役割の重要性についての強調をおこたってはならない。また党はより反動的な政府ができることにたいして闘わなければならないが、そのさい誤って、本質的には米日支配層の利益を代表する政府を支持するような態度におちいってはならない。
(2)革命が非流血的な方法で遂行されることはのぞましいことである。
世界の社会主義と平和・独立の勢力が画期的に大きく成長した世界情勢のもとで、アメリカ占領軍の全面的な占領支配が今日のような支配形態となり、サンフランシスコ体制によって制約されているとはいえ、今日の憲法が一応政治社会生活を規制する法制上の基準とされている情勢では大衆闘争を基礎にして、国会を独占資本の支配の武器から人民の支配の武器に転化さすという可能性が生じている。
しかし反動勢力が弾圧機関を武器として人民闘争の非流血的な前進を不可能にする措置に出た場合には、それにたいする闘争も避けることができないのは当然である。支配階級がその権力をやすやすと手ばなすもので決してないということは、歴史の教訓の示すところである。
われわれは反動勢力が日本人民の多数の意志にさからって、無益な流血的な弾圧の道に出ないように、人民の力を強めるべきであるが、同時に最後的には反革命勢力の出方によって決定される性質の問題であるということもつねに忘れるべきではない。
1956年6月の7中総の決議がこの問題について、51年綱領の再検討を呼びかけたことは、当然の根拠があった。この決議の問題提起にたいしては、その後いくつかの種類の意見が出されてきた。
一つは、平和革命必然論の観点に立つべきであるのに、決議はそうなっていないという意見である。
一つは、非流血的方法による革命の可能性がサンフランシスコ体制後生じたのではなく戦後からあったのだという意見である。
一つは、この決議が平和革命必然論になっているものとみなしてそれは正しくないという意見である。
一つは、暴力革命必然論の立場からの反対である。
一つは、この決議が、革命政府が「内戦をともなうことなしに『平和的』に成立しうる可能性がある」条件としてあげているものは今日のところ抽象的な可能性であるから、そのような可能性をうんぬんすべきではない。現実的な可能性があるときのみに「可能性」をうんぬんすべきであるという意見である。
われわれは、これらの意見に賛成することはできない。
7中総の決議は内外の情勢の変化をあげ、国際的には世界の社会主義と平和・独立勢力の画期的な発展、国内的にはサンフランシスコ体制以後の情勢変化について示している。そして言論・集会・結社の自由、民主的な選挙法と国会の民主的運営、民族解放民主統一戦線の発展と労働者階級の前衛党の強大化という三つの条件があるとき、民主的な党派が国会において多数をしめ、その政府をつくりうること、「このような政府は、その国民との結合、国民からの支持および政府を構成する民主党派の指導性や統一行動の確固さに応じて――内外の力関係に応じた進歩的、革命的な政策を実行できる」という可能性をあげている。
このような条件と可能性は今日の内外情勢において空想的なものではなく、歴史的・理論的な可能性をもっている。このことは、この決議の発表された直後の選挙の結果においても確かめられている。
そして、51年綱領が「日本の解放の民主的変革を、平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがいである」という断定をおこなって、そのような変革の歴史的・理論的可能性のいっさいを思想としても否定して、いわば暴力革命不可避論でみずからの手を一方的にしばりつけているのは、明らかに、今日の事態に適合しないものとなっている。したがって、7中総の決議は、どういう手段で革命が達成できるかは、最後的には敵の出方によって決まることであるから、一方的にみずからの手をしばるべきではないという基本的な見地に立っておこなわれた必要な問題提起であった。
平和的手段による移行の歴史的・理論的可能性をうんぬんできる条件が敗戦直後からではなく、サンフランシスコ条約以後に限定したのは、それ以前のアメリカ軍の「全一的支配」と異なって、サンフランシスコ条約以後は、サンフランシスコ体制の内部矛盾によって現在の憲法による民主的権利、国会運営、政府の成立の条件を米日支配層も、一応たてまえとしては認めざるをえないところにおかれているからである。だから、米日支配層は憲法や選挙法の改悪を熱望せざるをえないのである。
この矛盾に注目せず、単に米軍の半占領体制、米日反動の強力な軍事機関の存在というだけの理由で、暴力革命不可避論によってみずからの手をしばる態度を固執することは、この数年間の内外情勢の変化を創造的なマルクス・レーニン主義で分析しない保守的な誤りをおかすものである。
また、7中総の決議は、平和革命必然論の立場をとっていないしとるべきではないという見地に立っている。したがって敵の出方が平和的な手段による革命達成を不可能にする場合を歴史的な可能性として考察することをおこたってはいけないのである。
「このような政府の樹立の前後、あるいは新政府による内外の転換、実施にたいして、米日反動勢力が非道な挑発、暴力的な手段をもって抵抗する可能性もある。また、革命運動の発展を未然におさえるために、民主勢力がまだ強大にならないうちに、暴圧を加える可能性のあることも見失ってはならない。
このような暴力的な弾圧や抵抗を米日反動がおこなうとしてもとうてい成功しないように、つねに内外の民主的世論をたかめ、平和・独立・民主勢力の団結力を強大にしておくことが、解放運動にとってきわめて重要である。
独立と平和の勢力があくまでも国民の権利と自由を維持して進むならば、反動勢力の出方によってどのような道をとろうとも、もっとも犠牲の少ない方法で反動の暴力から革命運動と新しい政府を効果的に防衛し、勝利の道を確実にすることができる。」(7中総決議)
7中総の決議は、まさに「反動勢力の出方によってどのような道をとろうとも」革命運動を効果的に防衛するには、内外の平和・独立・民主勢力の団結の強大化、人民の既得権の防衛が重大であることを指摘しているのである。
また、平和的な手段による革命の可能性の問題をいわば無条件的な必然性として定式化する「平和革命必然論」は、今日の反動勢力の武力装置を過小評価して、反動勢力の出方がこの問題でしめる重要性について原則的な評価を怠っている一種の修正主義的な誤りにおちいるものである。
暴力革命不可避論も正しくないが、平和革命必然論もまた正しくないとしている。
これが、今回の政府答弁書でも問題となった、いわゆる「敵の出方論」のルーツである。
「敵の出方論」とは元々このようなものであり、暴力のみを否定し、平和的手段のみをも否定する折衷的な見解であって、以前引用した国会質問で不破氏が述べていたような、反共クーデターといった事態のみを想定したものではない。
「反動勢力が弾圧機関を武器として人民闘争の非流血的な前進を不可能にする措置に出た場合」
「米日反動勢力が非道な挑発、暴力的な手段をもって抵抗する可能性」
「民主勢力がまだ強大にならないうちに、暴圧を加える可能性」
というが、「措置」「挑発」「暴力的な手段」「暴圧」とは具体的に何を意味するのか、明確でない。
例えば、共産党が非合法活動を行っていて、それに対して警察が動いたり、管轄する行政当局が指導を行ったりすることも、「措置」「挑発」「暴圧」に当たると判断されたりはしないだろうか。
今回問題になった、公安調査庁が共産党を調査対象としていることはどうか。
「敵の出方」は共産党側の「出方」によっても左右されるはずだが、共産党側がまずは常に合法的活動の枠内にとどまると宣言していないのは何故だろうか。
そして、しんぶん赤旗の記事が述べていたように、これで武装闘争路線を「第7回党大会で党が統一を回復したさいに明確に批判され、きっぱり否定された問題」だと言えるのだろうか。
軍事方針とか武装闘争路線といった言葉を用いていないのに、何を明確に批判しきっぱり否定したというのだろうか。
51年綱領自体についても、意義を認めているではないか。
51年綱領を「分裂した時期の一方の側の行動」だとして全否定するのは、宮本体制が確立したもっと後のことではないか。
なのに、しんぶん赤旗の記事は、第7回党大会から一貫して全否定しているかのように語っている。
以前にも述べたが、「歴史の事実を歪曲」しているのは誰なのだろうか。
なお、綱領論争はこの第7回党大会後も続き、結局春日庄次郎ら綱領反対派は排除され、1961年の第8回党大会では綱領草案は満場一致で決定された。
この時の綱領が、基本的には現在まで続いている。
(続く)










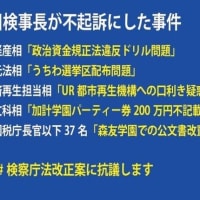

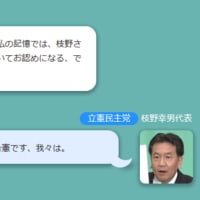
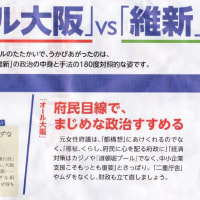


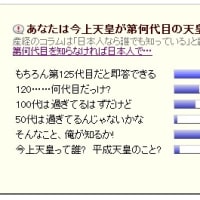
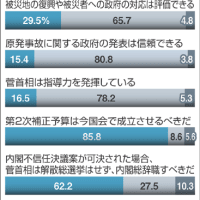


六全協の宣言や、その後の党の発出文書の内容は、党の延命と大衆化をにらんでの「暴力革命路線」を一時的に覆い隠すための方便でしかありません。
(実は「方便」にすらなっていない事は、ブログ主様の本シリーズ記事で明かなとおりですが。)
共産党というのは民進党などと違い、ある意味スジが通った政党で、党にとって綱領やその時々の公式文書が非常に重要で、逆に我々はそれを研究・解明する事によって問題点のほとんどを明かに出来ます。
なので、文書から読み解いて行くブログ主様の方法は共産党を対象にした場合すこぶる正しい。
ただ、文言や文章を巧みに操っているので、ブログ主様のように慎重かつ精緻な分析が必要で、相当の読解力がないと理解出来ないし、また意図してそのように作ってあるのです。
ところで共産党はなぜ、前非をありのままに認め一切の暴力革命路線を自己批判しないのでしょうか。
宣言し、綱領にそれを明確にする事で公安の見解を変える努力をなぜしないか、俄か支持者はそこを良く考えてもらいたいものです。
しかし、実はそれは出来ない相談なのでした。
それにはおおまかに三つの理由があります。
ひとつは、党内に今だ持って「造反有為」だの「抵抗の拠点」だのと、暴力を肯定する従来からの支持者が力を持っているからです。
もうひとつは伝統的に、日本共産党が政権を完全に掌握するまでのシナリオを見せていく事が必須であるとの考えに拠っています。
これは「科学的歴史観」と密接に関連した考えに立脚したもので、最終的には共産主義の世界になるのが「歴史の必然」なのですから、そこに至るまでの手段として、反動が公然の暴力を有している以上、共産党としても手段としての「暴力」はどこかで肯定されていなくては歴史そのものが完遂しないワケです。
つまり、「暴力」なくして共産主義の世の中の到来はありえない、という事を共産党自身が認識しているわけです。
もうひとつはこれは事実誤認でしょうが、旧社会党が取った「構造改革路線」に対する失望と警戒があります。
旧社会党は「構造改革路線」に舵を切ったゆえに衰退・滅亡した、との考えに基ずくものです。
いずれにせよ、共産党と「暴力」は理論上も実際的にも切っても切れない類縁関係にあるのが明かなもので、これは、党がどういうふうに糊塗しても免れるものではありません。