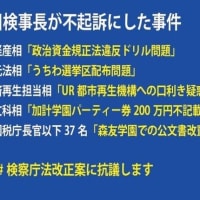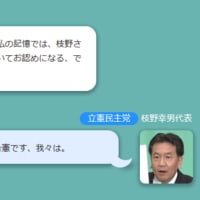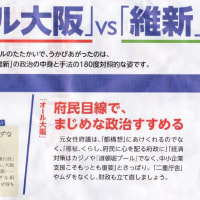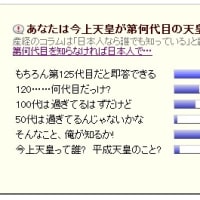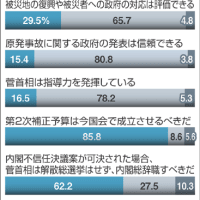著者は宗教学者。元日本女子大教授。たしか、オウム真理教を擁護している、あるいはカルト宗教に対する見方が甘いなどとして猛烈な批判を受け、教授辞任を余儀なくされたのではなかったか。
しかし、当時の私の印象では、地下鉄サリン事件以前は、統一教会などの問題は知られていたにしろ、カルト宗教に対する世間の視線は、今日ほど厳しいものではなかった。
島田のカルトへのアプローチに興味本位のウォッチャー的な面があったとは思うが、それにしてもあれほどのバッシングは異様だと感じていた。
例えば、同じ宗教学者であり、その著作がオウムに影響を与えたとも言われ、なおかつサリン事件の時に「もっと犠牲者が多かった方が、事件の意味があった」(うろ覚え)といった趣旨の発言を内輪でしていたということが暴露された中沢新一の方が、はるかに問題があると思っていた。
しかし、中沢は、批判は受けたものの、職を失うことはなかった。
その後の島田の活動はよく知らなかったが、最近では『創価学会』(新潮新書、2004)や『創価学会の実力』(朝日新聞社、2006)と創価学会関係の本を出している。
また、今年、中沢新一批判の本も出しているという。内容は知らないが、おそらく、中沢は安泰なのに何故自分がとの思いがあるのではないだろうか。
「鶴タブー」という言葉も未だにあるようだが、創価学会に関する本は、島田の著作以外にも、『別冊宝島 となりの創価学会』(1995)、朝日新聞アエラ編集部『創価学会解剖』(朝日文庫、1999)、『別冊宝島Real 池田大作なき後の創価学会』(2007)などいくつかあり、それを論じること自体は、近年では必ずしもタブーとは言い難いように思える。
しかし、公明党についてはどうだろう。島田は本書で次のように述べている。
《公明党について、あるいは公明党とその支持母体である創価学会との関係について、研究はほとんど進んでいない。公明党について専門に研究している人間は皆無であり、学術論文が書かれることもない。以前なら、とくに言論出版妨害事件が起こるまでは、ジャーナリストや研究者が公明党について、比較的客観的な立場から論じることはあった。
しかし、一九七〇年代以降は、公明党や創価学会のスキャンダルを暴こうとする、徹底して批判的な書物しか書かれなくなった。かつては、選挙戦で公明党と鍔迫り合いを演じてきた共産党や共産党系の研究者、ジャーナリストが公明党、創価学会の分析を進め、批判を展開していた。だが、共産党が退潮するなかで、そうした試みも少なくなってきた。》(p.10~11)
そのとおりだと思う。Amazonで「公明党」で検索してみるとよい。古川利明、平野貞夫、乙骨正生の著作が上位に並ぶが、これらは 島田の言う「徹底して批判的な書物」 だろう。しかも、公明党イコール創価学会として、本質的には後者を批判しているのだろう。
政党としての公明党を正面から論じているものとしては堀幸雄『公明党論―その行動と体質』(南窓社、1999)があるが、これは青木書店から1973年に刊行されたものの再刊で、内容的にはいささか古い。
本書は、そのような公明党研究の現状を塗り替えるものとなるだろう。
本書の帯には「公明党と創価学会は本当に一体なのか。」とある。
島田は、両者は必ずしも一枚岩ではないことをわかりやすく説明していく。
池田大作の「デージン」発言や、安倍晋三が首相就任直前に池田と会談していたことなどから、池田は公明党を通じて政治的に巨大な影響力を行使しているかのような印象がある。しかし、島田が論じるように、公明党の一挙一動を池田が指示しているという関係にはないことは確かなようだ。
言論出版妨害事件を機に、政教分離が唱えられて、両者は別組織とされた。それまでは公明党の議員は創価学会の幹部を兼務しており、まさに公明党は学会政治部の色彩が強かったという。しかし、両者が別組織となったことが、公明党を躍進させる上で有利に働いたと、島田は、ライバルである共産党と比較して説明する。
《共産党の場合は、候補者と支持者は同じ組織に属しており、組織が一体となって選挙戦にあたる。それに対して、公明党と創価学会は組織が分離されており、自動的に一体となって活動を展開するわけではない。
公明党の側は、直接創価学会の会員を動員することはできない。会員が動くのは、創価学会の組織の意向が定まったときで、個別の選挙でどの程度エネルギーをかけるかは、支援長などの判断で決まり、それが一般の会員に伝えられる。ワンクッションおかなければならない点で、共産党の方がはるかに効率的に思える。〔中略〕
しかし、現状においては、公明党と創価学会が別組織であることが、かえってエネルギーを生むことに結びついている。創価学会の方は、公明党議員の選挙活動を担う代わりに、議員の活動を監視し、コントロールできるからである。
〔中略〕公明党の議員は、個人で選挙の心配をすることがない代わりに、支援者である学会員の要望を実現していくという役割を負っている。学会員にとっては、公明党議員の活動があってこそ、自分たちの生活を充実させることができる。〔中略〕いつでも住民相談に応じてもらえる体制ができていることは、学会員の生活の安全、安心を保証している。
こうした体制ができあがっているために、公明党の議員も、創価学会の会員も、自分たちの役割を果たすために懸命に活動しなければならない。それも、公明党と創価学会が組織としては対等で、そこに上下関係がないからである。
共産党のような、あるいはかつての公明党、創価学会のような一体の組織では、議員と一般の支援者とは上下の関係になり、支援者は上の命令で動かされているという構図になってしまう。それでは、エネルギーが生まれないし、支援者が議員から厚く感謝され、ねぎらわれることもない。》(p.171~172)
島田は、自民党と公明党との連立は、民主党と公明党が連立する場合に比べて、相性がよいと主張している。民主党と公明党はともに都市部を基盤としている。公明党が都市部において弱い自民党を支援することにより自民党は大勝することができたが、民主党との連立ではこのような効果を発揮することは難しいという。
また、政策面でも、公明党は自民党より民主党に近い。しかし自民党と連携することにより、公明党はその独自性を発揮することができる。民主党との連携では、埋没しかねないという。それに、政権に参加することにより、その政策を実現することもできる。島田は、
《自民党も、連立が続くなかで、福祉政策にかんしては、公明党に依存するようになってきた。》(p.200)
とまで言う。
終章で島田は、創価学会会員の多様化により、学会員の公明党支持が薄れる可能性、さらにポスト池田の問題にも触れ、公明党の将来の不透明性にも触れている。
そして、劇場型政治の現代において、政治を盛り上げ、公明党の存在感を示すため、公明党はもっと自民党に対して異議申し立てをすべきだと説く。たとえ両党間で激しい議論が展開されても、もはや連立の枠組みが壊れることはあり得ない。2大政党制の中、そのような役割が公明党には求められていると島田は説く。
いくつか異論もあるが、総じて冷静な筆致には好感が持てる。
公明党の歴史と現状を把握するのにうってつけの好著。
島田には、ぜひ本格的な公明党史を書いていただきたいものだ。
しかし、当時の私の印象では、地下鉄サリン事件以前は、統一教会などの問題は知られていたにしろ、カルト宗教に対する世間の視線は、今日ほど厳しいものではなかった。
島田のカルトへのアプローチに興味本位のウォッチャー的な面があったとは思うが、それにしてもあれほどのバッシングは異様だと感じていた。
例えば、同じ宗教学者であり、その著作がオウムに影響を与えたとも言われ、なおかつサリン事件の時に「もっと犠牲者が多かった方が、事件の意味があった」(うろ覚え)といった趣旨の発言を内輪でしていたということが暴露された中沢新一の方が、はるかに問題があると思っていた。
しかし、中沢は、批判は受けたものの、職を失うことはなかった。
その後の島田の活動はよく知らなかったが、最近では『創価学会』(新潮新書、2004)や『創価学会の実力』(朝日新聞社、2006)と創価学会関係の本を出している。
また、今年、中沢新一批判の本も出しているという。内容は知らないが、おそらく、中沢は安泰なのに何故自分がとの思いがあるのではないだろうか。
「鶴タブー」という言葉も未だにあるようだが、創価学会に関する本は、島田の著作以外にも、『別冊宝島 となりの創価学会』(1995)、朝日新聞アエラ編集部『創価学会解剖』(朝日文庫、1999)、『別冊宝島Real 池田大作なき後の創価学会』(2007)などいくつかあり、それを論じること自体は、近年では必ずしもタブーとは言い難いように思える。
しかし、公明党についてはどうだろう。島田は本書で次のように述べている。
《公明党について、あるいは公明党とその支持母体である創価学会との関係について、研究はほとんど進んでいない。公明党について専門に研究している人間は皆無であり、学術論文が書かれることもない。以前なら、とくに言論出版妨害事件が起こるまでは、ジャーナリストや研究者が公明党について、比較的客観的な立場から論じることはあった。
しかし、一九七〇年代以降は、公明党や創価学会のスキャンダルを暴こうとする、徹底して批判的な書物しか書かれなくなった。かつては、選挙戦で公明党と鍔迫り合いを演じてきた共産党や共産党系の研究者、ジャーナリストが公明党、創価学会の分析を進め、批判を展開していた。だが、共産党が退潮するなかで、そうした試みも少なくなってきた。》(p.10~11)
そのとおりだと思う。Amazonで「公明党」で検索してみるとよい。古川利明、平野貞夫、乙骨正生の著作が上位に並ぶが、これらは 島田の言う「徹底して批判的な書物」 だろう。しかも、公明党イコール創価学会として、本質的には後者を批判しているのだろう。
政党としての公明党を正面から論じているものとしては堀幸雄『公明党論―その行動と体質』(南窓社、1999)があるが、これは青木書店から1973年に刊行されたものの再刊で、内容的にはいささか古い。
本書は、そのような公明党研究の現状を塗り替えるものとなるだろう。
本書の帯には「公明党と創価学会は本当に一体なのか。」とある。
島田は、両者は必ずしも一枚岩ではないことをわかりやすく説明していく。
池田大作の「デージン」発言や、安倍晋三が首相就任直前に池田と会談していたことなどから、池田は公明党を通じて政治的に巨大な影響力を行使しているかのような印象がある。しかし、島田が論じるように、公明党の一挙一動を池田が指示しているという関係にはないことは確かなようだ。
言論出版妨害事件を機に、政教分離が唱えられて、両者は別組織とされた。それまでは公明党の議員は創価学会の幹部を兼務しており、まさに公明党は学会政治部の色彩が強かったという。しかし、両者が別組織となったことが、公明党を躍進させる上で有利に働いたと、島田は、ライバルである共産党と比較して説明する。
《共産党の場合は、候補者と支持者は同じ組織に属しており、組織が一体となって選挙戦にあたる。それに対して、公明党と創価学会は組織が分離されており、自動的に一体となって活動を展開するわけではない。
公明党の側は、直接創価学会の会員を動員することはできない。会員が動くのは、創価学会の組織の意向が定まったときで、個別の選挙でどの程度エネルギーをかけるかは、支援長などの判断で決まり、それが一般の会員に伝えられる。ワンクッションおかなければならない点で、共産党の方がはるかに効率的に思える。〔中略〕
しかし、現状においては、公明党と創価学会が別組織であることが、かえってエネルギーを生むことに結びついている。創価学会の方は、公明党議員の選挙活動を担う代わりに、議員の活動を監視し、コントロールできるからである。
〔中略〕公明党の議員は、個人で選挙の心配をすることがない代わりに、支援者である学会員の要望を実現していくという役割を負っている。学会員にとっては、公明党議員の活動があってこそ、自分たちの生活を充実させることができる。〔中略〕いつでも住民相談に応じてもらえる体制ができていることは、学会員の生活の安全、安心を保証している。
こうした体制ができあがっているために、公明党の議員も、創価学会の会員も、自分たちの役割を果たすために懸命に活動しなければならない。それも、公明党と創価学会が組織としては対等で、そこに上下関係がないからである。
共産党のような、あるいはかつての公明党、創価学会のような一体の組織では、議員と一般の支援者とは上下の関係になり、支援者は上の命令で動かされているという構図になってしまう。それでは、エネルギーが生まれないし、支援者が議員から厚く感謝され、ねぎらわれることもない。》(p.171~172)
島田は、自民党と公明党との連立は、民主党と公明党が連立する場合に比べて、相性がよいと主張している。民主党と公明党はともに都市部を基盤としている。公明党が都市部において弱い自民党を支援することにより自民党は大勝することができたが、民主党との連立ではこのような効果を発揮することは難しいという。
また、政策面でも、公明党は自民党より民主党に近い。しかし自民党と連携することにより、公明党はその独自性を発揮することができる。民主党との連携では、埋没しかねないという。それに、政権に参加することにより、その政策を実現することもできる。島田は、
《自民党も、連立が続くなかで、福祉政策にかんしては、公明党に依存するようになってきた。》(p.200)
とまで言う。
終章で島田は、創価学会会員の多様化により、学会員の公明党支持が薄れる可能性、さらにポスト池田の問題にも触れ、公明党の将来の不透明性にも触れている。
そして、劇場型政治の現代において、政治を盛り上げ、公明党の存在感を示すため、公明党はもっと自民党に対して異議申し立てをすべきだと説く。たとえ両党間で激しい議論が展開されても、もはや連立の枠組みが壊れることはあり得ない。2大政党制の中、そのような役割が公明党には求められていると島田は説く。
いくつか異論もあるが、総じて冷静な筆致には好感が持てる。
公明党の歴史と現状を把握するのにうってつけの好著。
島田には、ぜひ本格的な公明党史を書いていただきたいものだ。