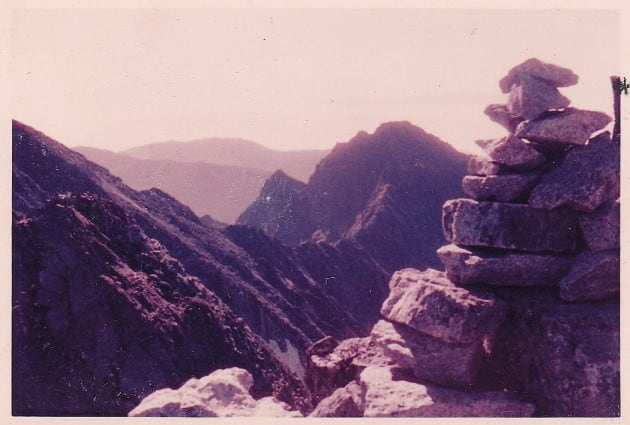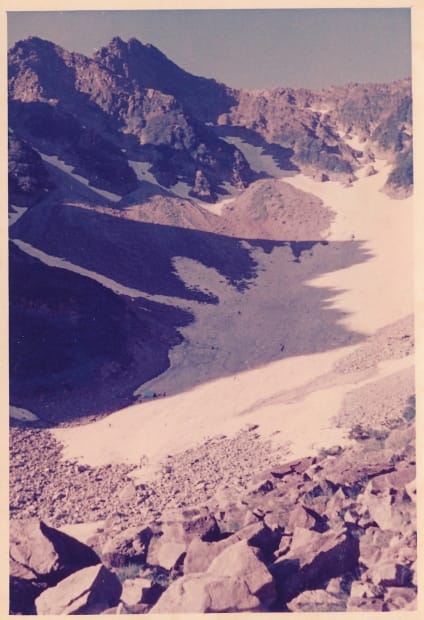この山旅は
縦走にしては写真の枚数が少ないので
35ミリの小さいカメラも持って
使い分けていたのかもしれません。
今のところ、この縦走に関する
他のネガフィルムは見つかっていないので
今回の記事で完結いたします。
∨
横通岳から下りて
鞍部の常念乗越になります。(現在)

標高2450m

(写真は加工してメガネをつけてもらいました。)
横通岳と常念岳の山頂は広くなくて
道標には左が常念小屋と書いてあるので

この写真は
常念乗越で撮ったことにしておきます。
*
常念小屋に向かう写真が2枚あり

1枚目は
左側の登山者の視線の先に
子供を背負った男性と
その後ろを歩く女性が写っていました。

ドラマチックな写真ですが
何があったのかを知る方法はありません。
∨
もう1枚は
常念小屋越しの大キレットです。

常念小屋のホームページにある山の形と
そっくりですので間違いないでしょう。

*
(現在)

∨
最後の写真は、どこで撮ったのか
判別できる情報はありません。

常念岳の山頂から撮った写真がないので
これがそうなのかと
勝手に解釈しています。
*
常念岳はまだ未踏破なので、
写真の謎を解明する楽しみも増え
ぜひ挑戦したいと思います。
end